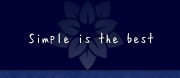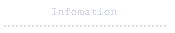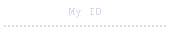م€گé،Œهگچم€‘Mikiمپ¨Shiori
م€گن½œè€…م€‘kuuko
م€گو—¥و™‚م€‘????
白éٹ€BBSم‚ˆم‚ٹ転載م€‚
第ن¸€è©±م€€م€€ç§پمپŒه½¼ه¥³م‚’ه¤§ه¥½مپچمپھçگ†ç”±
白مپ„ه¤©ن؛•مƒ»مƒ»مƒ»مپ©مپ“مپ«مپ§م‚‚مپ‚م‚‹ن؛Œوœ¬مپ®è›چه…‰çپ¯مƒ»مƒ»مƒ»
مپµمپ¨و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨م€پç§پمپ¯مƒ™مƒƒمƒ‰مپ«ه¯مپ‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚
م€Œمپ“مپ“مپ¯ï¼ںم€چ
ه£°م‚’ه‡؛مپمپ†مپ¨و€مپ£مپںمپŒم€پن½•مپ‹مپŒمپ®مپ©م‚’مپµمپ•مپ„مپ§مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ§م€پ
مپ‹مپ™م‚Œمپںمپ†م‚پمپچه£°مپ—مپ‹ه‡؛مپھمپ„م€‚
é،”مپŒه‹•مپ‹مپھمپ„م€‚
ç§پمپ¯مپ©مپ†مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ م‚چمپ†ï¼ں
白مپڈéœمپ®مپ‹مپ‹مپ£مپں視界مپŒم€پو™‚é–“مپ¨مپ¨م‚‚مپ«مپ™مپ“مپ—مپڑمپ¤ه؛ƒمپŒمپ£مپ¦مپ„مپڈم€‚
ç›®م‚’ن¸‹مپ«ه‹•مپ‹مپ—م€پè‡ھهˆ†مپ®ن½“مپ®و§کهگم‚’وژ¢م‚‹م€‚
مپ¾مپڑم€پé¼»مپ®ç©´مپ«é€ڈوکژمپھمƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–مپŒمپ•مپ•مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپŒç¢؛èھچمپ§مپچمپںم€‚
هڈ£م‚’é€ڑمپ—مپ¦م€پمپ®مپ©مپ«م‚‚مƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–مپŒé€ڑمپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
éپ“çگ†مپ§ه£°مپŒه‡؛مپھمپ„م‚ڈمپ‘مپ م€‚
مپ•م‚‰مپ«è–„مپ„وژ›مپ‘ه¸ƒه›£مپ®ن¸،脇مپ‹م‚‰ç„،و•°مپ®مƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–مپŒه‡؛مپ¦مپ„م‚‹مپ®م‚‚見مپˆمپںم€‚
è…•مپ«مپ¯ç‚¹و»´مپŒهˆ؛مپ•مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ن½“ه…¨ن½“مپŒمپ م‚‹مپ„م€‚
و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨و•ه…ƒمپ«ن¸€ن؛؛مپ®ه°‘ه¥³مپŒم€په؛§مپ£مپںمپ¾مپ¾مپ“مپڈم‚ٹمپ“مپڈم‚ٹمپ¨çœ مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
مپ»مپ¤م‚Œمپںé«ھمپŒه½¼ه¥³مپ®é ¬م‚’éڑ مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€Œمپمپ†مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»ç§پم€پهٹ©مپ‹مپ£مپںم‚“مپ م€‚م€چ
ه¾گم€…مپ«è¨کو†¶مپŒوˆ»مپ£مپ¦مپچمپںم€‚
ç§پمپ¯éپ؛è·،مپ«و½œمپ£مپ¦مپ„مپںمپ®مپ م€په½¼ه¥³م€پshioriمپ¨مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«م€‚
ن½“هٹ›مپŒه؟ƒè¨±مپھمپڈمپھم‚ٹم€پè–¬م‚‚مپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپچمپںمپ®مپ§م€پ
م€Œه¸°م‚چمپ†م€‚م€چ
مپ¨è¨€مپ£مپںمپ¨مپ“م‚چمپ¾مپ§مپ¯è¦ڑمپˆمپ¦مپ„م‚‹م€‚
ç›´ه¾Œم€پ背ن¸مپ«و؟€ç—›م‚’و„ںمپکم€پمپمپ®مپ¾مپ¾و°—م‚’ه¤±مپ£مپںمپ®مپ م€‚
è‡ھç”±مپھو–¹مپ®و‰‹مپ§م€پè‡ھهˆ†مپ®ن½“م‚’وژ¢مپ£مپ¦مپ؟م‚‹م€‚
هŒ…ه¸¯مپŒمپ´مپ£مپںم‚ٹه·»مپچن»کمپ‘مپ¦مپ‚مپ£مپںم€‚
ن½“م‚’ه°‘مپ—مپ²مپمپ£مپںç¬é–“م€په‚·هڈ£مپ®é–‹مپڈو؟€ç—›مپŒè¥²مپ£مپںم€‚
م€Œمپ†مپ£ï¼پم€چ
ç§پمپ®مپ†م‚پمپچه£°مپ«م€پçœ مپ£مپ¦مپ„مپںshioriمپŒç›®م‚’è¦ڑمپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمپ‚م€پMikiم€پو°—مپŒمپ¤مپ„مپںمپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپ†مپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œم‚ˆمپ‹مپ£مپںم€‚مپ“مپ®مپ¾مپ¾و»م‚“مپکم‚ƒمپ£مپںم‚‰مپ©مپ†مپ—م‚ˆمپ†مپ‹مپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
点و»´م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ†مپ®ç§پمپ®و‰‹م‚’وڈ،م‚ٹم€په½¼ه¥³مپ¯مپ½مپںمپ½مپںمپ¨و¶™م‚’èگ½مپ¨مپ—مپںم€‚
م€Œمپ‚مƒ»مƒ»مƒ»مپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ه£°م‚’ه‡؛مپمپ†مپ¨مپ™م‚‹مپŒم€پمپ†مپ¾مپڈمپ—م‚ƒمپ¹م‚Œمپھمپ„م€‚
م€Œمپ‚م€پç„،çگ†مپ«مپ—م‚ƒمپ¹م‚‰مپھمپ„مپ§م€‚مپ¾مپ مƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–مپŒمپ®مپ©مپ«هˆ؛مپ•مپ£مپںمپ¾م‚“مپ¾مپ مپ‹م‚‰م€‚م€چ
ç§پمپ¯ç›®مپ§مپ†مپھمپڑمپ„مپںم€‚
م€Œمپ¨مپ«مپ‹مپڈن»ٹمپٹهŒ»è€…مپ•م‚“ه‘¼مپ¶مپم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦ه½¼ه¥³مپ¯مƒ™مƒƒمƒ‰مپ®و¨ھمپ«مپ‚م‚‹èµ¤مپ„مƒ–م‚¶مƒ¼م‚’وٹ¼مپ—مپںم€‚
مپمپ—مپ¦م€پهŒ»è€…مپŒو¥م‚‹مپ¾مپ§ن¸،و‰‹مپ§ç§پمپ®و‰‹مپ®مپ²م‚‰م‚’هŒ…مپ؟è¾¼م‚€م‚ˆمپ†مپ«وڈ،مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
م€Œو°—مپŒمپ¤مپچمپ¾مپ—مپںمپ‹م€‚م€چ
هŒ»è€…مپŒه…¥مپ£مپ¦مپچمپ¦ç§پم‚’見مپ¤م‚پمپںم€‚
م€Œمپ©م‚Œم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦ç§پمپ®و‰‹é¦–م‚’هڈ–م‚ٹم€پ脈م‚’èھ؟مپ¹م‚‹م€‚
م€Œمپµم‚€مƒ»مƒ»مƒ»مپ¨م‚ٹمپ‚مپˆمپڑوœ€هˆمپ®ه±±مپ¯è¶ٹمپˆمپںم‚‰مپ—مپ„م€‚م€چ
م€Œوœ€هˆمپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»م‚‚مپ†ه¤§ن¸ˆه¤«مپھم‚“مپکم‚ƒï¼ںم€چ
shioriمپŒهŒ»è€…مپ®و–¹م‚’م€پو‡‡é،کمپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«è¨€مپ†م€‚
م€Œمپ¾مپ ه®‰ه؟ƒمپ¯مپ§مپچمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ¾مپ‚م€پم‚ˆمپڈمپ¦ن؛”هˆ†ن؛”هˆ†مپ¨مپ„مپ†مپ¨مپ“م‚چمپ§مپ™مپم€‚
م€€مپںمپ م€پمپ“مپ†مپ„مپ†مپ®مپ¯م€پوœ¬ن؛؛مپ®ن½•مپŒن½•مپ§م‚‚ç”ںمپچم‚ˆمپ†مپ¨و€مپ†ه¼·مپ„و„ڈه؟—مپŒه¤§ن؛‹مپ§مپ™م€‚
م€€مپ‘مپ£مپ—مپ¦è«¦م‚پمپھمپ„مپ“مپ¨م€‚絶ه¯¾و²»مپ—مپ¦م‚„م‚‹م‚“مپ مپ¨مپ„مپ†ه¼·مپ„و°—وŒپمپ،م‚’وŒپمپ¤مپ“مپ¨م€‚
م€€و‰€è©®مپ©م‚“مپھمپ«هŒ»ه¦مپŒé€²و©مپ—مپ¦م‚‚م€پ
م€€ç”ںه‘½مپŒوœ¬و¥وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹è‡ھ然و²»ç™’能هٹ›مپ«مپ¯م€پéپ مپڈهڈٹمپ³مپ¾مپ›م‚“م€‚
م€€وˆ‘م€…مپ¯مپم‚Œم‚’مپ»م‚“مپ®ه°‘مپ—مپٹو‰‹ن¼مپ„مپ—مپ¦مپ‚مپ’م‚‹مپ مپ‘مپھم‚“مپ§مپ™م€‚م€چ
هŒ»è€…مپ¯مپمپ†è¨€مپ†مپ¨م€پç§پمپ®é،”م‚’覗مپچè¾¼مپ؟م€پم‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œو®‹مپ•م‚Œمپں者م‚’و‚²مپ—مپ¾مپ›مپھمپ„مپںم‚پمپ«م‚‚م€پç”ںمپچمپھمپ•مپ„م€‚
م€€ç”ںمپچمپ¦م€پم‚‚مپ†ن¸€ه؛¦مپٹمپ„مپ—مپ„م‚‚مپ®م‚’مپٹè…¹مپ„مپ£مپ±مپ„é£ںمپ¹مپھمپ•مپ„م€‚م€چ
ç§پمپ¯ه°ڈمپ•مپڈé ·مپ„مپںم€‚
م€Œمپ¾مپڑمپ¯çœ م‚‹مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚مƒ–مƒ‰م‚¦ç³–مپ¯ç‚¹و»´مپ§ï¼’ï¼”و™‚é–“و³¨ه…¥مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€€ه¯مپ¦م€په›ه¾©مپ™م‚‹مپ®م‚’ه¾…مپ¤مپ®مپ§مپ™م€‚م€چ
مپمپ“مپ§ç§پمپ¯مپ¾مپ¶مپںم‚’é–‰مپکمپںم€‚
هŒ»è€…مپ®è©±م‚’èپمپڈمپ®مپ«مپ‘مپ£مپ“مپ†م‚¨مƒچمƒ«م‚®مƒ¼م‚’ن½؟مپ£مپںمپ®مپ م‚چمپ†م€‚
مپ™مپگمپ«و„ڈèکمپŒéپ مپ®مپ„مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
ن½•ه؛¦ç›®مپ‹مپ«ç›®مپŒè¦ڑم‚پمپںو™‚م€پهŒ»è€…مپ¯ç§پمپ®ه–‰مپ®مƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–م‚’وٹœمپ„مپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
و°´مپŒé£²مپ؟مپںمپ‹مپ£مپںمپŒم€پ
م€Œه½“هˆ†مپ¯é£²م‚€مپ®م‚‚é£ںمپ¹م‚‹مپ®م‚‚مپ‚مپچم‚‰م‚پمپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
م€€مپ‚مپھمپںمپ®ه†…臓مپ¯م€پمپ¾مپ و¶ˆهŒ–و´»ه‹•مپ«è€گمپˆم‚‰م‚Œم‚‹çٹ¶و…‹مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚م€چ
مپ¨هŒ»è€…مپ«è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ¯م€پمپ‚مپچم‚‰م‚پم‚‹مپ—مپ‹مپھمپ„م€‚
مپ¨مپ«مپ‹مپڈهچ±é™؛مپھçٹ¶و…‹مپ‹م‚‰مپ¯è„±مپ—مپ¤مپ¤مپ‚م‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
shioriمپŒو¹؟م‚‰مپ›مپںم‚¬مƒ¼م‚¼مپ§ç§پمپ®هڈ£م‚’و‹مپ„مپ¦مپڈم‚Œمپںمپ®مپ§م€پ
مپھم‚“مپ¨مپ‹مپ—م‚ƒمپ¹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚
م€Œshioriمپ¯م€پمپ‚مپ®و™‚م€په¤§ن¸ˆه¤«مپ مپ£مپںمپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€په¤§ن¸ˆه¤«م€‚مپ‚مپ®و™‚هپ¶ç„¶م€پمƒ†مƒ¬مƒ‘م‚¤مƒ—مپŒن¸€مپ¤م€پè؟‘مپڈمپ«è»¢مپŒمپ£مپ¦مپ„مپںمپ®م€‚
م€€و¨ھمپ£é£›مپ³مپ«مپ¤مپ‹م‚“مپ§Mikiم‚’وٹ±مپˆمپ¦è،—مپ«وˆ»مپ£مپںم‚ڈمƒ»مƒ»مƒ»م€‚م€چ
م€Œمپمپ£مپ‹م€پمپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚مپٹمپ‹مپ’مپ§هٹ©مپ‹مپ£مپںم‚“مپ م€‚shioriمپ¯ç§پمپ®ه‘½مپ®وپ©ن؛؛مپ مپھم€‚م€چ
م€Œمپ†مپ†م‚“م€پمپمپ†مپکم‚ƒمپھمپ„م€‚م€چ
shioriمپ¯çھپ然ن¸‹م‚’هگ‘مپ„مپںم€‚
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںم‚“مپ ï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€پمپ‚مپ®مپم€پç§پمپ‚م‚„مپ¾م‚‰مپھمپڈمپ£مپ،م‚ƒم€‚م€چ
م€Œمپھمپ«م‚’ï¼ںم€چ
م€ŒMikiمپŒمپ“م‚“مپھمپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپ،م‚ƒمپ£مپںمپ®مپ¯م€پç§پمپ®مپ›مپ„مپھم‚“مپ م€‚م€چ
ç§پمپ¯shioriمپŒن½•م‚’言مپ„ه‡؛مپمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ‹م€پمپھم‚“مپ¨مپھمپڈو°—مپŒمپ¤مپ„مپ¦مپ„مپںم€‚
م€Œمپ‚م‚Œم€پمپمپ†مپ مپ£مپ‘مپ‹ï¼ںم€چ
م‚ڈمپ–مپ¨مپ¨مپ¼مپ‘مپ¦è¨€مپ£مپ¦مپ؟مپںمپŒم€پمپ‚مپ¾م‚ٹهٹ¹وœمپ¯مپھمپ‹مپ£مپںم‚ˆمپ†مپ م€‚
م€Œهˆ†مپ‹مپ£مپ¦م‚‹مپ®م€پمپ‚مپ®و™‚م€پMikiمپ¯م€پم‚‚مپ†è–¬مپŒمپھمپ„مپ‹م‚‰è،—مپ«ه¸°م‚چمپ†مپ£مپ¦è¨€مپ£مپںمپ§
مپ—م‚‡م€‚م€چ
مپںمپ—مپ‹مپ«مپمپ†è¨€مپ£مپںم€‚è¦ڑمپˆمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ مپŒمƒ»مƒ»مƒ»
م€Œمپ‚مپ®و™‚ç§پم€پمپ،م‚‡مپ†مپ©ç›®مپ®ه‰چمپ«م‚´مƒƒمƒ‰مƒ‘مƒ¯مƒ¼مپŒèگ½مپ،مپ¦م‚‹مپ®مپ«و°—مپŒمپ¤مپ„مپںمپ®م€‚
م€€مپ“م‚Œمپ•مپˆو‰‹مپ«ه…¥م‚Œم‚Œمپ°م€پç§پمپ®و¦ه™¨م‚‚ه¤§ه¹…مپ«مƒ‘مƒ¯مƒ¼م‚¢مƒƒمƒ—مپ™م‚‹م€‚
م€€مپمپ—مپںم‚‰è–¬مپŒمپھمپڈمپ¦م‚‚م€پم‚‚مپ†مپ—مپ°م‚‰مپڈمپ¯م€پوˆ¦مپ£مپ¦مپ„مپ‘م‚‹م€‚
م€€مƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†و€مپ£مپ¦مپںمپ®مƒ»مƒ»مƒ»ç”کمپ‹مپ£مپںمپ®م‚ˆم€‚م€چ
shioriمپŒن»ٹه›مپ®مپ“مپ¨مپ§è‡ھهˆ†م‚’責م‚پمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ«مپ¯è–„م€…و„ںمپ¥مپ„مپ¦مپ„مپںم€‚
م€Œمپم‚Œمپ¯çµگوœè«–مپ م‚ˆم€پshioriم€‚مپمپ†م‚„مپ£مپ¦è‡ھهˆ†م‚’責م‚پمپ،م‚ƒمƒ€مƒ،مپ م‚ˆم€‚
م€€مپم‚Œمپ«ç§پم€پمپ“مپ†مپ—مپ¦هٹ©مپ‹مپ£مپںم‚“مپ مپ‹م‚‰مپ„مپ„مپکم‚ƒمپھمپ„م€‚م€چ
م€Œç§پم€پمƒ•م‚©مƒ¼م‚¹ه¤±و ¼مپ مپم€‚ه¤§هˆ‡مپھ相و£’م‚’مپ“م‚“مپھç›®مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ،م‚ƒمپ†مپھم‚“مپ¦م€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€مƒ»مƒ»مƒ»مپ”م‚پم‚“م€پمپ”م‚پم‚“مپم€پمپ»م‚“مپ¨مپ«مپ”م‚پم‚“مپم€‚م€چ
وœ¬و ¼çڑ„مپ«و³£مپچه‡؛مپ—مپںshioriم‚’م€پç§پمپ¯مپ©مپ†مپ—مپںم‚‰مپ„مپ„م‚‚مپ®مپ‹مپ¨è€ƒمپˆè¾¼م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ£مپںم€‚
م€Œمپ مپ„مپںمپ„ç§پمپ¨Mikiمپ¨مپکم‚ƒم€پم‚‚مپ¨م‚‚مپ¨مƒپمƒ¼مƒ م‚’組م‚€مپ®مپ«
م€€é‡£م‚ٹهگˆمپ„مپŒهڈ–م‚Œمپ¦مپھمپ‹مپ£مپںمپ®م‚ˆم€‚
م€€Mikiمپ¯مپ„مپ¤مپ§م‚‚ه†·é™مپھمپ®مپ«م€پ
م€€ç§پمپ¨مپچمپںم‚‰مپمپ®و™‚مپ®و„ںوƒ…مپ§è،Œه‹•مپ—مپ،م‚ƒمپ†مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»
م€€مپ مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپم‚“مپھمپ“مپ¨مپ¯مپھمپ„م€‚م€چ
م€Œç§پمپ®مپ›مپ„مپ§Mikiم€پمپ“م‚“مپھمپ«مپٹè…¹ه‚·مپ م‚‰مپ‘مپ«مپھمپ£مپ،م‚ƒمپ£مپ¦
م€€مƒ»مƒ»مƒ»م‚‚مپ†ن؛؛ه‰چمپ§و°´ç€مپ مپ£مپ¦ç€م‚‰م‚Œمپھمپ„م€‚مپ™مپ”مپڈمپچم‚Œمپ„مپھن½“مپ—مپ¦م‚‹مپ®مپ«م€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپم‚“مپھمپ“مپ¨مپ§و³£مپ„مپ¦مپ„مپںمپ®مپ‹م€‚م€چ
è‡ھهˆ†مپ®مپٹè…¹مپ®çٹ¶و…‹م‚’見مپھمپŒم‚‰ç§پمپ¯مپںم‚پوپ¯م‚’مپ¤مپ„مپںم€‚
مپںمپ—مپ‹مپ«مپ²مپ©مپ„وœ‰و§کمپ م€‚ه‚·م‚’و¶ˆو¯’مپ™م‚‹و™‚مپ«ن½•ه؛¦مپ‹è¦‹مپںمپ®مپ مپŒم€پ
م‚«م‚ھم‚¹مƒ–مƒھمƒ³م‚¬مƒ¼مپ«هˆ؛مپ•م‚Œمپںç©´مپŒن¸€مپ¤م€پو‰‹è،“مپ§هˆ‡مپ£مپںè·،مپŒم€پ
مپ؟مپمپٹمپ،مپ‹م‚‰مپٹمپ¸مپمپ«مپ‹مپ‘مپ¦ç´„11م‚»مƒ³مƒپم€پ
مپمپ®ن»–مپ«م‚‚腹腔ه†…مپ®è†؟م‚’هگ¸مپ„ه‡؛مپ™مپںم‚پمپ®مƒ‘م‚¤مƒ—مپŒمپ‚مپ،مپ“مپ،مپ«هں‹م‚پم‚‰م‚Œمپ¦م€پ
و‚²وƒ¨مپھم‚‚مپ®مپ مپ£مپںم€‚مپ“م‚ŒمپŒè‡ھهˆ†مپ®ن½“مپ مپ¨èھچم‚پم‚‹مپ®مپ«مپ¯éڑڈهˆ†مپ¨ه‹‡و°—مپŒم€پ
مپمپ—مپ¦ه°‘مپ—مپ°مپ‹م‚ٹمپ®مپ‚مپچم‚‰م‚پمپŒه؟…è¦پمپ مپ£مپںم€‚
م€ŒMikiمپ¯ç§پم‚ˆم‚ٹمپڑمپ£مپ¨مپ™م‚‰مپ£مپ¨مپ—مپ¦مپ¦م€پو‰‹è¶³م‚‚é•·مپ„مپ—م€پ
م€€م‚¦م‚¨م‚¹مƒˆمپ مپ£مپ¦مپچم‚…مپ£مپ¨مپڈمپ³م‚Œمپ¦م‚‹مپ—مƒ»مƒ»مƒ»ç§پمپ،مپ³مپ مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»
م€€مپ‚مپ“مپŒم‚Œمپ¦مپںمپ®م€‚مپم‚Œمپھمپ®مپ«م€‚م€چ
م€Œه¤–見مپھم‚“مپ‹مپ©مپ†مپ§م‚‚مپ„مپ„م‚“مپ م€‚م€چ
م€Œمپ مپ£مپ¦م€چ
م€Œمپ„مپ„مپ‹م‚‰èپمپ‘م€‚م€چ
و€م‚ڈمپڑه‘½ن»¤هڈ£èھ؟مپ§è¨€مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںم€‚
م€Œç§پمپŒshioriمپ¨مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«مپ„مپںمپ„مپ¨و€مپ†مپ®مپ«مپ¯çگ†ç”±مپŒمپ‚م‚‹م‚“مپ م€‚م€چ
مپمپ—مپ¦ç§پمپ¯م€پمپھمپœمپ‹مپ“م‚“مپھ話م‚’مپ¯مپکم‚پمپںمپ®مپ مپ£مپںمƒ»مƒ»مƒ»م€‚
ه¤©و°—مپ®م‚ˆمپ„هچˆه¾Œمپ مپ£مپںم€‚ç§پمپ¯هڈ‹ن؛؛مپ¨ن¸‹ç”؛م‚’و©مپ„مپ¦مپ„مپںم€‚
ه½¼ه¥³مپ¯مپ،م‚‡مپ£مپ¨ه°ڈوں„مپھم€پمپ§م‚‚首مپŒç´°مپڈمپ¦م€پ
مپ‚مپ”مپ¨é¼»مپ®ç·ڑمپŒمپ™مپ£مپچم‚ٹمپ¨مپ—مپںه¥³مپ®هگمپ مپ£مپںم€‚
مپ‚مپ¾م‚ٹè»ٹمپ®é€ڑم‚‰مپھمپ„é™مپ‹مپھéپ“مپ مپ£مپںم€‚
ن¸‹ç”؛مپ مپ‹م‚‰مپںمپ¾مپ«é€ڑم‚‹è»ٹم‚‚م€پن¸€و™‚ن»£ه‰چمپ®هچٹè‡ھه‹•éپ‹è»¢هˆ¶ه¾،م‚؟م‚¤مƒ—مپ م€‚
è،Œمپچمپ¤مپ‘مپ®ه–«èŒ¶ه؛—م‚پمپ–مپ—مپ¦م€پمپ®م‚“مپ³م‚ٹمپ¨و©مپڈم€‚
مپ،م‚‡مپ†مپ©ن؛¤ه·®ç‚¹مپ«ه·®مپ—وژ›مپ‹مپ‹مپ£مپںو™‚م€پهگ猫مپ®و³£مپچه£°مپŒمپ—مپںم€‚
مپ¾مپ ن¸–مپ®ن¸مپ«ه‡؛مپ¦é–“م‚‚مپھمپ„مپ م‚چمپ†هگ猫مپ م€‚
ن؛¤ه·®ç‚¹مپ®çœںم‚“ن¸مپ«مپ،م‚‡مپ“م‚“مپ¨ه؛§مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
هگ‘مپ“مپ†مپ‹م‚‰è»ٹمپŒè؟‘مپ¥مپ„مپ¦مپڈم‚‹م€‚
م€Œمپ©مپ‘م‚ˆم€‚م€چ
مپ¨مپ„مپ†و„ںمپکمپ§م€پن»ٹو™‚çڈچمپ—مپ„و‰‹ه‹•مپ®م‚¯مƒ©م‚¯م‚·مƒ§مƒ³م‚’مپھم‚‰مپ™م€‚
猫مپ¯مپ©مپ†مپ—مپںم‚‰مپ„مپ„مپ®مپ‹م€پمپ¨مپ¾مپ©مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ç§پمپ¯
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپ‚مپ®çŒ«مپ¯م€پمپ“مپ†مپ„مپ†و™‚مپ©مپ†مپ—مپںم‚‰مپ„مپ„مپ‹م€پمپ¾مپ م‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپ„م‚“مپ مپھم€‚
م€€ه‰چمپ«é€²م‚“مپ م‚‰مپ„مپ„مپ®مپ‹م€‚ه¾Œم‚چمپ«مپ•مپŒمپ£مپںم‚‰مپ„مپ„مپ®مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»هڈ¯ه“€وƒ³مپ مپ‘مپ©م€پ
م€€ن¸–مپ®ن¸مپ®مپ“مپ¨م‚’ه¦ç؟’ن¸چ足مپھم‚“مپ م€‚è»ٹمپ«مپ²مپ‹م‚Œمپ¦و»م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ†م‚“مپ م‚چمپ†مپھم€‚
م€€ن»ٹم‚‚مپ—هپ¶ç„¶هٹ©مپ‹مپ£مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پéپ…مپ‹م‚Œو—©مپ‹م‚Œمپ¾مپںن¼¼مپںم‚ˆمپ†مپھç›®مپ«هگˆمپ£مپ¦
م€€و»م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ†مپ®مپ م‚چمپ†مپھم€‚م€چ
مپ¨مپ„مپ†م‚ˆمپ†مپھمپ“مپ¨م‚’م€پمپ¾مپ‚مپ–مپ£مپ¨ï¼‘秒مپڈم‚‰مپ„مپ®é–“مپ«è€ƒمپˆمپ¦مپ„مپںمپ¨و€مپ†م€‚
مپµمپ¨و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨م€پمپ•مپ£مپچمپ¾مپ§مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«éڑ£م‚’و©مپ„مپ¦مپ„مپںهڈ‹ن؛؛مپŒمپ„مپھمپ„م€‚
مپ©مپ“مپ م‚چمپ†مپ¨ه‘¨ه›²م‚’見ه›مپ™مپ¨م€په½¼ه¥³مپ¯مپ„مپ¤مپ®é–“مپ«مپ‹مپمپ®çŒ«مپ®و‰€مپ«èµ°م‚ٹم‚ˆمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ه¾Œم‚چمپ‹م‚‰وٹ±مپچن¸ٹمپ’مپ¦م€پè»ٹمپ®éپ‹è»¢و‰‹مپ«è»½مپڈن¸€ç¤¼مپ—م€پم‚ڈمپچمپ®ه°ڈéپ“مپ«çŒ«م‚’é™چم‚چمپ™مپ¨
é م‚’مپھمپ§مپ¦م‚„مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
مپ—مپ°م‚‰مپڈç§پمپ¯مپ¼مƒ¼مپ£مپ¨مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚
ن½•مپŒمپٹمپچمپںمپ®مپ‹م‚’è‡ھهˆ†مپ®ن¸مپ§و•´çگ†مپ—م€پçگ†è§£مپ™م‚‹مپ®مپ«و™‚é–“مپŒمپ‹مپ‹مپ£مپںمپ®مپ م€‚
ه½¼ه¥³مپ¯مپم‚“مپھç§پمپ«و°—مپŒمپ¤مپچ
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںمپ®ï¼ںم€چ
مپ¨مپ„مپ†م‚ˆمپ†مپ«é¦–م‚’مپ‹مپ—مپ’مپ¦مپ“مپ،م‚‰م‚’見مپںم€‚
مپمپ†مپ„مپ†مپ¨مپچمپ®ه½¼ه¥³مپ¯م€پمپ„مپ¤م‚‚ه”‡مپŒم‚ڈمپڑمپ‹مپ«é–‹مپ„مپ¦مپ„مپ¦م€پ
مپمپ®ن¸،端مپŒه°‘مپ—ن¸ٹمپŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ«è¦‹مپˆم‚‹مپ®مپ مپ£مپںم€‚
مپمپ®ç¬‘é،”م‚’見مپ¦م€پç§پمپ¯وˆ‘مپ«è؟”م‚ٹم€په½¼ه¥³مپ®م‚‚مپ¨مپ«é§†مپ‘مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
è‡ھهˆ†مپ¯ه½¼ه¥³مپ¨هڈ‹مپ مپ،مپ§م‚ˆمپ‹مپ£مپںمپ¨و€مپ£مپںم€‚
è‡ھهˆ†مپ«مپ¯مپھمپ„مپ™مپ”مپ„م‚‚مپ®م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨و€مپ£مپںم€‚
مپ¨مپ¦م‚‚مپ‹مپھم‚ڈمپھمپ„مپ¨م‚‚و€مپ£مپںم€‚
مپمپ—مپ¦م€پ
ن¸€ç”ںه½¼ه¥³مپ¨مپ¯هڈ‹مپ مپ،مپ§مپ„م‚ˆمپ†مپ¨و€مپ£مپںم€‚
م‚ڈمپچمپ®ه°ڈéپ“م€پن½•ن؛‹م‚‚مپھمپ‹مپ£مپںمپ‹مپ®م‚ˆمپ†مپ«م€پمپ²م‚‡مپ“مپ²م‚‡مپ“مپ¨و©مپ„مپ¦مپ„مپڈهگ猫م€‚
ه½¼ه¥³مپ¯مپ«مپ“مپ«مپ“مپ¨و‰‹م‚’وŒ¯مپ£مپ¦è¦‹é€پمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ç§پمپ¯ه£°م‚’مپ‹مپ‘مپںم€‚
م€ŒçŒ«مƒ»مƒ»مƒ»م€پهٹ©مپ‹مپ£مپ¦م‚ˆمپ‹مپ£مپںمپم€‚م€چ
م€Œمپ†م‚“ï¼پم€چ
وڑ–مپ‹مپھو—¥ه°„مپ—مپ®ن¸م€پمپ„مپ¤م‚‚مپ®ه–«èŒ¶ه؛—مپ¯م‚‚مپ†مپ™مپگمپمپ“مپ مپ£مپںم€‚
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپم‚Œم€پç§پï¼ںم€چ
مپ½مپ‹م‚“مپ¨ه°ڈمپ•مپھهڈ£م‚’é–‹مپ‘مپ¦م€پshioriمپ¯ç§پمپ®è©±مپ«èپمپچه…¥مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
م€Œمƒ‘م‚¤م‚ھمƒ‹م‚¢مپ«ن¹—م‚‹ه‰چم€پمپ¾مپ هœ°çگƒمپ«مپ„مپںمپ“م‚چمپ®مپ“مپ¨مپ مپ‹م‚‰مپھم€‚م€چ
م€Œمپم‚“مپھمپ“مپ¨م€پمپ‚مپ£مپںمپ£مپ‘ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مپ£مپںم‚“مپ م‚ˆم€‚م€چ
م€Œèھ°مپ‹ن»–مپ®ن؛؛مپ®è©±مپ؟مپںمپ„مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ¨مپ«مپ‹مپڈم€پshioriمپ¯ç§پمپ®مپ“مپ¨ه†·é™مپ مپ£مپ¦è¨€مپ£مپ¦مپںمپ‘مپ©م€پ
م€€مپمپ†مپکم‚ƒمپھمپ„م‚“مپ م€پç§پمپ¯م€‚م€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œç§پمپ¯ه¤ڑهˆ†م€پن»–مپ®ن؛؛م‚ˆم‚ٹم‚‚ه°‘مپ—ه†·مپںمپ„م‚“مپ مپ¨و€مپ†م€‚
م€€مپمپ—مپ¦م€پمپم‚“مپھè‡ھهˆ†مپŒه°‘مپ—ه«Œمپ„مپھم‚“مپ م€‚
م€€مپمپ†مپ„مپ†ç§پمپ®ه؟ƒم‚’ç™’مپ—مپ¦مپڈم‚Œم‚‹مپ®مپŒم€پshioriم€پمپ‚مپھمپںمپھم‚“مپ م€‚م€چ
مپھم‚“مپ مپ‹مپ™مپ”مپڈوپ¥مپڑمپ‹مپ—مپ„مپ“مپ¨م‚’言مپ£مپ¦م‚‹م‚ˆمپ†مپھو°—مپŒمپ™م‚‹م€‚
مپ§م‚‚مپ“م‚Œمپ¯ن»ٹ言مپ£مپ¦مپٹمپڈمپ¹مپچمپ“مپ¨مپھم‚“مپ م‚چمپ†م€‚
مƒ»مƒ»مƒ»shioriمپ¯مپ—مپ°م‚‰مپڈé»™مپ£مپ¦è€ƒمپˆمپ¦مپ„مپںمپŒم€پم‚„مپŒمپ¦هڈ£م‚’é–‹مپ„مپںم€‚
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»Mikiمپ¯مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»MikiمپŒو€مپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚ˆم‚ٹم€پمپ»م‚“مپ¨مپ¯مپڑمپ£مپ¨ه„ھمپ—مپ„م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپˆم€‚م€چ
م€Œمپ†مپ†م‚“م€پمپھم‚“مپ§م‚‚مپھمپ„م€‚مپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚ه°‘مپ—ç”ںمپچم‚‹ه‹‡و°—مپŒم‚ڈمپ„مپ¦مپچمپںم‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپٹمپ„مپٹمپ„م€پç”ںمپچم‚‹ه‹‡و°—مپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»مپھم‚“مپ‹م‚ھمƒ¼مƒگمƒ¼مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹ï¼ںم€چ
م€Œم‚ھمƒ¼مƒگمƒ¼مپکم‚ƒمپھمپ„م‚ˆمپ£ï¼پم€چ
مپ«مپ£مپ“م‚ٹه¾®ç¬‘م‚€shioriمپ®é،”مپ¯م€پمپ¤مپ„مپ¤م‚‰م‚Œمپ¦مپ“مپ£مپ،مپ¾مپ§é،”مپŒه´©م‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ†م€‚
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپٹمپھمپ‹ç©؛مپ„مپںم€‚م€چ
و°—وŒپمپ،مپŒه’Œم‚„مپ‹مپ«مپھم‚‹مپ¨م€پن؛؛é–“هپ¥ه؛·çڑ„مپ«مپھم‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
م€Œه…ƒو°—مپ«مپھمپ£مپںم‚‰ن½•مپŒé£ںمپ¹مپںمپ„ï¼ںم€چshioriمپŒèپمپڈم€‚
م€Œه¤¢مپ§م‚«مƒ„ن¸¼مپŒمپµم‚ڈمپµم‚ڈمپ¨é£›م‚“مپ§مپ„مپڈم‚“مپ م‚ˆم€‚مپم‚Œمپ‹م‚‰مƒ©مƒ¼مƒ،مƒ³م‚‚م€‚
م€€مپ‚مپ¨مپھمپœمپ‹م‚¨مƒ³â—‹مƒ«مƒ‘م‚¤م‚‚飛م‚“مپ§مپ£مپںمپھمپ‚م€‚م€چ
م€Œمپھم‚“مپ مپ‹ه؛¶و°‘çڑ„مپھé£ںمپ¹ç‰©مپ°مپ‹م‚ٹمپم€‚م€چ
م€Œمپ¾مپ£مپںمپڈمپ م€‚م€چ
ç—…ه®¤مپ®ç™½مپ„ه£پمپ«م€پç§پمپںمپ،ن؛Œن؛؛مپ®ç¬‘مپ„ه£°مپŒو¸©مپ‹مپڈéں؟مپڈم€‚
çھ“مپ®ه¤–م€پمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ¯ه¤‰م‚ڈم‚‰مپڑé’مپ„ه¤§هœ°م‚’مپ®مپ³م‚„مپ‹مپ«ه؛ƒمپ’مپ¦مپ„مپںم€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€ç¬¬ن¸€è©±م€€çµ‚م‚ڈم‚ٹ
|
第ن؛Œè©±م€€م€€مپ“م‚Œمپ¯ç§پمپ®ه¤§هˆ‡مپھè¨کو†¶
ه¤¢م‚’見مپ¦مپ„مپںم€‚
ه¤¢مپ®ن¸مپ®ç§پمپ¯ه°ڈمپ•مپھه¥³مپ®هگمپ مپ£مپںم€‚
çœںمپ£وڑ—مپھç©؛é–“م‚’ç§پمپ¯ن¸€ن؛؛ç«‹مپ،مپ¤مپڈمپ—مپ¦مپ„مپںم€‚
ه؟ƒç´°مپ•مپ«ه£°م‚’مپ‚مپ’مپ¦و³£مپ„مپ¦م‚‚م€په‘¨م‚ٹمپ«èھ°ن¸€ن؛؛مپ„مپھمپ„م€‚
و³£مپچç–²م‚Œمپ¦مپ®مپ©مپŒن¹¾مپڈم€‚
مپ™م‚‹مپ¨م€پمپھمپœمپ‹ç›®مپ®ه‰چم‚’م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپŒç´°مپڈوµپم‚Œèگ½مپ،مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ç§پمپ¯مپم‚ŒمپŒé£²مپ؟مپںمپڈمپ¦مپچم‚‡م‚چمپچم‚‡م‚چمپ¨م‚³مƒƒمƒ—م‚’وژ¢مپ™م€‚
مپ مپŒم€پمپم‚“مپھم‚‚مپ®مپ¯مپ©مپ“مپ«م‚‚見مپ‚مپںم‚‰مپھمپ„م€‚
م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸è‰²مپ®م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ¯مپچم‚‰مپچم‚‰مپ¨م€پ
مپ„مپ¤مپ¾مپ§م‚‚é»’مپ„é—‡مپ®ن¸مپ«هگ¸مپ„è¾¼مپ¾م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«وµپم‚Œèگ½مپ،مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ç§پمپ¯ç‚؛مپ™è،“م‚‚مپھمپڈم€پمپںمپ مپم‚Œم‚’見مپ¦مپ„مپںم€‚
ن½•و•…مپ‹م€په“€مپ—مپ„مپ®مپ«و¸©مپ‹مپ„م‚‚مپ®مپŒمپ“مپ؟ن¸ٹمپ’مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œه¤¢مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ن¸ٹهچٹè؛«م‚’èµ·مپ“مپمپ†مپ¨مپ—مپ¦م€پمپٹè…¹مپ®ه‚·م‚’و€مپ„ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œمپ¤مپ£ï¼پم€چ
è…¹ç‹م‚’ه‹•مپ‹مپ™مپ¨ه‚·هڈ£مپ«ç—›مپ؟مپŒèµ°م‚‹م€‚
مپ®مپ©مپŒمپ‹م‚‰مپ‹م‚‰مپ مپ£مپںم€‚
éه¸¸çپ¯مپ®م‚°مƒھمƒ¼مƒ³مپ®مƒ©م‚¤مƒˆمپ مپ‘مپŒمپ‹مپ™مپ‹مپ«ç—…ه®¤م‚’ç…§م‚‰مپ™ن¸م€پ
و•ه…ƒمپ«ç½®مپ„مپںمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«و™‚計مپ«ç›®م‚’م‚„م‚‹م€‚
مƒ–مƒ«مƒ¼مپ®و–‡ه—مپ¯ï¼گï¼”ï¼ڑ16م‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚
و™‚計مپ®و¨ھمپ«ç½®مپ„مپ¦مپ‚م‚‹و°´ه·®مپ—مپ«و‰‹م‚’ن¼¸مپ°مپ—م€پ
éڑ£مپ®مƒ™مƒƒمƒ‰مپ§مپ™م‚„مپ™م‚„مپ¨ه¯مپ¦مپ„م‚‹shioriمپ«و°—مپŒمپ¤مپ„مپںم€‚
مپ‚م‚Œمپ‹م‚‰ه½¼ه¥³مپ¯م€پمپڑمپ£مپ¨م‚ڈمپںمپ—مپ®çœ‹ç—…مپ®مپںم‚پمپ«ن»کمپچو·»مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
و‰‹è،“مپ‹م‚‰ï¼‘週間مپŒçµŒمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚هŒ»è€…م‚‚é©ڑمپڈه›ه¾©مپ®و—©مپ•مپ مپ£مپںم€‚
م€Œم‚„مپ¯م‚ٹمƒڈمƒ‹مƒ¥م‚¨مƒ¼مƒ«م€پمƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³م‚ˆم‚ٹم‚‚و²»م‚ٹمپŒو—©مپ„مپ§مپ™مپم€‚م€چ
مپچمپ®مپ†مپ‹م‚‰é£ںن؛‹مپ®è¨±هڈ¯مپŒمپٹم‚ٹمپںم€‚
é£ںن؛‹مپ¨مپ„مپ£مپ¦م‚‚م€پمپٹç²¥مپ®ن¸ٹو¾„مپ؟مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپ مپ£مپںم€‚
白مپ„هچٹé€ڈوکژمپ®مپٹو¹¯مپ®ه؛•مپ«م€پمپ»م‚“مپ®ن¸€ç²’مپ®مپ”飯粒مپŒو²ˆم‚“مپ§مپ„م‚‹مپ®مپŒè¦‹مپˆمپںم€‚
病院مپ®é£ںن؛‹مپ¯مپ¾مپڑمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ®مپŒه®ڑèھ¬مپ مپ£مپںم‚ˆمپ†مپ«و€مپ†م€‚
مپ مپŒم€پمپ²مپ•مپ—مپ¶م‚ٹمپ«é£ںمپ¹مپںمپمپ®ن¸€ç²’مپ®م€پمپھم‚“مپ¨ç”کç¾ژمپھمپ“مپ¨مپ‹م€‚
م€Œمپ”飯مپ£مپ¦مپ“م‚“مپھمپ«مپٹمپ„مپ—مپ‹مپ£مپںم‚“مپ م€‚م€چ
مپںمپ£مپںن¸€ç²’مپ®مپ”飯م‚’م€پç§پمپ¯م€پهڈ£مپ®ن¸مپ§و؛¶مپ‘مپ¦مپھمپڈمپھم‚‹مپ¾مپ§ه™›مپ؟مپ—م‚پمپںم€‚
ç”ںمپچمپ¦مپ„مپ¦م‚ˆمپ‹مپ£مپںمپ¨م€پمپ¤مپڈمپ¥مپڈو€مپ£مپںم€‚
ه®¹و…‹مپŒè‰¯مپڈمپھمپ£مپ¦مپ‹م‚‰مپ¯م€پ見èˆه®¢م‚‚ه¢—مپˆمپںم€‚
مپ„مپ¤م‚‚مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«ن»•ن؛‹م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مƒپمƒ¼مƒ مپ®مپ؟م‚“مپھم‚‚و¥مپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
م€Œن»ٹمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ¯مپ„م‚چمپ„م‚چمپ¨ه¤§ه¤‰مپھمپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¦م€پ
م€€و¬،مپ‹م‚‰و¬،مپ¸مپ¨ن»•ن؛‹مپ®ن¾é ¼مپŒèˆمپ„è¾¼م‚“مپ§مپڈم‚‹م€‚
م€€ن¸€ن؛؛مپ§م‚‚ه¤ڑمپڈم€پè…•مپ®مپ„مپ„مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼مپŒو¬²مپ—مپ„مپ¨مپ“م‚چمپھم‚“مپ م€‚
م€€و—©مپڈم‚ˆمپڈمپھمپ£مپ¦وˆ»مپ£مپ¦مپ“مپ„م‚ˆم€‚م€چ
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ¯مپمپ†è¨€مپ£مپ¦ç§پمپ®è‚©م‚’ه°ڈمپ•مپڈهڈ©مپڈمپ¨م€پç—…ه®¤م‚’ه‡؛مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م‚‰مپ—مپ„و€مپ„م‚„م‚ٹمپ مپ£مپںم€‚
ن»–مپ®مپ؟م‚“مپھمپ¯م€پç—…ه®¤مپ®é›°ه›²و°—م‚’ه°‘مپ—مپ§م‚‚وکژم‚‹مپڈمپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ§م‚‚مپ„مپ†مپ®مپ‹م€پ
م‚„مپںم‚‰مپ¨ه†—談م‚’連ç™؛مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚
مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپ®ن¸€ن؛؛مپŒه†’é™؛ن¸çœ مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ„م€پمپم‚Œم‚’مƒپمƒ¼مƒ مپ®çڑ†مپŒهڈ–م‚ٹه›²مپ؟م€پ
مپ„مپںمپڑم‚‰مپ—مپں話م‚’é¢ç™½مپٹمپ‹مپ—مپڈمپ—م‚ƒمپ¹م‚ٹه‡؛مپ™مپ¨م€پم‚‚مپ†ç¬‘مپ„مپŒو¢مپ¾م‚‰مپھمپ„م€‚
مپٹè…¹مپ®ه‚·مپŒé–‹مپچمپمپ†مپ«مپھم‚ٹم€پ笑مپ„مپھمپŒم‚‰é،”م‚’مپ—مپ‹م‚پم‚‹ç§پم‚’見مپ¦shioriمپŒè¨€مپ£مپںم€‚م€€
م€Œمپ•مپ•م€پMikiمپ¯ç–²م‚Œمپ،م‚ƒمپ£مپںمپ؟مپںمپ„مپ مپ‹م‚‰ن»ٹو—¥مپ¯مپ“مپ“مپ¾مپ§م€‚
م€€مپ؟م‚“مپھه؟™مپ—مپ„م‚“مپ م‚ˆمپï¼ںمپ¾مپںوڑ‡مپŒمپ§مپچمپںو™‚مپ§مپ„مپ„مپ‹م‚‰è¦‹èˆمپ„مپ«و¥مپ¦مپم€‚م€چ
مپمپ†م‚„مپ£مپ¦çڑ†م‚’ه»ٹن¸‹مپ¾مپ§é€پم‚ٹه‡؛مپ™مپ¨م€پç—…ه®¤مپ¯ه†چمپ³ç™½مپ„é™è¬گمپھن¸–ç•Œمپ«هŒ…مپ¾م‚Œمپںم€‚
ه¤©ن؛•مپ®و‰€م€…مپ«مپ‚م‚‹م€پè–„مپ¼م‚“م‚„م‚ٹمپ¨مپ—مپںمپ—مپ؟م‚’見مپ¦م€پمپمپ„مپ†مپˆمپ°è‡ھهˆ†م‚‚م€پ
ه†’é™؛مپ®وœ€ن¸مپ«و„ڈèکمپŒé£›م‚“مپکم‚ƒمپ£مپںمپ“مپ¨مپŒمپ‚مپ£مپںمپھمپ‚مپ¨و€مپ„ه‡؛مپ™م€‚
مپ„م‚چمپ„م‚چوƒ³هƒڈمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨م€پ
shioriمپŒوˆ»مپ£مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œمپمپˆم€پمپ‚مپ„مپ¤م‚‰مپٹ見èˆمپ„مپ«و،ƒم‚’وŒپمپ£مپ¦مپچمپ¦مپڈم‚Œمپںم‚“مپ م‚ˆم€‚ç§پم€پو،ƒه¤§ه¥½ç‰©ï¼پم€چ
言مپ„مپھمپŒم‚‰م€پمƒٹم‚¤مƒ•مپ¨çڑ؟م‚’هڈ–م‚ٹمپ مپ—م€پ
ه™¨ç”¨مپ«و،ƒمپ®çڑ®م‚’è–„مپڈم‚¯مƒ«م‚¯مƒ«مپ¨م‚€مپ„مپ¦مپ„مپڈم€‚
م€Œم‚‚مپ†وœç‰©مپ¯é£ںمپ¹مپ¦م‚‚良مپ„مپ£مپ¦مƒ‰م‚¯م‚؟مƒ¼è¨€مپ£مپ¦مپںم‚ˆمپم€‚مپ¯مپ„م€‚م€چ
ن¸€هڈ£م‚µم‚¤م‚؛مپ«هˆ‡مپ£مپںو،ƒمپ«ه°ڈمپ•مپھمƒ•م‚©مƒ¼م‚¯م‚’هˆ؛مپ—م€پç§پمپ®و‰‹مپ«وŒپمپںمپ›مپ¦مپڈم‚Œم‚‹م€‚
هڈ£مپ«مپ™م‚‹مپ¨م€پمپ±مپ£مپ¨و،ƒمپ®èٹ³é†‡مپھ香م‚ٹمپŒه؛ƒمپŒم‚ٹم€پ
ه¥¥و¯مپ®éڑ…مپ«مپ¾مپ§وœو±پمپ®و؟ƒه¯†مپھç”کمپ•مپŒè،Œمپچو¸،م‚‹م€‚
م€Œمپ¯مپ‚ï½م€‚م€چ
言مپ£مپ¦مپٹمپڈمپŒم€پç§پمپ®مپںم‚پوپ¯مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚
shiriمپŒو¨ھمپ§م€پو،ƒمپ®مپ‚مپ¾م‚ٹمپ®مپٹمپ„مپ—مپ•مپ«وˆ‘م‚’ه؟کم‚Œمپ‹مپ‘مپ¦مپ„م‚‹مپ مپ‘مپ م€‚
ه½¼ه¥³مپ®هڈ³و‰‹مپŒمƒ•م‚©مƒ¼م‚¯م‚’مƒ†مƒ¼مƒ–مƒ«مپ®ن¸ٹمپ®çڑ؟مپ«وˆ»مپمپ†مپ¨مپ™م‚‹مپمپ®ç¬é–“م‚’
ç§پمپ¯ن½•و°—مپھمپڈ見مپ¦مپ„مپںم€‚مپ¯مپ£مپ¨وپ¯م‚’飲م‚“مپ§è¨€مپ†م€‚
م€Œهچ±مپھمپ„ï¼پم€چ
م€Œمپˆï¼ںم€چ
وˆ‘مپ«è؟”مپ£مپںshioriمپŒو‰‹ه…ƒمپ«ç›®م‚’م‚„م‚‹م€‚
هڈ³مپ®è‚کمپŒمپ‚م‚„مپ†مپڈمƒ†مƒ¼مƒ–مƒ«مپ®م‚³مƒƒمƒ—م‚’ه€’مپ™مپ¨مپ“م‚چمپ مپ£مپںم€‚
م€Œمپ‚ï½م€پمپ»م‚“مپ¨مپ«هچ±مپھمپ„مپ¨مپ“م‚چمپ مپ£مپںï½مƒ»مƒ»مƒ»
م€€مپ§م‚‚مپ•مپ™مپŒMikiمپم€‚مƒ™مƒƒمƒ‰مپ«و¨ھمپ«مپھمپ£مپ¦مپ¦م‚‚م€پم‚„مپ£مپ±م‚ٹه†·é™مپ م‚ڈم€‚م€چ
م€Œمپ„م‚„مƒ»مƒ»مƒ»م€پمپ“م‚Œمپ¯م‚³مƒƒمƒ—م‚’مپم‚“مپھèگ½مپ،مپمپ†مپھو‰€مپ«ç½®مپ„مپ¦مپٹمپ„مپںç§پمپ®مƒںم‚¹مپ م€‚م€چ
م€Œمپˆم€پمپمپ†مپھمپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€پم€€م€ژèگ½مپ،م‚‹و‰€مپ«ç½®مپ„مپ¦مپٹمپڈمپ‹م‚‰èگ½مپ،م‚‹م€‚م€ڈم€€ç§پم‚ھمƒھم‚¸مƒٹمƒ«مپ®و•™è¨“مپ م€‚م€چ
ن؛Œن؛؛مپ—مپ°م‚‰مپڈçœںé¢ç›®مپھé،”مپ§مپٹن؛’مپ„م‚’見مپ¤م‚پمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ
م‚„مپŒمپ¦هگŒو™‚مپ«مƒ—مƒƒمپ¨هگ¹مپچمپ مپ—مپںم€‚
م€Œمپھمپ«مپم‚Œï¼ںMikiم‚ھمƒھم‚¸مƒٹمƒ«مپ®و•™è¨“مپھمپ®ï¼ںمپ‚مپ¯مپ¯م€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ¯مپ¯م€پمپمپ†مپھم‚“مپ م€په¤‰مپ م‚چï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€پمپٹمپ‹مپ—مپ„م€‚م€چ
و¶™م‚’و‹مپچمپھمپŒم‚‰م€پمپ—مپ‹مپ—shioriمپ¯م‚„مپŒمپ¦çœںé¢ç›®مپھé،”مپ«مپھمپ£مپ¦è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œمپ§م‚‚م€پç¢؛مپ‹مپ«مپمپ†مپ م‚ˆمپم€‚ن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œم‚‹هچ±é™؛مپ¯مپ‚م‚‰مپ‹مپکم‚په¾¹ه؛•مپ—مپ¦وژ’除مپ™م‚‹م€‚
م€€مƒ—مƒمپ®مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼مپ¨مپ—مپ¦مپ¯ه½“然مپ®ه؟ƒو§‹مپˆم‚ˆمپم€‚م€چ
م€Œمپ¾مپ‚م€پمپںمپ—مپ‹مپ«مپمپ†مپھم‚“مپ مپ‘مپ©مپ•م€‚م€چ
م€Œم‚„مپ£مپ±م‚ٹMikiمپ¯éپ•مپ†مپھمپ‚م€‚ç§پمپ¨مپ¯ه¤§éپ•مپ„مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپھمپ«مپ‹èھ¤è§£مپ—مپ¦م‚‹م‚ˆمپ†مپ مپ‹م‚‰è¨€مپ£مپ¦مپٹمپڈمپ‘مپ©م€پ
م€€ç§پمپŒم‚‚مپ¨مپ‹م‚‰ه†·é™مپھن؛؛é–“مپ مپ£مپںمپ¨و€مپ£مپ¦م‚‹م‚“مپھم‚‰ه¤§é–“éپ•مپ„مپ مپم€‚م€چ
م€Œمپˆï¼ںمپمپ†مپھمپ®ï¼ں
م€€Mikiم‚‚وک”مپ¯ç§پمپ¨هگŒمپکم‚ˆمپ†مپھمپٹمپ£مپ،م‚‡مپ“مپ،م‚‡مپ„مپ®ه¥³مپ®هگمپ مپ£مپںمپ®ï¼ںم€چ
م€Œه®ںمپ¯مپمپ†مپھم‚“مپ م€‚م€چ
笑مپ„مپھمپŒم‚‰è¨€مپ†م€‚
shioriمپ¯ن؟،مپکم‚‰م‚Œمپھمپ„م‚ˆمپ†مپھè،¨وƒ…مپ¨هگŒو™‚مپ«م€پ
興ه‘³و´¥م€…مپ¨مپ„مپ†é،”مپ¤مپچم‚’مپ—مپھمپŒم‚‰èپمپ„مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œمپںمپ¨مپˆمپ°مپ©م‚“مپھ風مپھه¤±و•—مپ—مپںمپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپمپ†مپ مپھمپ‚مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپمپ“مپ¾مپ§è¨€مپ£مپ¦م€پç§پمپ¯è€ƒمپˆè¾¼م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ£مپںم€‚
وک”مپ®مپ“مپ¨م‚’و€مپ„ه‡؛مپ›مپھمپ„مپ®مپ م€‚
م€Œمپھمپ‚م€پshioriمƒ»مƒ»مƒ»shioriمپ¯وک”مپ®مپ“مپ¨م€پمپ©م‚Œمپڈم‚‰مپ„مپ¾مپ§è¦ڑمپˆمپ¦م‚‹ï¼ںم€چ
م€Œمپˆï¼ںوک”مپ®مپ“مپ¨ï¼ںم€چ
مپمپ†م€پوˆ‘م€…مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ¯ï¼Œé€ م‚‰م‚Œمپںç”ںه‘½ن½“مپ م€‚
ه½“然è¦ھمپŒمپ„م‚‹م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚
مƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ¨مپ¯éپ•مپ„م€پوˆگé•·é€ںه؛¦مپŒé€ںمپ‹مپ£مپںم‚ٹم€په†چç”ں能هٹ›مپŒé«کمپ‹مپ£مپںم‚ٹم€پ
مپ‚م‚‹مپ„مپ¯مƒ†م‚¯مƒ‹مƒƒم‚¯مپھمپ©ç‰¹و®ٹمپھ能هٹ›مپ«é•·مپ‘مپ¦مپ„مپںم‚ٹمپ™م‚‹م€‚
مپمپ†مپ„مپ£مپں特è³ھمپ¯م€پمپ™مپ¹مپ¦éپ؛ن¼هگمپ®çµ„مپ؟هگˆم‚ڈمپ›مپ§م€پ
مپ‚م‚‹ç¨‹ه؛¦م‚³مƒ³مƒˆمƒمƒ¼مƒ«مپ—مپ¦ç”ںمپ؟ه‡؛مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
ç”ںمپ¾م‚Œم‚‹مپ¨مپ™مپگم€پوˆ‘م€…مپ¯و”؟ه؛œç›´è½„مپ®و•™è‚²و©ںé–¢مپ«é گمپ‘م‚‰م‚Œم€پ
مپمپ“مپ§ه€‹م€…مپ®وŒپمپ¤èƒ½هٹ›م‚’وœ€ه¤§é™گمپ«ه¼•مپچه‡؛مپ™و•™è‚²م‚’هڈ—مپ‘م‚‹م€‚
ç²¾ç¥هٹ›مپ®é«کمپ„هگمپ¯مƒ†م‚¯مƒ‹مƒƒم‚¯مپ®و‰±مپ„و–¹م‚’ن¸ه؟ƒمپ«م€پ
ن؟ٹو•ڈمپھهگمپ¯و ¼é—کوٹ€م‚’مƒ»مƒ»مƒ»مپ¨مپ„مپ†مپµمپ†مپ«مپ م€‚
مپمپ†م‚„مپ£مپ¦è؛«مپ«مپ¤مپ‘مپں能هٹ›م‚’ç”ںمپ‹مپ—م€پمƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³م‚’هٹ©مپ‘م€پ
مپ¨م‚‚مپ«مپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®وœھو¥م‚’هˆ‡م‚ٹé–‹مپ„مپ¦مپ„مپڈم€‚
مپم‚ŒمپŒه°ڈمپ•مپ„é ƒمپ‹م‚‰ç§پمپںمپ،مپ«و±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپچمپںمپ“مپ¨م€‚
و ،é•·ه…ˆç”ںمپ¯مپ„مپ¤م‚‚言مپ£مپ¦مپ„مپںمپ£مپ‘م€‚
م€Œç”ںمپ¾م‚Œمپ¦مپچمپںن»¥ن¸ٹمپ¯م€پèھ°مپ‹مپ®ه½¹مپ«ç«‹مپ¤هکهœ¨مپ«مپھم‚ٹمپھمپ•مپ„م€‚م€چمپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
مپمپ†م€پمپ„م‚ڈمپ°م€پن؛؛é،مپ®م‚ˆمپچم‚µمƒمƒ¼مƒˆه½¹مپ¨مپ—مپ¦وˆ‘م€…مپ¯ç”ںمپ؟ه‡؛مپ•م‚Œمپںم€‚
çڈ¾مپ«ç§پمپ¯è؟‘وژ¥و ¼é—کوٹ€م‚„هگ„種ه…µه™¨مپ®و‰±مپ„و–¹م€پمƒ†م‚¯مƒ‹مƒƒم‚¯مپ®و‰±مپ„و–¹م€پ
مƒˆمƒ©مƒƒمƒ—解除مپ®ن»•و–¹مپھمپ©م€پمƒ‘م‚¤م‚ھمƒ‹م‚¢مپ«ن¹—م‚‹ه‰چمپ‹م‚‰م€په°‚é–€مپ®ه¤§ه¦مپ«ه…¥م‚ٹم€پ
é«که؛¦مپھو•™è‚²م‚’مپ؟مپ£مپ،م‚ٹهڈ—مپ‘مپ¦مپچمپںم€‚
مپمپ—مپ¦مپم‚Œم‚‰مپ¯ن»ٹç¢؛مپ‹مپ«ه¤§مپچمپڈه½¹مپ«مپںمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ن؛؛é،移ن½ڈ計画مپ®هچ±و©ںم‚’و•‘مپ†مپ«مپ¯م€پç§پمپںمپ،مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ¨مƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³م€پ
مپمپ—مپ¦م‚¢مƒ³مƒ‰مƒم‚¤مƒ‰مپںمپ،مپ®هچ”هٹ›مپھمپڈمپ—مپ¦مپ¯مپ‚م‚ٹمپˆمپھمپ„م€‚
مپمپ†مپ„مپ†م‚ڈمپ‘مپ مپ‹م‚‰م€پç§پمپںمپ،مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ«م€په®¶و—ڈمپ¨مپ®ه¹¼ه°‘وœںمپ®و€مپ„ه‡؛مپھمپ©مپ¯مپھمپ„م€‚
物ه؟ƒمپ¤مپ„مپںو™‚مپ«مپ¯ه¦و ،مپ®ه¯®مپ§م€پمپ»مپ‹مپ®ن»²é–“مپںمپ،مپ¨مپ¨م‚‚مپ«وڑ®م‚‰مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚
مپ§مپ¯م€پمپ“مپ®مپ‚مپ„مپ 見مپںمپ‚مپ®ه¤¢مپ¯مپھم‚“مپ مپ£مپںمپ®مپ ï¼ں
مƒھم‚¢مƒ«مپھه¤¢مپ مپ£مپںم€‚
ç”کمپڈمپ¦ه°‘مپ—مپ—م‚‡مپ£مپ±مپ„م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ®ه‘³مپŒم€پ
مپ‚م‚ٹمپ‚م‚ٹمپ¨èˆŒه…ˆمپ«م‚ˆمپ؟مپŒمپˆمپ£مپ¦مپڈم‚‹م€‚
م€Œم‚ڈمپںمپ—مپŒو،ƒم‚’ه¥½مپچمپھمپ®مپ¯مپمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
çھپ然shioriمپŒè©±مپ—ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œمپںمپ—مپ‹ن¸ه¦ç”ںمپ®و™‚مپ مپ£مپںمپ®م€‚مƒ†مƒ‹م‚¹مپ®ه¤§ن¼ڑمپŒمپ‚مپ£مپ¦مپم€‚
م€€ï¼“ه¹´ç”ںمپ مپ‹م‚‰è² مپ‘مپںم‚‰مپم‚Œمپ§ه¼•é€€م€‚
م€€هœ°هŒ؛ن؛ˆéپ¸مپ¯é †èھ؟مپ«ه‹مپ،ن¸ٹمپŒمپ£مپ¦م€پهœ°هŒ؛1ن½چمپ®وˆگ績مپ§çœŒه¤§ن¼ڑمپ«ه‡؛مپںمپ®مپم€‚
م€€مپ¾مپ‚م€پن¸–é–“م‚’çں¥م‚‰مپھمپ„مپ‹م‚‰م€پ県م‚‚هˆ¶مپ—مپ¦ه…¨ه›½مپ«è،Œمپڈم‚“مپ مپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»
م€€éڑڈهˆ†é¼»وپ¯èچ’مپ‹مپ£مپںم‚ڈم€‚
م€€مپمپ—مپںم‚‰ن»ٹمپ¾مپ§ن¸€ه؛¦م‚‚ç§پمپ®è©¦هگˆè¦‹مپ«و¥مپںمپ“مپ¨مپŒمپھمپ‹مپ£مپںمپٹ父مپ•م‚“مپŒ
م€€م€ژshioriم€پوکژو—¥مپ®è©¦هگˆمپ¯è¦‹مپ«è،Œمپڈمپ‹م‚‰مپھم€‚م€ڈ
م€€مپ£مپ¦م€پçھپ然言مپ†مپ®م€‚ç§پمپ¨مپ¾مپ©مپ£مپ،م‚ƒمپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»
م€€مپ§م‚‚مپ™مپ”مپڈه¬‰مپ—مپ‹مپ£مپںم€‚
م€€çµ¶ه¯¾مپ«ه‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ“م‚چم‚’مپٹ父مپ•م‚“مپ«è¦‹مپ¦م‚‚م‚‰مپ†م‚“مپ مپ£مپ¦م€په¼µم‚ٹهˆ‡مپ£مپںمپ®مپم€‚م€چ
مƒ•م‚©مƒ‹مƒ¥م‚¨مƒ¼مƒ«مپ®shioriمپ«مپھمپœè¦ھمپŒمپ„م‚‹م‚“مپ ï¼ں
ç§پمپ®ç–‘ه•ڈم‚’م‚ˆمپمپ«shioriمپ¯èھم‚ٹç¶ڑمپ‘مپںم€‚
م€Œمپ§م‚‚م€پçڈ¾ه®ںمپ¯مپمپ†ç”کمپڈمپھمپ‹مپ£مپںم€‚
م€€ç§پم€پمپٹ父مپ•م‚“مپŒه؟œوڈ´مپ«و¥م‚‹ه‰چمپ«م€پوœ€هˆمپ®è©¦هگˆمپ§è² مپ‘مپ،م‚ƒمپ£مپںمپ®مپم€‚
م€€ن¼ڑه ´مپ®و¨ھمپ§ç§پم€پن¸€ن؛؛èگ½مپ،è¾¼م‚“مپ§مپںم‚‰ن½•م‚‚çں¥م‚‰مپھمپ„مپٹ父مپ•م‚“مپŒم‚„مپ£مپ¦مپچمپںم‚ڈم€‚
م€€è² مپ‘مپںمپ£مپ¦èپمپ„مپ¦م€پمپںمپ¶م‚“ç§پن»¥ن¸ٹمپ«مپŒمپ£مپ‹م‚ٹمپ—مپںم‚“مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹مپھï¼ں
م€€مپ§م‚‚مپمپ®و™©مپم€پ部ه±‹مپ§مپµمپ¦مپڈمپ•م‚Œمپ¦مƒمƒ³م‚¬èھم‚“مپ§مپںم‚‰
م€€مپٹ父مپ•م‚“مپŒهڈ°و‰€مپ‹م‚‰ç§پم‚’ه‘¼مپ¶مپ®م€‚è،Œمپ£مپ¦مپ؟مپںم‚‰مپم€‚
م€€م€ژshioriم€پن»ٹو—¥مپ¯و®‹ه؟µمپ مپ£مپںمپھم€‚م€ڈ
م€€مپمپ†è¨€مپ£مپ¦و،ƒم‚’م‚€مپ„مپ¦مپڈم‚Œمپںمپ®م€‚
م€€مپٹمپ„مپ—مپ‹مپ£مپںمپھمپ‚م€پمپ‚مپ®و،ƒم€‚
م€€مپ‚م‚Œمپ‹م‚‰ç§پم€پو،ƒمپŒه¤§ه¥½مپچمپ«مپھمپ£مپ،م‚ƒمپ£مپںمپ®م€‚
م€€ç§پم€پن¸€ن؛؛مپ£هگمپ§م€پمپ—مپ‹م‚‚مپٹ父مپ•م‚“م‚‚مپٹو¯چمپ•م‚“م‚‚
م€€مپ مپ„مپ¶ه¹´هڈ–مپ£مپ¦مپ‹م‚‰ç”ںمپ¾م‚Œمپںم‚‚مپ®مپ مپ‹م‚‰م€پ
م€€مپم‚Œمپ¯مپم‚Œمپ¯éڑڈهˆ†مپ‹م‚ڈمپ„مپŒم‚‰م‚Œمپںم‚“مپ مپ‘مپ©مپم€‚
م€€مپ§م‚‚م€پمپ‚مپ®و،ƒمپ®مپ“مپ¨مپŒن¸€ç•ھه؟ƒمپ«و®‹مپ£مپ¦م‚‹مپھمپ‚م€‚م€چ
مپم‚“مپھمپ“مپ¨مپŒمپ‚مپ£مپںمپ®مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»مپ§م‚‚مپھمپœمپم‚“مپھè¨کو†¶مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ ï¼ں
ه¤§ن½“و™‚ن»£م‚‚ه›½م‚‚ه…¨ç„¶éپ•مپ†مپم€‚
県مپ مپ®ن½•مپ مپ®مپ¨مپ„مپ†مپ®مپ¯م€پمپم‚Œمپ¯éپ¥مپ‹وک”مپ®JAPANمپ¨مپ‹è¨€مپ†ه›½مپ®ن؛‹مپکم‚ƒمپھمپ„مپ®مپ‹ï¼ں
shioriمپ®è¨کو†¶مپ¯ه®ںمپ¯shioriمپ®è¨کو†¶مپکم‚ƒمپھمپڈمپ¦م€پ
éپژهژ»مپ«ç”ںمپچمپ¦مپ„مپںèھ°مپ‹مپ®م‚‚مپ®مپھم‚“مپکم‚ƒمپھمپ„مپ®مپ‹ï¼ں
مپ مپŒم€پن½•مپ®مپںم‚پمپ«ن»–ن؛؛مپ®è¨کو†¶م‚’shioriمپ«ï¼ںï¼ںï¼ں
مپمپ®و™‚مƒ»مƒ»مƒ»
و€مپ„ه‡؛مپ—مپںم€‚ç§پمپ®è¨کو†¶م‚’مƒ»مƒ»مƒ»
م€€وک”مپ¯م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ®è‡ھه‹•è²©ه£²و©ںم‚‚م€پن»ٹمپ®م‚ˆمپ†مپھه½¢مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
و©ںو¢°مپ®مپ¦مپ£مپ؛م‚“مپ«é€ڈوکژمپھهچٹçگƒمپ®مƒ‰مƒ¼مƒ مپŒمپ‚م‚ٹم€پ
éٹ€è‰²مپ®مƒژم‚؛مƒ«مپ‹م‚‰ه™´مپچه‡؛مپ™م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپŒم€پ
مƒ‰مƒ¼مƒ مپ®ه†…هپ´م‚’مپ¤مپںمپ£مپ¦èگ½مپ،مپ¦مپڈم‚‹م€پ
مپم‚ŒمپŒç„،é™گمپ«ç¶ڑمپڈمپ¨مپ„مپ†م€پ見م‚‹مپ‹م‚‰مپ«مپٹمپ„مپ—مپمپ†مپھمپ—مپ‹مپ‘مپŒو–½مپ—مپ¦مپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ—مپںم€‚
飲م‚€و™‚مپ«مپ¯م€پو©ںو¢°مپ®و¨ھمپ®é€ڈوکژمپھç’مپ«ه…¥مپ£مپںç´™م‚³مƒƒمƒ—م‚’ن¸‹ç«¯مپ‹م‚‰و‰‹مپ§وٹœمپچهڈ–م‚ٹم€پ
وŒ‡ه®ڑمپ•م‚Œمپںهڈ°مپ®ن¸ٹمپ«ç½®مپڈم€‚مپ—مپ‹م‚‹ه¾Œمپ«ï¼‘ï¼گه††çژ‰م‚’وٹ•ه…¥مپ™م‚‹مپ¨م€پ
è‡ھه‹•çڑ„مپ«ç´™م‚³مƒƒمƒ—مپ«م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپŒو³¨مپŒم‚Œم‚‹مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ§مپ—مپںم€‚
ه°ڈه¦و ،ï¼’ه¹´ç”ںمپ®ç§پمپ¯م€په¸¸م€…1ه؛¦مپ§مپ„مپ„مپ‹م‚‰م€پ
è‡ھهˆ†مپ§و“چن½œمپ—مپ¦مپ“مپ®م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹م‚’飲م‚“مپ§مپ؟مپںمپ„
مپ¨و€مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
م€€مپم‚“مپھمپ‚م‚‹و™‚م€پو¯چè¦ھمپ«é€£م‚Œم‚‰م‚Œمپ¦م€پ
ç”؛مپ®م‚¹مƒ¼مƒ‘مƒ¼مپ«è²·مپ„物مپ«é€£م‚Œمپ¦è،Œمپ£مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
و¯چمپŒè²·مپ„物م‚’مپ™م‚‹é–“م€پم‚¹مƒ¼مƒ‘مƒ¼مپ®ه‰چمپ®م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ®è‡ھه‹•è²©ه£²و©ںمپ®مپ¨مپ“م‚چمپ§
ه¾…مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مƒپمƒ£مƒ³م‚¹ï¼پ
و¯چمپ«مپمپ مپ£مپ¦ï¼‘ï¼گه††م‚‚م‚‰مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
مپچم‚‡مپ†مپ“مپé،کمپ„مپŒمپ‹مپھمپ†م€‚
و¯چمپŒمپٹه؛—مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„مپڈمپ®م‚’見é€پم‚‹مپ¨م€پç§پمپ¯و€¥مپ„مپ§è‡ھه‹•è²©ه£²و©ںمپ«è؟‘مپ¥مپچمپ¾مپ—مپںم€‚
م‚ڈمپڈم‚ڈمپڈمپ—مپھمپŒم‚‰ï¼‘ï¼گه††çژ‰م‚’وٹ•ه…¥مپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ¨مپ“م‚چمپŒم€پç©´مپ®مپµمپ،مپ«ï¼‘ï¼گه††çژ‰مپ®مپژمپ–مپژمپ–مپŒمپ²مپ£مپ‹مپ‹م‚ٹم€پ
ç§پمپ¯مپٹ金م‚’èگ½مپ¨مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ“م‚چمپŒمپ£مپں1ï¼گه††çژ‰م‚’ç§پمپ¯ه؟…و»مپ§è؟½مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
مپٹ金مپ¯ç„،وƒ…مپ«م‚‚م€پè؟‘مپڈمپ«مپ‚مپ£مپںوژ’و°´و؛مپ®ن¸مپ«èگ½مپ،مپ¦مپ—مپ¾مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
مپمپ“مپ¯ن؛؛مپŒèگ½مپ،مپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«é‡چمپمپ†مپھ金網مپŒمپ‹مپ‘مپ¦مپ‚م‚ٹم€پ
مپ¨مپ¦م‚‚هڈ–م‚Œمپمپ†مپ«مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
م‚ڈمپںمپ—مپ¯é»’مپڈوµپم‚Œم‚‹و°´م‚’مپںمپ هڈ£م‚’é–‹مپ‘مپ¦è¦‹مپ¦مپ„م‚‹مپ مپ‘مپ§مپ—مپںم€‚
م‚„مپŒمپ¦è²·مپ„物م‚’و¸ˆمپ¾مپ›مپںو¯چمپŒه؛—م‚’ه‡؛مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚
وژ’و°´و؛مپ«مپ—م‚ƒمپŒمپ؟مپ“م‚“مپ§مپ„م‚‹ç§پم‚’見مپ¦
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںمپ®ï¼ںم€چ
مپ¨èپمپچمپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمپٹ金م€پèگ½مپ¨مپ—مپںم€‚م€چ
م€Œمپمپ†م€‚م€چ
و¯چمپ¯و·±ه‘¼هگ¸م‚’ن¸€مپ¤مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚è²·مپ„物مپ‹مپ”مپ‹م‚‰م‚µم‚¤مƒ•م‚’هڈ–م‚ٹه‡؛مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œن»ٹه؛¦مپ¯èگ½مپ¨مپ—مپ،م‚ƒمپ م‚پم‚ˆم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦و–°مپ—مپ„1ï¼گه††çژ‰م‚’و¸،مپ—مپ¦مپڈم‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمپٹو¯چمپ•م‚“م€پن¸€مپ¤è²·مپ„物ه؟کم‚Œمپ¦مپںمپ‹م‚‰م‚‚مپ†ن¸€ه؛¦è،Œمپ£مپ¦مپڈم‚‹مپم€‚مپ“مپ“مپ§ه¾…مپ£مپ¦م‚‹مپ®
م‚ˆم€‚م€چ
و¯چمپ¯مپمپ†è¨€مپ£مپ¦ه†چمپ³ه؛—مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—مپںم€‚
ç§پمپ¯ه¬‰مپ—مپڈمپھمپ£مپ¦م€پè‡ھه‹•è²©ه£²و©ںمپ«é§†مپ‘ه¯„م‚ٹم€پ
ن»ٹه؛¦مپ¯ï¼‘ï¼گه††çژ‰م‚’èگ½مپ¨مپ•مپ¬م‚ˆمپ†و³¨و„ڈمپ—مپ¦ه…¥م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
مپ‹مپ،م‚ƒم‚“م€‚
م‚„مپ£مپںم€‚ن»ٹه؛¦مپ¯مپ،م‚ƒم‚“مپ¨ه…¥م‚Œم‚‰م‚Œمپںم€‚
مپ§م‚‚مƒ»مƒ»مƒ»ç§پمپ¯مپ„مپچمپھم‚ٹمپٹ金م‚’ه…¥م‚Œمپںم‚‰مپمپ®ه¾Œمپ©مپ†مپھم‚‹مپ‹م€پ
مپم‚“مپھç°،هچکمپھمپ“مپ¨م‚’ن؛ˆو¸¬مپ™م‚‹م‚†مپ¨م‚ٹمپŒمپھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚
مپمپ†م€پمپ†م‚Œمپ—مپڈمپ¦èˆˆه¥®مپ—مپ¦مپ„مپںمپ®مپ§مپ™مپم€پç§پمپ¯م€‚
م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ¯ه½“然مپ§مپ™مپŒم€پç§پمپ®ç›®مپ®ه‰چم‚’مپ¾مپ£مپ™مپگمپ«èگ½مپ،مپ¦م‚†مپچم€پ
مپمپ—مپ¦هڈ°مپ®ن¸‹مپ«مپ‚م‚‹ه°ڈمپ•مپھç„،و•°مپ®ç©´مپ«هگ¸مپ„è¾¼مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپڈمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€€مپ—مپ°م‚‰مپڈç§پمپ¯è‡ھه‹•è²©ه£²و©ںم‚’مپ¼ï½مپ£مپ¨è¦‹مپ¤م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
è‡ھهˆ†مپŒé™گم‚ٹمپھمپڈمپٹم‚چمپ‹مپھهگمپ©م‚‚مپ مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م€پ
ن¸€ن؛؛مپ§مپ¯ن½•م‚‚مپ§مپچمپھمپ„ن¸–é–“çں¥م‚‰مپڑمپھهگمپ©م‚‚مپ مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚’م€پ
مپ¤مپڈمپ¥مپڈو€مپ„çں¥م‚‰مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
ç§پمپ¯é¦¬é¹؟مپ م€‚ç§پمپ¯é¦¬é¹؟مپ م€‚ç§پمپ¯ه¤§é¦¬é¹؟مپ مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
مپµمپ¨و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨م€په¾Œم‚چمپ«و¯چمپŒç«‹مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œم‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹م€پمپٹمپ„مپ—مپ‹مپ£مپںï¼ںم€چ
ç§پمپ¯و¯چمپ®é،”م‚’見م‚‹مپ“مپ¨م‚‚ه‡؛و¥مپڑم€پمپ†مپ¤م‚€مپ„مپںمپ¾مپ¾م€پمپ¼مپم‚ٹمپ¨ç”مپˆمپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œم‚³مƒƒمƒ—ç½®مپڈمپ®ه؟کم‚Œمپںم€‚م€چ
م€Œمپمپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
و¯چمپ¯مپ—مپ°م‚‰مپڈé»™مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
م‚„مپŒمپ¦مپ«مپ£مپ“م‚ٹه¾®ç¬‘م‚€مپ¨م€په†چمپ³م‚µم‚¤مƒ•م‚’هڈ–م‚ٹه‡؛مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مپمپ—مپ¦ç§پمپ«م‚‚مپ†ï¼‘وڑم€پ1ï¼گه††çژ‰م‚’وڈ،م‚‰مپ›مپ¦مپڈم‚Œمپںمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€Œن»ٹه؛¦مپ¯و°—م‚’مپ¤مپ‘م‚‹مپ®م‚ˆم€‚م€چ
م€€و¶™مپŒèگ½مپ،مپ¾مپ—مپںم€‚و¬،مپ‹م‚‰و¬،مپ¸مپ¨م€‚
مپ“م‚“مپھ馬é¹؟مپھه¨کمپ«م€پمپھمپœو¯چمپ¯مپ“مپ“مپ¾مپ§ه„ھمپ—مپ„مپ®مپ م‚چمپ†م€‚
ç§پمپŒو¯چمپ مپ£مپںم‚‰م€پهگŒمپکه¤±و•—م‚’ç¹°م‚ٹè؟”مپ—م€پ
مپ“م‚“مپھمپ«م‚‚مپٹ金م‚’ç²—وœ«مپ«مپ™م‚‹مپٹم‚چمپ‹مپھه¨کمپھمپ©
مپ»مپ£مپ؛مپںم‚’مپ¯م‚ٹمپ¨مپ°مپ—مپ¦مپ„مپںمپ م‚چمپ†م€‚
مپ§م‚‚و¯چمپ¯éپ•مپ†مپ®مپ§مپ™م€‚
ن½•ه؛¦ه¤±و•—مپ—مپ¦م‚‚مپ«مپ“مپ«مپ“笑مپ£مپ¦ï¼‘ï¼گه††çژ‰م‚’ه·®مپ—ه‡؛مپ™مپ®مپ§مپ™م€‚
م€€و¯چمپŒè¦‹ه®ˆم‚‹ن¸م€پç§پمپ¯و…ژé‡چمپ«ç´™م‚³مƒƒمƒ—م‚’م‚»مƒƒمƒˆمپ—م€پ
èگ½مپ¨مپ•مپھمپ„م‚ˆمپ†و³¨و„ڈمپ—مپ¦ï¼‘ï¼گه††çژ‰م‚’ç©´مپ«وٹ•ه…¥مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م‚„مپ£مپ¨و‰‹مپ«ه…¥م‚Œمپںم‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ®ه‘³مپ¯م€پ
و¶™مپ®ه‘³مپ¨و··مپ–م‚ٹهگˆمپ£مپ¦مپ‹مپˆمپ£مپ¦مپم‚ŒمپŒéڑ مپ—ه‘³مپ¨مپھمپ£مپںمپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¨مپ¦م‚‚ç”کمپ„م‚‚مپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€Œèگ½مپ،م‚‹و‰€مپ«ç½®مپ„مپ¦مپٹمپڈمپ‹م‚‰èگ½مپ،م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†مپ‹م€پمپ“مپ®è¨کو†¶مپ مپ£مپںمپ®مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپ¤مپ¶م‚„مپ„مپںç§پمپ«shioriمپŒ
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںمپ®ï¼ںم€چ
مپ¨ه°‹مپم‚‹م€‚ç§پمپ¯مپ‚م‚‰مپںم‚پمپ¦shioriمپ«è‡ھهˆ†مپ®è¨کو†¶م‚’èھم‚ٹه§‹م‚پمپںم€‚
èھ°مپ‹مپŒن½•مپ®ç‚؛مپ‹مپ¯çں¥م‚‰مپھمپ„مپŒم€پç§پمپںمپ،مپ«ن؛؛é–“مپ®è¨کو†¶م‚’هں‹م‚پè¾¼م‚“مپ§مپ„م‚‹مپ®مپ م€‚
مپ„م‚„م€په†·é™مپ«è€ƒمپˆم‚Œمپ°çگ†è§£مپ¯مپ§مپچم‚‹مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»
وˆ‘م€…ن؛؛é€ ن؛؛é–“مپ§مپ‚م‚‹مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپŒم€پن؛؛é،مپ¨ن»²éپ•مپ„مپ›مپ¬م‚ˆمپ†مپ«مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پ
ç§پمپںمپ،مپ®ه؟ƒمپ®ن¸مپ«ن؛؛é–“مپ®è¨کو†¶م‚’ه…¥م‚Œمپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨مپŒن¸€ç•ھمپ مپ¨مƒ»مƒ»مƒ»
ن؛؛é–“مپ®è¨کو†¶مپŒمپ‚م‚‹ن»¥ن¸ٹم€پمپم‚Œمپ¯ç§پمپںمپ،مپ¨ن؛؛é،مپ¨مپ®çµ†مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ م‚چمپ†م€‚
مپمپ†م€پمپ“مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’考مپˆمپں科ه¦è€…مپ¯مپ¨مپ¦م‚‚é مپŒمپ„مپ„مپھم€‚
مپµمپ¨م€په¾Œمپ‹م‚‰هں‹م‚پè¾¼مپ¾م‚Œمپںمپ“مپ®è¨کو†¶مپŒم€پçµگو§‹و°—مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„م‚‹è‡ھهˆ†مپ«و°—مپŒمپ¤مپ„مپںم€‚
مپںمپ¨مپˆمپم‚ŒمپŒو„ڈه›³çڑ„مپ«هں‹م‚پè¾¼مپ¾م‚Œمپںم‚‚مپ®مپ مپ¨مپ—مپ¦م‚‚مپ م€‚
مپچمپ£مپ¨مپ“مپ†مپ„مپ†è¨کو†¶م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپںن؛؛مپŒه®ںéڑ›مپ«مپ„مپںمپ®مپ م‚چمپ†م€‚
ن؛؛é،مپ¯éڑڈهˆ†è‡ھهˆ†ه‹و‰‹مپھن؛‹م‚‚مپ™م‚‹مپŒم€پ
هڈچé¢مپ“م‚“مپھمپ«م‚‚و„›مپ™مپ¹مپچه؟ƒم‚’وŒپمپ£مپ¦م‚‚مپ„م‚‹م‚“مپ مپ¨مƒ»مƒ»مƒ»
م‚‚مپ—مپ‹مپ—مپںم‚‰م€پç§پمپ®مپ“مپ®ن½“مپ¨هگŒمپکمپڈم€پé€ م‚‰م‚Œمپںè¨کو†¶مپھمپ®مپ‹م‚‚çں¥م‚Œمپھمپ„م€‚
م€€م€€م€€مپ‘مپ©مƒ»مƒ»مƒ»
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»ç§پمپ¯مپ“مپ®è¨کو†¶م‚’ه¤§هˆ‡مپ«مپ—مپںمپ„م€‚
م€€ï¼‘週間ه¾Œم€پç§پمپ¯é€€é™¢مپ—مپںم€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€ç¬¬ن؛Œè©±م€€çµ‚م‚ڈم‚ٹ
|
第ن¸‰è©±م€€م€€مƒ©م‚°م‚ھمƒ«و¸©و³‰مپ®هٹ¹èƒ½
ن¹…مپ—مپ¶م‚ٹمپ«ç«‹مپ¤مƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ®ه¤§هœ°م€پ赤مپ„ه¤•و—¥مپŒçœ©مپ—مپ‹مپ£مپںم€‚
مپ¾مپ ه®Œه…¨مپ«و²»مپ£مپںم‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„مپŒم€پمپ¨م‚ٹمپ‚مپˆمپڑمƒھمƒڈمƒ“مƒھم‚‚ه…¼مپمپ¦م€پ
مƒ©م‚°م‚ھمƒ«هœ°è،¨éƒ¨مپ«é™چم‚ٹç«‹مپ£مپ¦مپ؟مپںمپ®مپ م€‚
م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ«مپ¯shioriم€پمپمپ®ن»–مپ«م‚‚مƒپمƒ¼مƒ مپ®ن¸مپ‹م‚‰Dakiniم€پUkiمپںمپ،経験è±ٹه¯Œمپھ
مƒ™مƒ†مƒ©مƒ³مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼م‚’مپ¤مپ‘مپ¦م‚‚م‚‰مپ£مپںم€‚
ن»ٹو—¥مپ®ن¾é ¼مپ¯è‹¥مپ„ه¥³و€§مپ®مƒ€م‚¤م‚¨مƒƒمƒˆم‚’و‰‹ن¼مپ†مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ مپ£مپںم€‚
ن»•ن؛‹مپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپںم‚‰مپ¤مپ„مپ§مپ«و´çھںه†…مپ«م‚ڈمپچه‡؛م‚‹و¸©و³‰مپ§ه‚·è·،م‚’م‚†مپ£مپڈم‚ٹç™’مپمپ†
مپ¨مپ„مپ†è€ƒمپˆم‚‚مپ‚مپ£مپںم€‚
مپ¤مپ„مپ§مپ«م€پمƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ«هں‹م‚پè¾¼مپ¾م‚Œمپںè¨کو†¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پ
çڑ†مپ®è€ƒمپˆم‚‚èپمپ„مپ¦مپٹمپچمپںمپ‹مپ£مپںم€‚
shioriمپ«مپ¯ن¾‹مپ®و،ƒمپ®è¨کو†¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦ç¢؛مپ‹م‚پمپ¦مپ؟مپںم€‚
مƒ»مƒ»مƒ»و،ƒم‚’م‚€مپ„مپ¦مپڈم‚Œمپںمپٹ父مپ•م‚“مپ¯ن»ٹمپ¯مپ©مپ†مپ—مپ¦م‚‹مپ®ï¼ں
م€€م€€م€€مپˆم€پمپ¨مپ£مپڈمپ«و»م‚“مپکم‚ƒمپ£مپںم‚ڈم‚ˆم€‚
مپمپ†ç”مپˆمپ¦مپ‹م‚‰shioriمپ¯م€پمپ¯مپںمپ¨è€ƒمپˆè¾¼م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ£مپںم€‚
مپ©مپ†م‚„م‚‰è‡ھهˆ†مپ®éپژهژ»مپ®è¨کو†¶مپ«ç–‘مپ„م‚’وٹ±مپچه§‹م‚پمپںم‚‰مپ—مپ„م€‚
ç§پمپ¯è¨کو†¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®è‡ھهˆ†مپھم‚ٹمپ®è€ƒمپˆم‚’shioriمپ«è©±مپ—مپںم€‚
shioriمپ¯هچٹهˆ†ç´چه¾—مپ—مپںم‚ˆمپ†مپھم€پ
مپ§م‚‚هچٹهˆ†مپ¯ç´چه¾—مپ§مپچمپھمپ„م‚ˆمپ†مپھم€پ複雑مپھè،¨وƒ…م‚’مپ—مپںم€‚
shioriمپ«مپ¯shioriمپ®و‚©مپ؟مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ م‚چمپ†م€‚
مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«و¸©و³‰مپ«مپ¤مپ‹مپ£مپ¦è©±م‚’مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پ
ه°‘مپ—مپ§م‚‚ه½¼ه¥³مپ®ه؟ƒمپ®م‚ڈمپ مپ‹مپ¾م‚ٹمپŒهڈ–م‚Œم‚Œمپ°
مپ¨و€مپ£مپںم€‚
ن»•ن؛‹مپ¯و»م‚ٹمپھمپڈ終م‚ڈم‚ٹم€پن¾é ¼è€…مپ¯مپ™مپ£مپچم‚ٹمپ¨ç—©مپ›مپںن½“مپ§م‚¹م‚مƒƒمƒ—è¸ڈمپ؟مپھمپŒم‚‰
مƒ‘م‚¤م‚ھمƒ‹م‚¢مپ«ه¸°مپ£مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
و¸©و³‰مپ«ه…¥م‚‹مپ®م‚‚ن¹…مپ—مپ¶م‚ٹمپ م€‚
露ه¤©é¢¨ه‘‚مپ§و··وµ´مپ مپ‹م‚‰م€پ裸مپ§ه…¥م‚‹م‚ڈمپ‘مپ«مپ¯مپ„مپ‹مپھمپ„م€‚ه½“然و°´ç€ç€ç”¨مپ م€‚
ç§پمپ¯مپ‚مپˆمپ¦ç™½مپ®مƒ“م‚مƒ‹م‚’ç€مپ¦مپ؟مپںم€‚shioriمپŒمپ³مپ£مپڈم‚ٹمپ—مپںç›®مپ§ç§پم‚’見مپ¦مپ„م‚‹م€‚
(ه¤§ن¸ˆه¤«مپ م‚ˆshioriم€په‚·مپ®مپ“مپ¨مپھم‚“مپ‹و°—مپ«مپ—مپ¦مپھمپ„م€‚)
ç§پمپ¯مپ«مپ£مپ“م‚ٹمپ¨ç¬‘é،”مپ§ç”مپˆمپںم€‚
م€Œه…¥é™¢ç”ںو´»مپ®مپ‚مپ„مپ مپ«م€پمپ™مپ£مپ‹م‚ٹ白مپڈمپھمپ£مپ،م‚ƒمپ£مپںمپم€‚م€چ
م€Œمپمپ†مپمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
2週間م‚‚مƒ™مƒƒمƒ‰مپ§مپٹمپ¨مپھمپ—مپڈمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨م€پç´«ه¤–ç·ڑمپ¨مپ¯مپ¾م‚‹مپ§ç¸پمپŒمپھمپ„مپ‹م‚‰م€پ
è‚ŒمپŒم€پé™è„ˆمپ®é€ڈمپ‘مپ¦è¦‹مپˆم‚‹مپ»مپ©مپ«ç™½مپڈمپھم‚‹م€‚مپ„مپ‹مپ«م‚‚ç—…ن؛؛مپ¨مپ„مپ†é›°ه›²و°—مپ م€‚
UkiمپŒه”گèچ‰و¨،و§کمپ®م‚¯مƒ©م‚·مƒƒم‚¯مپھوµ·مƒ‘مƒ³م‚’مپ¯مپ„مپ¦مپکم‚ƒمپ¶مپکم‚ƒمپ¶ه…¥م‚‹م€‚
م€Œمپٹï¼پمپٹè…¹مپ®ه‚·م€پمپچم‚Œمپ„مپ«مپ¤مپھمپŒمپ£مپ¦م‚‹مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹م€‚
م€€è؟‘مپڈمپ§è¦‹مپھمپ„مپ¨و°—مپŒمپ¤مپ‹مپھمپ„مپœم€‚م€چ
مپ“مپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚’م€پمپ•م‚ٹمپ’مپھمپڈ言مپ†مپ¨مپ“م‚چمپŒه½¼مپ®و‰چ能مپ مپ¨و€مپ†م€‚
مپںمپ—مپ‹مپ«م€پمپ؟مپمپٹمپ،مپ‹م‚‰مپٹè‡چمپ«مپ‹مپ‘مپ¦م€پمپ†مپ£مپ™م‚‰مپ¨مƒ”مƒ³م‚¯è‰²مپ®ç¸«هگˆè·،مپŒè¦‹مپˆم‚‹م€‚
مپٹو¹¯مپ«و¸©م‚پم‚‰م‚Œمپ¦م€پمپمپ®مƒ”مƒ³م‚¯è‰²مپŒو¬،第مپ«و؟ƒمپڈوµ®مپ‹مپ³ن¸ٹمپŒمپ£مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œمپ م‚Œمپ‹مپ•م‚“مپŒمپڈمپ م‚‰مپھمپ„ه†—談مپ§ç¬‘م‚ڈمپ•مپھمپ‘م‚Œمپ°م€پ
م€€م‚‚مپ£مپ¨مپچم‚Œمپ„مپ«مپڈمپ£مپ¤مپ„مپںمپ¯مپڑمپھم‚“مپ مپ‘مپ©مپم€‚م€چ
shioriمپŒç›®م‚’مپ¤م‚ٹمپ‚مپ’مپ¦è¨€مپ†م€‚
م€Œمپˆم€پمپٹم‚Œمپ®مپ›مپ„مپ‹ï¼ںمپ‚مپ„مپںمپںمپںمƒ»مƒ»مƒ»م‚ڈم€پو‚ھمپ‹مپ£مپںم€‚許مپ—مپ¦مپڈم‚Œم€‚م€چ
مپ©مپ†م‚„م‚‰shioriمپŒو€مپ„هˆ‡م‚ٹUkiمپ®è„‡è…¹م‚’مپ¤مپمپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
م€Œمپ—مپ‹مپ—م€پمپµمپ¤مپ†و‰‹è،“مپ®è·،مپ¯éڑ مپ™مپ م‚چمپ†ï¼ںMikiمپ¯و€مپ„هˆ‡مپ£مپںمپ“مپ¨مپ™م‚‹مپھï¼ںم€چ
DakiniمپŒé مپ®ن¸ٹمپ«و‰‹مپ¬مپگمپ„م‚’ن¹—مپ›مپھمپŒم‚‰è¨€مپ†م€‚
م€Œمپ†م‚“م€پمپ“م‚Œمپ¯éڑ مپ•مپڑç›®مپ«è¦‹مپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپ—مپ¦مپٹمپچمپںمپ„م‚“مپ م€‚
م€€مپ¾مپ‚م€پè‡ھهˆ†مپ®ن¸مپ«ç”کمپ•مپŒه‡؛مپ¦مپچمپںم‚‰م€پمپ“م‚Œم‚’وˆ’م‚پمپ¨مپ—مپ¦و°—م‚’مپ²مپچمپ—م‚پم‚‹
م€€مƒ»مƒ»مƒ»مپ؟مپںمپ„مپھو„ڈه‘³مپ‹مپھم€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپںمپ—مپ‹ه¤§وک”م€پن¸ه›½مپ£مپ¦مپ„مپ†ه›½مپ«مپم‚“مپھمپ“مپ¨م‚ڈمپ–مپŒمپ‚مپ£مپںم‚ˆمپ†مپھمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œè‡¥è–ھهک—胆مپ£مپ¦è¨€مپ†م‚“مپ مپ¨و€مپ†م€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ„مپھمپŒم‚‰م€پç§پمپ¯مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ®ه؟ƒمپ®ن¸مپ«مپ‚م‚‹è¨کو†¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پ
çڑ†مپ®و„ڈ見م‚’èپمپ„مپ¦مپ؟م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ—مپںم€‚
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ¾مپ‚م€پمپ„مپ„م‚ˆمپ†مپ«è€ƒمپˆم‚Œمپ°Mikiمپ®è¨€مپ†é€ڑم‚ٹمپ مپ¨و€مپ†م‚ˆم€‚م€چ
و¸©و³‰مپ®و¨ھمپ«مپ¯ç™½مپڈمپ¦ه¹…مپ®ه؛ƒمپ„و»مپŒم€پو¶¼م‚„مپ‹مپ«وµپم‚Œèگ½مپ،مپ¦مپ„م‚‹م€‚
Dakiniمپ¯è™¹مپ®مپ‹مپ‹م‚‹و»م‚’見مپھمپŒم‚‰مپمپ†è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œو‚ھمپ„م‚ˆمپ†مپ«م‚‚考مپˆم‚‰م‚Œم‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨ï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€پمپ¤مپ¾م‚ٹمƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ®هڈچن¹±م‚’éک²مپگمپںم‚پمپ¨مپ„مپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپمپ®مپںم‚پمپ«è¨کو†¶م‚’ï¼ںم€چ
م€Œمپمپ®ه ´هگˆم€پè¨کو†¶مپ¯و»م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ£مپںèھ°مپ‹مپ®م‚‚مپ®م‚’وŒپمپ£مپ¦مپچمپںمپ®مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„مپ—م€پ
م€€مپ‚م‚‹مپ„مپ¯CGن¼ڑ社مپŒن½œم‚ٹه‡؛مپ—مپںوک هƒڈم‚’ه¹¼ه°‘وœںمپ®è„³مپ«هˆ·م‚ٹè¾¼م‚“مپ مپ®مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„م€‚م€چ
م€Œمپھم‚‹مپ»مپ©مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپ§م‚‚م€پوœ€هˆمپ®ç›®çڑ„مپŒمپھم‚“مپ§مپ‚م‚Œم€پن»ٹمپ¨مپھمپ£مپ،م‚ƒé–¢ن؟‚مپھمپ„مپ®مپ‹م‚‚çں¥م‚Œمپھمپ„مپھم€‚م€چ
م€Œمپˆï¼ںم€چ
م€Œمپ†مپ،مپ®مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م€پن»ٹه؛¦çµگه©ڑمپ™م‚‹م‚“مپ م€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پèپمپ„مپںمپ“مپ¨مپ‚م‚‹م‚ˆم€‚م€چ
م€Œç›¸و‰‹مپ¯Mikiمپ¨هگŒمپکمƒڈمƒ‹مƒ¥م‚¨مƒ¼مƒ«مپ•م€‚مپ»م‚‰م€پçں¥مپ£مپ¦م‚‹مپ م‚چï¼ںم€چ
م€Œمپ‚م€پمپ‚مپ®ن؛؛مپم€‚م€چ
م€Œمپمپم€پمپںمپ¶م‚“مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ¦مپˆمپ®مپ¯ن»ٹه›مپ®مƒ‘م‚¤م‚ھمƒ‹م‚¢ç§»ن½ڈ計画م‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹مپںم‚پمپ«
م€€ç”ںمپ؟ه‡؛مپ•م‚Œمپںم‚‚مپ®مپھم‚“مپ م‚چمپ†م‚ˆم€پمپ§م€پمپٹمپˆم‚‰مپ•م‚“مپںمپ،مپŒè¨ˆç”»مپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپںه¾Œمپ®مپ“مپ¨م‚’
م€€مپ©مپ†è€ƒمپˆمپ¦مپ„م‚‹مپ‹مپ¯çں¥م‚‰مپھمپ„مپ‘مپ©م€پن»ٹمپ“مپ“مپکم‚ƒمپ‚م€پمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپںمپ،مپ مپ‘مپکم‚ƒمپ‚مپھمپ„م€پ
م€€مپ‚مپ،مپ“مپ،مپ§مپٹن¼¼هگˆمپ„مپ®م‚«مƒƒمƒ—مƒ«مپŒه‡؛و¥مپ¦م‚‹م‚“مپ مپœم€‚م€چ
م€Œمپمپ†مپھمپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپ¯مپ¯م€پن¸€ه؛¦ه‹•مپچه‡؛مپ—مپںوµپم‚Œمپ¯و¢م‚پم‚‰م‚Œمپھمپ„مپ•م€‚مپٹمپˆم‚‰مپ•م‚“مپŒه¾Œمپ§و°—مپŒمپ¤مپ„مپںé ƒمپ«
مپ¯م€پ
م€€مپ„مپںم‚‹مپ¨مپ“م‚چمپ§مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒ™م‚¤مƒ“مƒ¼مپŒèھ•ç”ںمپ—مپ¦م‚‹مپ£مپ¦م‚ڈمپ‘مپ م€‚
م€€ن؛؛é،مپ®و–°مپںمپھن¸€و©مپ£مپ¦م‚„مپ¤مپ مپھم€‚
م€€Mikiم€پمپ‚م‚“مپںمپ«مپ مپ£مپ¦مپ„م‚چمپ„م‚چمپٹه£°مپŒمپ‹مپ‹مپ£مپ¦م‚‹م‚“مپ م‚چï¼ںçں¥مپ£مپ¦م‚‹مپœم€‚م€چ
م€Œمپھم€پن½•م‚’و€¥مپ«مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
Dakiniمپ¯Mikiمپ®و–¹مپ¸م€پم‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨هگ‘مپچç›´مپ£مپ¦مپ‹م‚‰è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œمپھمپ‚م€پMikiم€پé€ م‚‰م‚Œمپںç”ںه‘½ن½“م€پن½œم‚‰م‚Œمپںè¨کو†¶مپ£مپ¦مپ®مپ¯مپںمپ—مپ‹مپ«
م€€ه؟ƒمپ«مپ²مپ£مپ‹مپ‹م‚‹مپ‹م‚‚مپ—م‚Œم‚“م€‚مپ§م‚‚م€پمپٹه‰چمپ®مپ“مپ¨م‚’ه¤§ن؛‹مپ«و€مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپ¦م‚‹èھ°مپ‹مپŒ
م€€çڈ¾ه®ںمپ«مپ„م‚‹م‚“مپ م€‚ç”ںمپ¾م‚Œمپ¦مپچمپںن»¥ن¸ٹمپ¯مپم‚Œم‚’ه¤§هˆ‡مپ«م€پمپمپ—مپ¦è‡ھهˆ†مپ®ه¹¸مپ›م‚’ه¤§هˆ‡مپ«
م€€مپ™م‚‹مپ®مپŒمپ„مپ„م€پمپ¨ن؟؛مپ¯و€مپ†مپم€‚م€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»ç§پم€په‡؛م‚‹م€‚م€چ
م€Œم‚“ï¼ںم€چ
م€ŒMikiم€پé،”çœںمپ£èµ¤مپ م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ°مپ£م€پ馬é¹؟م€‚مپ،م‚‡مپ£مپ¨مپ®مپ¼مپ›مپںمپ مپ‘مپ م‚ˆم€‚shioriم€‚م€چ
م‚؟م‚ھمƒ«مپ§و±—م‚’و‹مپچهڈ–م‚ٹم€پمپ„مپ¤م‚‚مپ®ç™½مپ„وˆ¦é—کوœچم‚’è؛«مپ«مپ¤مپ‘م‚‹م€‚
و¸©و³‰مپ§مپ¯ن»ٹه؛¦مپ¯م€پshioriمپ®مپٹ相و‰‹مپ¯èھ°مپ‹مپ¨مپ„مپ†è©±é،Œمپ§ç››م‚ٹن¸ٹمپŒم‚ٹه§‹م‚پمپںم‚ˆمپ†مپ م€‚
مپٹو¹¯م‚’مپ‹مپ‘مپ‚مپ„مپھمپŒم‚‰ç„،é‚ھو°—مپ«ç¬‘مپ†shioriم‚’見مپ¦م€پ
مپ“مپ“مپ«مپچمپ¦وœ¬ه½“مپ«è‰¯مپ‹مپ£مپںم€‚
مپمپ†و€مپ£مپںم€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€ç¬¬ن¸‰è©±م€€çµ‚م‚ڈم‚ٹ
|
第ه››è©±م€€م€€çœںçڈ مپ®و¶™م€€
مپمپ®ه¤œم€پمƒمƒ“مƒ¼ï¼”ï¼چâ—‹ï¼چâ—‹مپ¯مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼مپںمپ،مپ§مپ«مپژم‚ڈمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ن»ٹه¤œمپ¯مƒپمƒ¼مƒ م€ŒSilveryï¼چSnow(SS)م€چمپ®مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپ«و‹›é›†مپŒمپ‹مپ‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ م€‚
وœ€è؟‘مپ«مپھمپ£مپ¦م€پمƒ€مƒ¼م‚¯ه±و€§مپ®é«کمپ„و¦ه™¨مپ®ç™؛見مپŒç›¸و¬،مپژم€پ
م‚ˆمپ†م‚„مپڈéپ؛è·،مپ®وœ€و·±éƒ¨مپ«مپ¾مپ§هˆ°éپ”مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚
مپم‚Œمپ«مپ¤م‚Œم€پéپ؛è·،مپ®هگ„و‰€مپ«و®‹مپ•م‚Œمپںمƒھم‚³مپ®مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸مپ®ه›هڈژم‚‚م€پ
مپ‹مپھم‚ٹمپ®و•°مپ«مپ®مپ¼مپ£مپںم€‚
مپ؟مپھمپŒوŒپمپ،ه¯„مپ£مپںمƒھم‚³مپ®مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸م‚’çµ±هگˆمپ—م€پ
ن»ٹه¾Œمپ®è،Œه‹•مپ®وŒ‡é‡م‚’و±؛ه®ڑمپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ„مپ†مپ®مپŒم€پ
ن»ٹه¤œمپ®مƒںمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³م‚°مپ®مƒ†مƒ¼مƒمپ مپ£مپںم€‚
هگ„è‡ھمپŒوŒپمپ،ه¯„مپ£مپںمƒھم‚³مپ®مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’م‚»مƒƒمƒˆمپ™م‚‹م€‚
وƒ…ه ±و‹…ه½“مپ®IZمپŒم‚«م‚؟م‚«م‚؟مپ¨م‚مƒ¼مƒœمƒ¼مƒ‰م‚’هڈ©مپچم€پمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’ن¸€مپ¤مپ«مپ¾مپ¨م‚پن¸ٹمپ’م‚‹م€‚
م€Œمپ“م‚“مپھو„ںمپکمپ§مپ™م€‚مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م€‚م€چ
م€Œمپ†م‚€مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مپ„مپ„مپ م‚چمپ†م€‚مپ؟م‚“مپھمƒ‡م‚£م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¤م‚’見مپ¦مپڈم‚Œم€‚م€چ
ه£پمپ«مپ‹مپ‹مپ£مپں1ï¼گï¼گم‚¤مƒ³مƒپمپ®مƒ‡م‚£م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¤مپ«م€پ
مپ¾مپ¨م‚پمپ‚مپ’م‚‰م‚Œمپںمپ°مپ‹م‚ٹمپ®مƒھم‚³مپ®مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸مپŒو¬،م€…وک مپ—ه‡؛مپ•م‚Œم‚‹م€‚
م€Œمپˆم€پمپمپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ مپ£مپںمپ®ï¼ںم€چ
مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸مپ®ن¸مپ«مپ¯م€پوکژم‚‰مپ‹مپ«çˆ¶مپ¸مپ®éپ؛言مپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚
م€Œمپ¾مپ•مپ‹م€پمپکم‚ƒمپ‚مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپ‚مپ،مپ“مپ،مپ§مپ–م‚ڈم‚پمپچمپŒèµ·مپچم‚‹م€‚
م€Œمپ؟م‚“مپھم€پèپمپ„مپ¦و¬²مپ—مپ„م€‚م€چ
話مپ—ه£°مپŒمپ´مپںمپ¨و¢مپ¾م‚‹م€‚
م€Œه‰چمپ‹م‚‰è–„م€…مپمپ†مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹مپ¨مپ¯و€مپ£مپ¦مپ„مپںم‚“مپ مپŒم€پمپ“م‚Œمپ§مپ¯مپ£مپچم‚ٹمپ—مپںم€‚م€چ
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®TeitokuمپŒçڑ†مپ®è¼ھمپ®ن¸ه؟ƒمپ«ç«‹مپ،م€په…¨ه“،مپ®é،”م‚’çœ؛م‚پمپھمپŒم‚‰è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œمپ“مپ®وکںمپ®هœ°ن¸‹و·±مپڈمپ«مپ¯م€پمƒ€مƒ¼م‚¯مƒ•م‚،مƒ«م‚¹مپ¨مپ„مپ†هگچه‰چمپ®è¶…ç”ںه‘½ن½“مپŒه°پمپکم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€€وˆ‘م€…مپ¯è¸ڈمپ؟مپ“م‚“مپ§مپ¯مپ„مپ‘مپھمپ„ه¢“ه ´مپ«ç«‹مپ،ه…¥مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںمپ®مپ م€‚م€چ
م€Œمپ—مپ‹م‚‚مپمپ„مپ¤مپ¯م€پم‚‚مپ†و—¢مپ«ه¾©و´»مپ—مپ¤مپ¤مپ‚م‚‹م‚“مپ§مپ™م€‚م€چ
IZمپŒè£œè¶³èھ¬وکژمپ™م‚‹م€‚
و„ںوƒ…م‚’وٹ‘مپˆم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پمپمپ®ه£°مپ®éœ‡مپˆمپ¯م€پمپمپ®ه ´مپ«مپ„م‚‹èھ°م‚‚مپ«ن¼م‚ڈمپ£مپںم€‚
shioriمپŒو‚²ç—›مپھه£°م‚’مپ‚مپ’م‚‹م€‚
م€Œمپکم‚ƒمپ‚م€پمƒھم‚³مپ¯ï¼ںم€چ
م€Œمپٹمپم‚‰مپڈمƒ€مƒ¼م‚¯مƒ•م‚،مƒ«م‚¹مپ®ه¾©و´»م‚’مپھم‚“مپ¨مپ‹éک»و¢مپ—م‚ˆمپ†مپ¨م€پ
م€€وœ€ه¾Œمپ®و‰‰م‚’é–‹مپ‘مپںم‚“مپ م‚چمپ†م€‚م€چ
TeitokuمپŒه†·é™مپ«هˆ†وگمپ™م‚‹م€‚
مپ—مپ°م‚‰مپڈمپ®é–“م€پï¼”ï¼چâ—‹ï¼چâ—‹مپ®مƒمƒ“مƒ¼م‚’م€پو²ˆé»™مپŒو”¯é…چمپ—مپںم€‚
مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
م€Œمپ§م‚‚م€پن»ٹمپ«مپھمپ£مپ¦م‚‚و¶ˆوپ¯مپŒçں¥م‚Œمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
shioriمپŒè¨€مپ£مپ¦مپ¯مپ„مپ‘مپھمپ„مپ“مپ¨م‚’言مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںم‚ˆمپ†مپھ言مپ„و–¹م‚’مپ—مپںم€‚
Teitokuمپ¯م‚„مپ¯م‚ٹه†·é™مپ«è¨€مپ†م€‚
م€Œمپمپ†م€پمپ¤مپ¾م‚ٹمƒھم‚³مپ¯م€پ
م€€مƒ€مƒ¼م‚¯مƒ•م‚،مƒ«م‚¹مپ¨مپ„مپ†م‚„مپ¤مپ«هڈ–م‚ٹè¾¼مپ¾م‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںهڈ¯èƒ½و€§مپŒه¤§مپچمپ„م€‚م€چ
م€Œمƒ€مƒ¼م‚¯مƒ•م‚،مƒ«م‚¹مپ¯م€په®Œه…¨ه¾©و´»مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پ
م€€م‚ˆم‚ٹه¼·مپ„ن¾ن»£ï¼ˆم‚ˆم‚ٹمپ—م‚چ)م‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚م€چ
IZمپŒمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®è¨€è‘‰م‚’ه¼•مپچ継مپگم€‚
مپ”مپڈم‚ٹمƒ»مƒ»مƒ»مپ¨èھ°مپ‹مپŒç”ںه”¾م‚’飲مپ؟è¾¼م‚€م€‚
مپ¤مپ‘مپ£مپ±مپھمپ—مپ®مƒ‡م‚£م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¤مپ«مپ¯م€پè‹¥مپ„ه¥³و€§مپŒè–„مپ„è،£م‚’مپ¾مپ¨مپ„م€پ
مƒ©م‚°م‚ھمƒ«هœ°ن¸‹مپ‹م‚‰ç›´é€پمپ•م‚Œمپںه¤©ç„¶و°´م‚’مپ“مپڈمپ“مپڈ飲م‚€م€پ
مپ¨مپ„مپ†ه®ںمپ«è„³ه¤©و°—مپھCMمپŒوµپم‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚
مپمپ®و™‚م€پمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹é€ںه ±مپŒوµپم‚Œمپںم€‚
م€Œé€ںه ±مپ§مپ™م€‚م€چ
ه·¨ه¤§مپھç”»é¢مپ„مپ£مپ±مپ„مپ«è¦‹و…£م‚Œمپںه¥³و€§مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م‚مƒ£م‚¹م‚؟مƒ¼مپ®é،”مپŒوک مپ—ه‡؛مپ•م‚Œم‚‹م€‚
م€Œوƒ‘وکںمƒ©م‚°م‚ھمƒ«هœ°ن¸‹مپ§م€پéپژهژ»مپ«ç•°وکںن؛؛مپŒو®‹مپ—مپںمپ¨
م€€è¦‹م‚‰م‚Œم‚‹ه‘éپ“مپŒç™؛見مپ•م‚Œمپ¦مپ‹م‚‰م€پ1週間مپŒمپںمپ،مپ¾مپ—مپںم€‚
م€€مپ¾مپںم€پمپمپ®ه‘éپ“مپ§مپ¯ç¨¼هƒچن¸مپ®é›»هگه…µه™¨مپŒه¤ڑو•°ç¢؛èھچمپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
م€€مپ“مپ®é›»هگه…µه™¨مپ¯ه¤–部مپ‹م‚‰مپ®ن¾µه…¥è€…م‚’وژ’除مپ™م‚‹م‚ˆمپ†
م€€مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپںم‚پم€پن»ٹمپ¾مپ§ه¤ڑمپڈمپ®مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼مپںمپ،مپŒم€پ
م€€و’¤é€€م‚’ن½™ه„€مپھمپڈمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںمپŒم€پمپ“مپ®ه؛¦مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپ؟مپھمپŒم€Œمپٹمپ„مپٹمپ„م€چمپ¨مپ„مپ†م‚ˆمپ†مپھن»•èچ‰مپ§مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م‚’見م‚‹م€‚
م€Œمپ¾مپںم€پمپڑمپ„مپ¶م‚“éپ…مپ„وƒ…ه ±مپ مپھم€‚م€چ
م€Œه‘éپ“مپ®ن¸‹مپ«éپ؛è·،مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨م€پمپٹمپˆم‚‰مپ•م‚“مپ¯مپ¨مپ£مپڈمپ«مپ”هکçں¥مپ®çˆمپکم‚ƒمپ‚ï¼ںم€چ
CrystalمپŒTeitokuمپ«ه•ڈمپ†م€‚
م€Œمپ†م‚€م€پمƒھم‚³مپ®مƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸م‚‚é€گن¸€ه ±ه‘ٹمپ—مپ¦مپ‚م‚‹م€‚مپچمپ£مپ¨و°‘é–“ن؛؛مپ«مپ¯م€پ
م€€ç¢؛ه®ڑمپ—مپںوƒ…ه ±مپ—مپ‹وµپمپ•مپھمپ„م‚“مپ م‚چمپ†م€‚م€چ
مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م‚مƒ£م‚¹م‚؟مƒ¼مپ¯مپ“مپ“مپ§ن¸€ه‘¼هگ¸ه…¥م‚Œم€پ
و¬،مپ«مپ«مپ£مپ“م‚ٹمپ¨و؛€é¢مپ«ç¬‘مپ؟م‚’وµ®مپ‹مپ¹مپ¦ç¶ڑمپ‘مپںم€‚
م€Œمپ“مپ®ه؛¦م€پمƒپمƒ¼مƒ SSمپŒم€په‘éپ“وœ€و·±éƒ¨مپ«مپ‚م‚‹مƒ،م‚¤مƒ³م‚³مƒ³مƒ”مƒ¥مƒ¼م‚؟مƒ¼مپ«وژ¥è§¦م€پ
م€€مپ“م‚Œم‚’و²ˆé»™مپ•مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ«وˆگهٹںمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€€ن»ٹه›مپ®و¥ç¸¾م‚’مپںمپںمپˆم€پمƒپمƒ¼مƒ SSمپ«مپ¯
م€€ç·ڈç£مپ‹م‚‰و„ںè¬çٹ¶مپ¨ç‰¹هˆ¥ه ±ه¥¨é‡‘مپŒè´ˆم‚‰م‚Œم‚‹ن؛ˆه®ڑمپ§مپ™م€‚
م€€مپم‚Œمپ§مپ¯مپ“مپ“مپ§م€پوƒ‘وکںمƒ©م‚°م‚ھمƒ«ç”ں物ه¦ç ”究مپ®ç¬¬ن¸€ن؛؛者مپ§مپ‚م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»هچڑه£«مپ«مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپٹمپٹï¼پمپ¨مƒمƒ“مƒ¼مپŒمپ©م‚ˆم‚پمپڈم€‚
م€Œمپ™مپ’مپˆم€‚م€چ
م€Œç‰¹هˆ¥ه ±ه¥¨é‡‘مپ مپ£مپ¦م‚ˆم€‚م€چ
م€Œم‚„مپ£مپںمپم€پمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼ï¼پم€چ
م€Œمپ“م‚Œمپ§ه®´ن¼ڑمپ ï½م€‚م€چ
ن»ٹمپ¾مپ§مپ®è‹¦هٹ´مپŒمپ™مپ•مپ¾مپکمپ‹مپ£مپںهˆ†م€پ
مپم‚ŒمپŒè©•ن¾،مپ•م‚Œم‚‹مپ¨مپھم‚‹مپ¨م€پم‚„مپ¯م‚ٹمپ†م‚Œمپ—مپ„م‚‚مپ®م€‚
ç§پمپںمپ،مپ¯çڑ†و‰‹م‚’مپ¨م‚ٹمپ‚مپ„م€پè·³مپن¸ٹمپŒمپ£مپ¦ه–œمپ³م‚’هˆ†مپ‹مپ،هگˆمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
مپ مپŒم€پTeitokuمپ¯وµ®مپ‹م‚Œمپںé›°ه›²و°—مپ®ن¸م€پن¸€ن؛؛م€پ
مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ®ç¶ڑمپچمپ«مپکمپ£مپ¨èپمپچه…¥مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ç”»é¢مپ§مپ¯م€پم‚مƒ£م‚¹م‚؟مƒ¼مپ¨هچڑه£«مپŒمƒ†مƒ¼مƒ–مƒ«م‚’مپ¯مپ•مپ؟م€پ
و–œم‚پمپ«هگ‘مپ‹مپ„هگˆمپ†ه½¢مپ§ه؛§مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€Œمپ•مپ¾مپ–مپ¾مپھé›»هگه…µه™¨مپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯م€پ
م€€وƒ‘وکںمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ«é«که؛¦مپھو–‡وکژم‚’وŒپمپ¤ç•°وکںن؛؛مپŒ
م€€مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںم€چ
م‚مƒ£م‚¹م‚؟مƒ¼مپŒهچڑه£«مپ«م€پمپ؟مپھمپŒوŒپمپ¤مپ§مپ‚م‚چمپ†ه½“然مپ®è³ھه•ڈم‚’وٹ•مپ’مپ‹مپ‘مپںم€‚
هچڑه£«مپ¯وکژم‚‹مپڈ笑مپ„مپھمپŒم‚‰ç”مپˆمپںم€‚
م€Œن»ٹمپ®مپ¨مپ“م‚چمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ«ç•°وکںن؛؛مپ®هکهœ¨مپ¯ç¢؛èھچمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
م€€مپ™مپ¹مپ¦مپ®é›»هگه…µه™¨مپ¯م€پم‚³مƒ³مƒ”مƒ¥مƒ¼م‚؟مƒ¼مپ®مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ«ه¾“مپ£مپ¦ه‹•مپ„مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
م€€مپ‹مپ¤مپ¦مپ“مپ®وکںمپ«ن½ڈم‚“مپ§مپ„مپںç•°وکںن؛؛مپںمپ،مپ¯م€پمپھم‚“م‚‰مپ‹مپ®çگ†ç”±مپ§م€پ
م€€مپ™مپ§مپ«مپ“مپ“م‚’ç«‹مپ،هژ»مپ£مپںمپ¨و€م‚ڈم‚Œمپ¾مپ™م€‚م€چ
م€Œمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯م€پمپ“م‚Œمپ§م€پن»ٹمپ¾مپ§مپ«èµ·مپچمپںو§کم€…مپھن؛‹ن»¶مپ«م‚‚
م€€و±؛ç€مپŒمپ¤مپ„مپںمپ¨è€ƒمپˆمپ¦م‚ˆمپ„مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںم€چ
م€Œمپ¾مپ و–言مپ¯مپ§مپچمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پمپمپ®هڈ¯èƒ½و€§مپ¯é«کمپ„مپ§مپ™مپم€‚
م€€ن¸»ن؛؛مپŒمپ„مپھمپڈمپھمپ£مپ¦م‚‚م€پم‚³مƒ³مƒ”مƒ¥مƒ¼م‚؟مƒ¼مپ¯ه؟ ه®ںمپ«è¨€مپ„مپ¤مپ‘م‚’ه®ˆم‚ٹم€پ
م€€وˆ‘م€…ه¤–و¥è€…م‚’وژ’除مپ—ç¶ڑمپ‘مپ¦مپچمپںم€‚مپمپ®م‚³مƒ³مƒ”مƒ¥مƒ¼م‚؟مƒ¼مپŒهˆ¶هœ§مپ•م‚Œمپںن»ٹم€پ
م€€وˆ‘م€…مپ¯مƒ©م‚°م‚ھمƒ«ç§»ن½ڈمپ«هگ‘مپ‘مپ¦ه¤§مپچمپڈ1و©ه‰چ進مپ—مپںمپ¨è¨€مپ£مپ¦م‚ˆمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚م€چ
Teitokuمپ¯çœ‰م‚’و›‡م‚‰مپ›مپ¦ن؛Œن؛؛مپ®م‚„م‚ٹمپ¨م‚ٹم‚’èپمپ„مپ¦مپ„مپںمپŒم€پ
هچڑه£«مپ®و¥½è¦³çڑ„مپھ見解م‚’èپمپڈمپ«هڈٹمپ³م€پ
م‚‚مپ†è€گمپˆم‚‰م‚Œمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†è،¨وƒ…م‚’مپ—مپ¦èˆŒو‰“مپ،مپ—مپںم€‚
مپمپ®و™‚م€پمƒمƒ“مƒ¼مپ«è¦‹و…£م‚Œمپھمپ„ن؛؛物مپŒçڈ¾م‚Œمپںم€‚
مپ™مپگو¨ھمپ«ç«‹مپ£مپ¦مپ„مپںUkiمپ«ن½•ن؛‹مپ‹ه°‹مپم‚‹م€‚
UkiمپŒTeitokuمپ®و–¹م‚’وŒ‡مپ™مپ¨م€پç”·مپ¯ه§؟ه‹¢م‚’و£مپ—م€پ
مپ¾مپ£مپ™مپگمپ«Teitokuمپ®ه‰چمپ¾مپ§و¥م‚‹مپ¨م€پوڈ،و‰‹م‚’و±‚م‚پمپھمپŒم‚‰è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œهˆم‚پمپ¾مپ—مپ¦م€پم‚ڈمپںمپڈمپ—م€پç·ڈç£مپ®ن»£çگ†مپ¨مپ—مپ¦هڈ‚م‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚م€چ
مپٹمپٹمƒ»مƒ»مƒ»مپ¨ه†چمپ³مƒمƒ“مƒ¼مپŒمپ©م‚ˆم‚پمپڈم€‚
مپ؟مپھمپ¯éپ ه·»مپچمپ«مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ¨ç·ڈç£ن»£çگ†ن؛؛م‚’ه›²م‚“مپ م€‚
مپ©مپ†م‚„م‚‰وژˆè³ه¼ڈمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®و‰“مپ،هگˆم‚ڈمپ›م‚’مپ—مپ«و¥مپںم‚‰مپ—مپ„م€‚
م‚„مپŒمپ¦è©±مپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپںم‚‰مپ—مپڈم€پن»£çگ†ن؛؛مپ¯è»½مپڈن¸€ç¤¼مپ™م‚‹مپ¨م€پ
مپ²م‚…م€پ
مپ¨مپمپ®ه ´مپ‹م‚‰ç«‹مپ،هژ»مپ£مپںم€‚
CrystalمپŒمپ½م‚“مپ¨Teitokuمپ®è‚©م‚’هڈ©مپ„مپ¦è¨€مپ†م€‚
م€Œمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م€پوژˆè³ه¼ڈمپ„مپ¤مپ مپ£مپ¦ï¼ںم€چ
Teitokuمپ¯ç”مپˆمپھمپ„م€‚
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںم‚“مپ مپ„م€پمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م€‚م€چ
م€Œمپ؟م‚“مپھمƒ»مƒ»مƒ»م€پو‚ھمپ„مپŒم€پن؟؛مپ¯وژˆè³ه¼ڈمپ«مپ¯ه‡؛ه¸مپ—مپھمپ„م€‚م€چ
مƒ»مƒ»مƒ»مپˆï¼پ
مپ–م‚ڈمپ¤مپ„مپںç©؛و°—مپŒن¸€ç¬é™مپ¾م‚‹م€‚
çڑ†مپ®è¦–ç·ڑمپŒو¬،م€…م€پTeitokuمپ«é›†ن¸مپ™م‚‹م€‚
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ مپ‹م‚‰م€په®´ن¼ڑم‚‚م€پمپمپ®مƒ»مƒ»مƒ»مپھمپ—مپ م€‚م€چ
çڑ†مپ®è¦–ç·ڑم‚’مپ—مپ£مپ‹م‚ٹمپ¨هڈ—مپ‘و¢م‚پمپھمپŒم‚‰م€پTeitokuمپ¯م‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œمپ؟م‚“مپھم€پمپ“مپ“مپ«مپڈم‚‹مپ¾مپ§éڑڈهˆ†ه¤§ه¤‰مپھو€مپ„م‚’مپ—مپ¦مپچمپںم‚ˆمپھم€‚
م€€Mikiمپ،م‚ƒم‚“مپ؟مپںمپ„مپ«ç€•و»مپ®é‡چه‚·م‚’è² مپ£مپں者م‚‚مپ„م‚‹م€‚م€چ
ن»ٹه؛¦مپ¯ç§پمپ«çڑ†مپ®è¦–ç·ڑمپŒن¸€ç¬é›†مپ¾م‚‹م€‚shioriمپŒمپ†م‚“مپ†م‚“مپ¨مپ†مپھمپڑمپڈم€‚
م€Œمپ“مپ“م‚‰مپ§ن¸€وپ¯ه…¥م‚Œمپںمپ„مپ®مپ¯م‚ˆمپڈم‚ڈمپ‹م‚‹م€‚ن؟؛مپ مپ£مپ¦é¨’مپگمپ®مپ¯ه¤§ه¥½مپچمپ م€‚م€چ
م€Œمپکم‚ƒم€پمپ©مپ†مپ—مپ¦ï¼ںم€چ
UkiمپŒç´ ç›´مپھو°—وŒپمپ،م‚’è،¨مپ™م€‚
م€Œن»ٹمپ¯مپم‚“مپھو°—هˆ†مپکم‚ƒمپھمپ„م€پمپمپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚ˆمپم€‚م€چ
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®è¨€è‘‰م‚’継مپ„مپ مپ®مپ¯Chieمپ مپ£مپںم€‚
م€ŒChieمپ•م‚“مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
UkiمپŒو°—م‚’هˆ©مپ‹مپ—م€پTeitokuمپ¨Chieمپ¨مپ®é–“مپ«م€پéپ“م‚’é–‹مپ‘م‚‹م€‚
م€ŒChieمپ‹مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
Teitokuمپ¯Chieمپ®ç³م‚’مپ¾مپ£مپ™مپگ見مپ¤م‚پمپںم€‚
ه½¼ه¥³مپ¯Teitokuمپ®ه©ڑ約者مپ م€‚Teitokuمپ®و¨ھمپ«مپ™مپ£مپ¨è؟‘ه¯„م‚‹مپ¨è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œçœںçڈ مپ®و¶™مƒ»مƒ»مƒ»مپ§مپ—م‚‡ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپٹه‰چمپ«مپ¯مپمپ®è©±م€پمپ—مپںم‚“مپ مپ£مپ‘مپھمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
UkiمپŒç–‘ه•ڈم‚’وٹ•مپ’مپ‹مپ‘م‚‹م€‚
م€Œمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼م€پçœںçڈ مپ®و¶™مپ£مپ¦ï¼ںم€چ
م€Œم‚“ï¼ںمپ‚مپ‚مƒ»مƒ»مƒ»مپ„م‚„م€چ
Chieمپ¯مپںم‚پم‚‰مپ†مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®è„‡è…¹م‚’مپ¤مپ¤مپ„مپ¦è¨€مپ†م€‚
م€Œç§پمپŒمپ‹م‚ڈمپ£مپ¦مپ؟م‚“مپھمپ«è©±مپمپ†مپ‹ï¼ںم€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ†م‚“م€پمپٹه‰چمپŒمپمپ†مپ—مپںمپ„م‚“مپھم‚‰مƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†مپ—مپ¦è²°مپٹمپ†مپ‹م€‚
م€€ن؟؛مپ¯ç…§م‚Œمپڈمپ•مپڈمپ¦مپ¨مپ¦م‚‚言مپˆمپمپ†مپ«مپھمپ„مپ—مپھم€‚م€چ
م€Œمپ†م‚“م€‚م€چ
Chieمپ¯çڑ†مپ®و–¹م‚’هگ‘مپچç›´م‚‹مپ¨م€پمپ„مپںمپڑم‚‰مپ£مپ½مپ„ç›®م‚’مپڈم‚‹م‚ٹمپ¨ه›مپ—مپ¦è©±مپ—ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œمپ‚مپ®مپم€پمƒ†م‚¤مپ•م‚“مپ¯ن»ٹمپ§مپ“مپم€پمپ“م‚“مپھمپ”مپ£مپ¤مپ„ن½“مپ—مپ¦م‚‹مپ‘مپ©م€پ
م€€هگمپ©م‚‚مپ®é ƒمپ¯مپ™مپ£مپ”مپ„و³£مپچ虫مپ مپ£مپںم‚“مپ م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپم‚“مپھه‰چç½®مپچمپ¯مپ„مپ„مپ‹م‚‰م€پمپ•مپ£مپ•مپ¨وœ¬é،Œم‚’ه§‹م‚پم‚چم‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ¯ï½مپ„م€پمپکم‚ƒمپ‚و³£مپچ虫مƒ†م‚¤مپ•م‚“مپ®مپٹ話م€په§‹مپ¾م‚ٹه§‹مپ¾م‚ٹï½م€‚م€چ
Teitokuمپ«مپ½مپ‹م‚ٹمپ¨é م‚’هڈ©مپ‹م‚ŒمپھمپŒم‚‰م€پChieمپŒèھم‚ٹه§‹م‚پمپںمپ®مپ¯م€پمپ“م‚“مپھ話مپ م€‚
م€€ï¼’ه¹´ï¼“組مپ¯مپمپ®و™‚م€پمپ„مپ¤مپ¾مپ§مپںمپ£مپ¦م‚‚é™مپ‹مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
وژˆو¥ن¸مپھمپ®مپ§مپ™مپŒم€په…ˆç”ںمپ¯و€¥مپھ用ن؛‹مپŒه‡؛و¥مپ¦م€پ
مپ—مپ°م‚‰مپڈه‡؛مپ¦مپ„مپ£مپںمپچم‚ٹمپھمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
مپ؟م‚“مپھه…ˆç”ںمپ¨مپ‹م‚ڈمپ—مپں
م€Œé™مپ‹مپ«è‡ھç؟’مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚م€چ
مپھمپ©مپ¨مپ„مپ†ç´„وںمپھمپ©مپ¨مپ†مپ«ه؟کم‚Œم€په¥½مپچه‹و‰‹مپ«é¨’مپ„مپ§مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
مƒ»مƒ»مƒ»
éڑڈهˆ†مپںمپ£مپ¦مپ‹م‚‰م€پم‚„مپ£مپ¨ه…ˆç”ںمپŒوˆ»مپ£مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚
مپ‚مپ¾م‚ٹمپ®é¨’مپŒمپ—مپ•مپ«م€په…ˆç”ںمپ®و€’م‚ٹمپ¯ه½“然مپ®مپ”مپ¨مپڈ爆ç™؛مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œه…¨ه“،م€پن¸ه؛مپ«ه‡؛مپھمپ•مپ„م€‚م€چ
ه¼·مپ„و„ڈه؟—مپ¨ç‡ƒمپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپھو€’م‚ٹم‚’ç§کم‚پمپںهڈ£èھ؟مپ§مپ—مپںم€‚
çڑ†م€پمپ—مƒ¼م‚“مپ¨é™مپ¾م‚ٹمپ‹مپˆم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
ن¸ه؛مپ«çڑ†م‚’ç«‹مپںمپ›م‚‹مپ¨م€په…ˆç”ںمپ®é•·مپ„مپٹèھ¬و•™مپŒه§‹مپ¾م‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
ن»–مپ®م‚¯مƒ©م‚¹مپ®هگمپںمپ،مپŒم€پç§پمپںمپ،م‚’見مپ¦مپ¯مپڈمپ™مپڈمپ™ç¬‘مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
م€Œه…ˆç”ںمپ®è¨€مپ„مپ¤مپ‘م‚’èپمپ‹مپڑمپ«é¨’مپ„مپ§مپ„مپںç½°مپ م€‚م€چ
مپ¨è¨€مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹مپ®م‚ˆمپ†مپ«ç§پمپ«مپ¯و€مپˆمپ¾مپ—مپںم€‚مپ™مپ”مپڈوپ¥مپڑمپ‹مپ—مپڈو„ںمپکمپ¾مپ—مپںم€‚
م‚„مپŒمپ¦م€په…ˆç”ںمپ¯ç§پمپںمپ،مپ«هڈچçœپم‚’ن؟ƒمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œن»ٹو—¥مپ؟مپںمپ„مپھمپ“مپ¨مپ¯ن؛Œه؛¦مپ¨مپ—مپ¾مپ›م‚“مپ¨ç´„وںمپ§مپچم‚‹هگمپ مپ‘م€پو•™ه®¤مپ«ه…¥م‚ٹمپھمپ•مپ„م€‚م€چ
çڑ†مپ¯مپ—مپ°م‚‰مپڈé€،ه·،مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںمپŒم€پن¸€ن؛؛مپ®هˆ©ç™؛مپھهگمپŒ
م€Œم‚‚مپ†مپ—مپ¾مپ›م‚“م€‚ç´„وںمپ—مپ¾مپ™م€‚م€چ
مپ¨ه…ˆç”ںمپ«ه‘ٹمپ’مپ¦و•™ه®¤مپ«ه…¥م‚‹مپ®م‚’見م‚‹مپ¨م€پمپم‚Œمپ«ه‹‡و°—م‚’ه¾—مپںم‚ˆمپ†مپ«و¬،م€…مپ¨
م€Œمپ”م‚پم‚“مپھمپ•مپ„م€‚م€چ
م€Œن»ٹه؛¦مپ‹م‚‰مپ¯م‚‚مپ†مپ—مپ¾مپ›م‚“م€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦ن¸€ن؛؛م€پمپ¾مپںن¸€ن؛؛مپ¨م€پو•™ه®¤مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„مپڈمپ®مپ§مپ™م€‚
ç§پمپ¯مپھمپœمپ‹è¶³مپŒه‹•مپچمپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨م€پن¸ه؛مپ«ç«‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ¯ç§پن¸€ن؛؛مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
ه…ˆç”ںمپ¯م€پç§پمپŒوœ€ه¾Œمپ¾مپ§و®‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپŒو„ڈه¤–مپمپ†مپھé،”مپ¤مپچمپ§مپ—مپںم€‚
م‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨è؟‘مپ¥مپ„مپ¦مپچمپ¦èپمپچمپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمپ©مپ†مپ—مپ¦مپ‚مپھمپںمپ¯م€په…ˆç”ںمپ«ç´„وںمپŒمپ§مپچمپھمپ„مپ®ï¼ںم€چ
م‚„مپ•مپ—مپڈèپمپ„مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚مپ§م‚‚م€پç›®مپ¯و‚²مپ—مپمپ†مپ«و·±مپ„é’色مپھمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
ç§پمپ¯م€پمپھمپœè‡ھهˆ†مپŒمپ“مپ“مپ«و®‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ‹م€په®ںمپ®مپ¨مپ“م‚چمپ¯è‡ھهˆ†مپ§م‚‚م‚ˆمپڈ
م‚ڈمپ‹مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
مپںمپ م€پç§پمپ®مپ—مپںمپ“مپ¨مپŒه…ˆç”ںم‚’مپ¨مپ¦م‚‚و‚²مپ—مپ¾مپ›مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںم‚‰مپ—مپ„م€پ
مپم‚ŒمپŒمپ¨مپ¦م‚‚مپ¤م‚‰مپ‹مپ£مپںمپ®مپ§م€پç§پمپ¯مپ¹مپمپ¹مپمپ¨و³£مپچمپ مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œو³£مپ„مپ¦مپھمپ„مپ§م€پمپ©مپ†مپ—مپ¦ç´„وںمپ§مپچمپھمپ„مپ®مپ‹م€په…ˆç”ںمپ«è¨€مپ£مپ¦مپ”م‚‰م‚“م€‚م€چ
مپ—م‚ƒمپڈم‚ٹمپ‚مپ’مپھمپŒم‚‰م€پ考مپˆمپ¦مپ؟مپ¾مپ—مپںم€‚مپھمپœç§پمپ¯ç´„وںمپ§مپچمپھمپ„مپ®مپ‹م‚’م€‚
مپمپ—مپ¦ن¸€è¨€مپڑمپ¤è€ƒمپˆمپھمپŒم‚‰è©±مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œç§پمپںمپ،مپ¯ه‰چمپ«م‚‚هگŒمپکم‚ˆمپ†مپھمپ“مپ¨م‚’مپ—مپ¦م€په…ˆç”ںمپ«و€’م‚‰م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚م€چ
ه…ˆç”ںمپ¯مپ¾مپںو„ڈه¤–مپمپ†مپھé،”م‚’مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمپمپ®و™‚مپ«م‚‚م€پن»ٹو—¥مپ¨هگŒمپکم‚ˆمپ†مپ«م€په…ˆç”ںمپ¨ç´„وںم‚’مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚م€چ
مپمپ†م€پمپ‚مپ®و™‚م‚‚ن»ٹو—¥مپ¨هگŒمپکم‚ˆمپ†مپ«ç§پمپںمپ،مپ¯ه…ˆç”ںمپ¨ç´„وںم‚’مپ—مپںمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€Œمپ§م‚‚م€پن»ٹو—¥م€پمپ؟م‚“مپھمپ¯ه…ˆç”ںمپ¨مپ®ç´„وںم‚’ه®ˆم‚Œمپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
م€€مپ مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»ن»ٹم€پç´„وںمپ—مپ¦م‚‚مپ؟م‚“مپھمپ¾مپںه®ˆم‚Œمپھمپ„مپ م‚چمپ†مپھمپ¨م€پمپمپ†و€مپ£مپںم‚“مپ§
مپ™م€‚م€چ
ç§پمپ¯مپ½مپںمپ½مپںمپ¨و¶™م‚’ه؛ٹمپ«èگ½مپ¨مپ—مپھمپŒم‚‰è©±مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚ه…ˆç”ںمپ¨ï¼‘ه¯¾ï¼‘مپ§è©±مپ™م€‚
مپ“م‚“مپھه¤§مپم‚Œمپںمپ“مپ¨م‚’مپ™م‚‹مپ«مپ¯م€پç§پمپ¯مپ‚مپ¾م‚ٹمپ«و³£مپچ虫مپ مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚
م€Œمپمپ†مƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†مپم€‚مپ‚مپھمپںمپ®è¨€مپ†مپ¨مپٹم‚ٹمپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„م‚ڈم€‚م€چ
ه…ˆç”ںمپ¯ه¤§مپچمپڈمپ†مپھمپڑمپڈمپ¨ç§پمپ®و‰‹م‚’وڈ،م‚ٹم€پو•™ه®¤مپ«ه¼•مپ£ه¼µم‚ٹè¾¼مپ؟مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ©مپ†مپ™م‚‹م‚“مپ م‚چمپ†مپ¨ه…ˆç”ںمپ®é،”م‚’見مپ¦مپ„م‚‹مپ¨م€په…ˆç”ںمپ¯مپ„مپ¤مپ®é–“مپ«مپ‹ه¤§ç²’مپ®و¶™م‚’
مپ½م‚چمپ½م‚چمپ¨وµپمپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚ç§پمپ¯مپ³مپ£مپڈم‚ٹمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ©مپ†مپ—مپںم‚“مپ م‚چمپ†ï¼ںمپ¨è€ƒمپˆم‚‹é–“م‚‚مپھمپڈم€په…ˆç”ںمپ¯
م€Œمپ؟مپھمپ•م‚“م€پمپٹèپمپچمپھمپ•مپ„م€‚م€چ
ه¤§مپچمپھه£°مپ§مپ؟م‚“مپھمپ«ه‘¼مپ³مپ‹مپ‘مپ¾مپ—مپںم€‚
م€Œمƒ†م‚¤مپ•م‚“مپ¯م€پمپ؟مپھمپ•م‚“مپ®مپںم‚پمپ«و³£مپ„مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
م€€ه…ˆç”ںمپ¨مپ®ç´„وںم‚’ن»ٹو—¥م€پمپ؟مپھمپ•م‚“مپ¯ç ´م‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
م€€مپ مپ‹م‚‰ن»ٹو—¥مپ®مپ“مپ®ç´„وںم‚‚م€پمپ¾مپںç ´م‚‹مپ م‚چمپ†مپ¨è€ƒمپˆمپ¦م€پ
م€€مپم‚ŒمپŒو‚²مپ—مپڈمپ¦مƒ†م‚¤مپ•م‚“مپ¯و³£مپ„مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚م€چ
ç§پمپ¯é©ڑو„•مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
ç§پمپŒو³£مپ„مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ¯مپم‚“مپھé«که°ڑمپھçگ†ç”±مپ‹م‚‰مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚
مپںمپ ç§پمپŒè‡†ç—…مپ§و³£مپچ虫مپ مپ‹م‚‰مپ م€‚مپم‚Œم‚’ه…ˆç”ںمپ¯مپ„مپ„م‚ˆمپ†مپ«èھ¤è§£مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ç§پمپ¯مپمپ®مپ“مپ¨م‚’ه…ˆç”ںمپ«ن¼مپˆم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ—مپ‹مپ—ه…ˆç”ںمپ¯ç§پمپ®مپم‚“مپھو°—وŒپمپ،مپھمپ©مپٹمپ‹مپ¾مپ„مپھمپڈم€پ
ç§پمپ®و‰‹م‚’مپ¤مپ‹م‚€مپ¨é«کمپ مپ‹مپ¨ه·®مپ—ن¸ٹمپ’م€پم‚¯مƒ©م‚¹مپ®مپ؟م‚“مپھم‚’見ه›مپ—م€پ
مپمپ—مپ¦هڈ«م‚“مپ مپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€Œمƒ†م‚¤مپ•م‚“مپ®و¶™مپ¯çœںçڈ مپ®و¶™مپ§مپ™م€‚م€چ
و°´م‚’و‰“مپ£مپںم‚ˆمپ†مپ«é™مپ‹مپ«مپھم‚‹مپ¨مپ¯م€پمپ“مپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚’言مپ†مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
çڑ†مپ®è¦–ç·ڑمپŒç§پمپ«é›†ن¸مپ™م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»مپھم‚“مپ¨م‚‚言مپˆمپ¬ه±…ه؟ƒهœ°مپ®و‚ھمپ•مپ®مپھمپ‹مپ§م€پ
م€Œمپ¯م‚„مپڈو™‚é–“مپŒوµپم‚Œمپ¦مپڈم‚Œمپںم‚‰مپ„مپ„مپ®مپ«مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپم‚“مپھمپ“مپ¨م‚’مپ¼م‚“م‚„م‚ٹمپ¨è€ƒمپˆمپ¦مپ„مپںمپ®مپ§مپ—مپںم€‚
م€Œمپ¾مپ‚م€په¤§ن½“مپ“م‚“مپھو„ںمپکمپ مپ£مپںمپ‹مپ—م‚‰م€‚م€چ
مپ،م‚‡مپ£مپ¨é•·مپ„話مپ مپ£مپںمپ‹مپھمپ¨مپ„مپ†é¢¨مپ«م€پChieمپŒè‚©م‚’مپ™مپڈم‚پم‚‹م€‚
م€Œمپڑمپ„مپ¶م‚“ç¾ژهŒ–مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ“م‚چمپŒمپ‚مپ£مپںمپ؟مپںمپ„مپ مپŒمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
TeitokuمپŒن¸چو؛€مپمپ†مپ«مپ¤مپ¶م‚„مپڈم€‚
م€Œمپ‚م‚‰م€پم‚‚مپ£مپ¨مپ‹مپ£مپ“م‚ˆمپڈمپ—مپ¦م‚‚م‚ˆمپ‹مپ£مپںم‚“مپ مپ‘مپ©مپھم€‚م€چ
م€Œمپ¯مپ„مپ¯مپ„م€پمپ®م‚چمپ‘مپ¯çµگو§‹م€پمپ”مپ،مپمپ†مپ•مپ¾م€‚م€چ
shioriمپŒمپ±م‚“مپ±م‚“مپ¨و‰‹م‚’هڈ©مپڈم€‚
م€Œمپ§م‚‚م€پمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®و°—وŒپمپ،مپ¯م‚ڈمپ‹مپ£مپںم‚ˆم€‚م€چ
UkiمپŒمپ—م‚“مپ؟م‚ٹمپ¨è¨€مپ†م€‚
م€Œمپمپ†مپ مپھم€په†·é™مپ«è€ƒمپˆم‚Œمپ°م€پمپ•مپ£مپچمپ®مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م€پمپ‚م‚Œمپ¯وœن¸‰وڑ®ه››مپ م€‚م€چ
DakiniمپŒمپ†م‚“مپ،مپڈم‚’ن؛¤مپˆمپ¦èھم‚‹م€‚
م€Œن½•م€پمپم‚Œï¼ںم€چ
مپ©مپ†م‚‚ن؟؛مپ¯مپمپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپ¯ه¼±مپ„م‚“مپ مپ¨مپ„مپ†مپمپ¶م‚ٹم‚’見مپ›مپھمپŒم‚‰CrystalمپŒèپمپڈم€‚
م€Œن¸ه›½مپ®هڈ¤مپ„مپ“مپ¨م‚ڈمپ–م‚ˆم€‚م€چ
ç§پمپŒمپ—م‚ƒمپ—م‚ƒم‚ٹه‡؛مپ¦è§£èھ¬مپ™م‚‹م€‚
م€Œمپمپ†م€پçŒ؟مپŒمپم€پمپ‚م‚‹وœمپˆمپ•مپŒè¶³م‚ٹمپھمپ„مپ£مپ¦é£¼مپ„ن¸»مپ«و–‡هڈ¥è¨€مپ†مپ®م€‚
م€€مپمپ—مپںم‚‰é£¼مپ„ن¸»مپ¯م€پن»ٹمپ¾مپ§وœن¸‰مپ¤م€پو™©ه››مپ¤م‚„مپ£مپ¦مپںمپˆمپ•م‚’مپم€پ
م€€ن»ٹو—¥مپ‹م‚‰مپ¯وœه››مپ¤م€پو™©ن¸‰مپ¤مپ«مپ™م‚‹مپمپ£مپ¦è¨€مپ£مپںمپ®م€‚
م€€çŒ؟مپ¯مپم‚Œم‚’èپمپ„مپ¦ه¤§ه–œمپ³مپ—مپںمپ£مپ¦مپ„مپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپھم‚“مپ§ه–œمپ¶م‚“مپ ï¼ںمپ‹م‚ڈم‚ٹمپ«و™©مپŒن¸‰مپ¤مپ«و¸›م‚‹مپ£مپ¦مپ®مپ«مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپ مپ‹م‚‰م€پمپمپ“مپŒçŒ؟çں¥وپµمپھمپ®مپم€پوœه››مپ¤çڈ¾ç‰©م‚’ç›®مپ®ه‰چمپ«ه‡؛مپ•م‚Œمپںم‚‰مپ†م‚Œمپ—مپ„م‚ڈمپ‘م‚ˆم€‚
م€€ه…ˆمپ®ن؛‹مپھم‚“مپ‹è€ƒمپˆمپ،م‚ƒمپ„مپھمپ„مپ®م€‚م€چ
م€Œمپ‚م€پمپھم‚‹م€‚م€چ
DakiniمپŒمپ“مپ“مپ¾مپ§مپ®è©±م‚’مپ¾مپ¨م‚پم‚‹م€‚
م€Œمپمپ†م€پمپ‚مپ®مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م€پمپ‚م‚Œمپ¯مپ„مپ¤مپ¾مپ§م‚‚مƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ«é™چم‚ٹç«‹مپ¦مپھمپ„مپ“مپ¨مپ§م€پ
م€€ن¸چه®‰مپŒé«کمپ¾م‚ٹمپ¤مپ¤مپ‚م‚‹و°‘é–“ن؛؛م‚’م€پن¸€و™‚çڑ„مپ«ه–œمپ°مپ›مپ¦مپ„م‚‹مپ مپ‘مپھم‚“مپ م€‚م€چ
م€Œوœ¬ه½“مپ®ه¤§مƒœم‚¹ç™»ه ´مپ¯م€پمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ مپ£مپ¦مپ“مپ¨م‚’éڑ مپ—مپ¦مپ¾مپ§ï¼ںم€چ
م€Œمپم‚“مپھمپ“مپ¨و°‘é–“ن؛؛مپŒçں¥مپ£مپںم‚‰م€پ絶وœ›مپ®ن½™م‚ٹم€پمƒ‘مƒ‹مƒƒم‚¯مپŒç”ںمپکم‚‹مپœم€‚م€چ
م€Œمپمپ†مپ‹مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپم‚Œمپ¾مپ§é»™مپ£مپ¦çڑ†مپ®è©±م‚’èپمپ„مپ¦مپ„مپںTeitokuمپŒم€په†چمپ³هڈ£م‚’é–‹مپ„مپںم€‚
م€Œن؟؛مپ¯ç·ڈç£مپ®م‚„م‚ٹو–¹مپ«مپ©مپ†مپ“مپ†è¨€مپ†مپ¤م‚‚م‚ٹمپ¯مپھمپ„م€‚
م€€و°‘é–“ن؛؛مپŒن¸چه®‰مپھو¯ژو—¥م‚’é€پمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚‚م‚ˆï½مپڈçں¥مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€€ه°‘مپ—مپ§م‚‚وکژم‚‹مپ„مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م‚’ه±ٹمپ‘مپ¦مپ‚مپ’مپںمپ„م€‚مپمپ®و°—وŒپمپ،مپ¯هچپهˆ†م‚ڈمپ‹م‚‹مپ•م€‚
م€€مپ مپŒوœ¬ه½“مپ«م€پمƒ‘م‚¤م‚ھمƒ‹م‚¢ï¼’مپ«ن¹—مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ؟م‚“مپھمپ®ن؛‹م‚’考مپˆم‚‹م‚“مپھم‚‰م€پ
م€€ه¤§ن؛‹مپھن؛‹مپ¯è‡ھ然مپ¨è¦‹مپˆمپ¦مپڈم‚‹مپ¨و€مپ†م‚“مپ م€‚
م€€مپم‚Œمپ¯م€پن؟؛مپںمپ،مپ®و‰‹مپ§م€پن¸€هˆ»م‚‚و—©مپڈه…ƒه‡¶م‚’هڈ–م‚ٹ除مپچم€پ
م€€مƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ®ه¹³ه’Œم‚’هڈ–م‚ٹوˆ»مپ™مپ“مپ¨مپ م€‚
م€€مپ¨مپ¯مپ„مپˆمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپمپ“مپ¾مپ§è¨€مپ£مپ¦م€پTeitokuمپ¯è¦–ç·ڑم‚’ن¸‹مپ«èگ½مپ¨مپ—مپںم€‚
م€Œمپ‚مپ®èµ¤مپ„è¼ھمپ®مƒھم‚³مپŒم€پمپ‹مپھم‚ڈمپھمپ‹مپ£مپں相و‰‹مپ م€‚
م€€ن»ٹه؛¦مپ®ن»•ن؛‹م€پç”ںمپچمپ¦ه¸°م‚Œمپھمپ„مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„م€‚
م€€مپم‚Œمپ§م‚‚مƒ»مƒ»مƒ»مپ مپŒمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مƒ»مƒ»مƒ»ن»²é–“مپ«و»مپ®è¦ڑو‚ںم‚’ه¼·è¦پمپ™م‚‹مپ®مپ‹م€پمپٹم‚Œمپ¯مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
Teitokuمپ«è؟·مپ„مپŒç”ںمپکمپںم€‚言葉مپŒمپ¨مپژم‚Œمپ¨مپژم‚Œمپ«مپھم‚‹م€‚
مپ مپŒم€پمپمپ®و™‚م€پTeitokuمپ®ه‰چمپ«مپڑمپ„مپ¨ن¸€و©è¸ڈمپ؟ه‡؛مپ—مپںç”·مپŒمپ„مپںم€‚
Dakiniمپ مپ£مپںم€‚
م€Œمƒ†م‚¤مپ•م‚“م€پç”ںمپچمپ¦ه¸°م‚چمپ†م€‚م€چ
IZم‚‚ن¸¦م‚“مپ م€‚
م€Œمپˆمپˆم€پç”ںمپچمپ¦ه¸°مپ£مپ¦م€پمپمپ—مپ¦وœ¬ه½“مپ®ه®´ن¼ڑم‚„م‚ٹمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚م€چ
CryatalمپŒé™½و°—مپ«è¨€مپ†م€‚
م€Œو»م‚“مپ م‚‰م€پé…’م€پ飲م‚پمپھمپ„مپœم€‚م€چ
م€Œمپ¯مپ¯م€پمپم‚Œمپ¯مپ„م‚„مپ مپھمپ‚م€‚م€چ
Sevenم€پDaimonم€پEchigoمƒ»مƒ»مƒ»و¬،م€…مپ«ه£°مپ¯ç¶ڑمپڈم€‚
م€Œمپ؟م‚“مپھمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
Teitokuمپ¯ه£°م‚’è©°مپ¾م‚‰مپ›م‚‹م€‚
م€Œم‚ˆمپ—م€په…¨éƒ¨çµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ‹م‚‰م€پمپ±ï½مپ£مپ¨و‰“مپ،ن¸ٹمپ’م‚„م‚چمپ†م€‚م€چ
م€Œمپ†م‚“م€پم‚„م‚چمپ†م€‚م€چ
م€Œمپٹمپ£مپ—م‚ƒï½م€پمپ„مپ£مپ،م‚‡مƒ‰و´¾و‰‹مپ«م‚„مپ£مپںم‚چمپ†مپ‹مپ„م€چ
é ¼م‚‚مپ—مپ„مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپںمپ،مپ®ه£°م€‚
مپ“مپ®مƒپمƒ¼مƒ م‚’ن½œمپ£مپ¦مپ»م‚“مپ¨مپ«è‰¯مپ‹مپ£مپںمƒ»مƒ»مƒ»م€‚
Teitokuمپ¯مپ“مپ؟ن¸ٹمپ’مپ¦مپچمپںه¤§هˆ‡مپھم‚‚مپ®م‚’مپ“مپ¼مپ•مپھمپ„م‚ˆمپ†م€په¤©ن؛•م‚’見ن¸ٹمپ’مپ¦هگ مپˆمپںم€‚
م€Œم‚ˆمپ—م€پمپ؟م‚“مپھم€پمپ„مپڈمپï¼پم€چ
ن»ٹه؛¦مپ“مپو±؛ç€م‚’مپ¤مپ‘مپ¦م‚„م‚‹م€‚مپ¾مپھمپکم‚ٹم‚’و±؛مپ—مپںمƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپںمپ،مپŒ
ن¸€ن؛؛م€پمپ¾مپںن¸€ن؛؛مپ¨م€پمƒمƒ“مƒ¼م‚’ه¾Œمپ«مپ—مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
ç§پم‚‚shioriمپںمپ،مپ¨ï¼”ن؛؛مپ§مƒپمƒ¼مƒ م‚’ن½œم‚ٹم€پم‚·مƒ†م‚£مپ¸مپ®è»¢é€پ装置مپ«é£›مپ³ن¹—م‚‹م€‚
مƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒ«مƒ¼مƒ مپ§مƒ‘مƒ¯مƒ¼é‡چ視مپ®مƒم‚°م‚’و€¥مپ„مپ§هڈ—مپ‘هڈ–م‚‹م€‚
装ه‚™م‚’Dه±و€§مپ«هˆ‡م‚ٹوڈ›مپˆم€پمپ„مپ–ه‡؛م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپںو™‚م€پ
shioriمپŒç§پمپ®و‰‹م‚’ه¼•مپ£مپ±مپ£مپںم€‚
م€Œمپ‚مپ›مپ£مپ،م‚ƒé§„ç›®مپ م‚ˆم€‚Mikiم€‚م€چ
م€Œمپˆï¼ںم€چ
م€Œمپ»م‚‰م€پمپ“م‚Œم€‚م€چ
見م‚‹مپ¨م‚‚مپ†ç‰‡و–¹مپ®و‰‹مپ«م€پوŒپمپ،مپچم‚Œمپھمپ„مپ»مپ©مپںمپڈمپ•م‚“مپ®م‚¹م‚±مƒ¼مƒ—مƒ‰مƒ¼مƒ«مپŒوڈ،م‚‰م‚Œمپ¦مپ„
م‚‹م€‚
م€Œèگ½مپ،م‚‹و‰€مپ«ç½®مپ„مپ¦مپٹمپڈمپ‹م‚‰èگ½مپ،م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»مپ م‚ˆمپم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦shioriمپ¯مƒ‰مƒ¼مƒ«م‚’ه·®مپ—ه‡؛مپ—مپںم€‚
مپ“مپ¼م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپھshioriمپ®ç¬‘é،”م‚’見مپ¦م€پ
ç§پمپ¯مپ„مپ¤م‚‚مپ®ه†·é™مپ•م‚’هڈ–م‚ٹوˆ»مپ—مپںم€‚
مپمپ®é€ڑم‚ٹمپ م€پو»م‚“مپ§مپ—مپ¾مپ†م‚ˆمپ†مپھ装ه‚™مپ§è،Œمپڈمپ‹م‚‰و»مپ¬مپ®مپ م€‚
ه¤§هˆ‡مپھمپ“مپ¨م‚’ç§پمپ¯ه؟کم‚Œمپ‹مپ‘مپ¦مپ„مپںم€‚
shioriمپ®مƒ‰مƒ¼مƒ«م‚’ه¤§هˆ‡مپ«هڈ—مپ‘هڈ–م‚‹م€‚
م€Œمپ‚م‚ٹمپŒمپ¨مپ†م€پshioriï¼پم€چ
م€Œç”ںمپچمپ¦ه¸°م‚چمپ†مپï¼پم€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€‚م€چ
shioriمپ®ç›®مپ®مپµمپ،مپ«و¶™مپŒن¸€ç²’م€په…‰مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
ç§پمپ¯م€پمپ•مپ£مپچمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®ç›®مپ®مپµمپ،مپ«م‚‚م€پهگŒمپکم‚‚مپ®مپŒه…‰مپ£مپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨م‚’و€مپ„ه‡؛مپ—مپںم€‚
مپ»م‚“مپ¨مپ®çœںçڈ مپ®و¶™مپ£مپ¦م€پمپ“مپ†مپ„مپ†م‚‚مپ®مپھم‚“مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹مپھم€‚
ç§پمپ¯و¼ 然مپ¨مپمپ†è€ƒمپˆمپھمپŒم‚‰م€پمƒ‰مƒ¼مƒ ه‹مپ®ه¤©ن؛•م‚’見ن¸ٹمپ’م‚‹م€‚
مپمپ—مپ¦èھ“مپ†م€‚
ه؟…مپڑç”ںمپچمپ¦م€پمپ“مپ“مپ«ه¸°م‚‹مپ¨م€‚
ه†چمپ³è¦–ç·ڑم‚’ه‰چو–¹مپ«وˆ»مپ™مپ¨م€پ
ï¼”ن؛؛مپ®ه†’é™؛者مپںمپ،مپ¯è؟·م‚ڈمپڑéپ؛è·،مپ¸مپ®è»¢é€پ装置مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦èµ°م‚ٹه‡؛مپ—مپںم€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€ç¬¬ه››è©±م€€çµ‚م‚ڈم‚ٹ
|
第ن؛”話م€€م€€مپمپ®و°—وŒپمپ،م‚’مپ“مپ¨مپ°مپ«
م€Œمپµï½مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ç§پمپ¯م€پمƒ”مƒƒم‚¯م‚’وŒپمپ£مپںن¸،و‰‹مپ«ç›®م‚’èگ½مپ¨مپ—م€پمپںم‚پوپ¯م‚’مپ¤مپ„مپںم€‚
وڈ،هٹ›مپŒé™گç•Œم‚’超مپˆمپںمپ®مپ م‚چمپ†م€‚
مƒ”مƒƒم‚¯م‚’ç½®مپچم€پمپ—مپ³م‚ŒمپŒو®‹م‚‹و‰‹مپ®مپ²م‚‰م‚’م‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨م‚‚مپ؟مپ»مپگمپ™م€‚
ShioriمپŒç§پمپ®و¨ھمپ«ç«‹مپ£مپ¦مپ¤مپ¶م‚„مپڈم‚ˆمپ†مپ«è¨€مپ†م€‚
م€Œمپھم‚“مپ¨مپ‹ç‰‡مپ¥مپ„مپںمپم€‚و‰‹ه¼·مپ‹مپ£مپںم‚ˆم€‚م€چ
UkiمپŒم€پو‰‹ه…ƒمپ®مƒ¬مƒ¼مƒ€مƒ¼م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپ‹م‚‰è¨€مپ†م€‚
م€Œم‚‚مپ†م€پمپ„مپھمپ„مپھم€‚م€چ
م€Œن¸€و™‚مپ¯ه…¨و»…مپ™م‚‹مپ‹مپ¨و€مپ£مپںمپŒم€پمƒ‰مƒ¼مƒ«مپ®مپٹمپ‹مپ’مپ§مپھم‚“مپ¨مپ‹وŒپمپ،مپ“مپںمپˆمپںمپھم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ†مپ¨Dakiniمپ¯ه‚چم‚‰مپ®ه²©م‚’وŒ‡مپ•مپ—مپںم€‚
م€Œمپ¨مپ«مپ‹مپڈن¸€وœچمپ—م‚ˆمپ†م€‚م€چ
çڑ†م€پو€مپ„و€مپ„مپ®ه§؟ه‹¢مپ§ه²©مپ«è…°وژ›مپ‘م‚‹م€‚
مپ„م‚ˆمپ„م‚ˆوœ€ه¾Œمپ®و‰‰مپ®ه‰چمپ«و¥مپںم€‚مپ“مپ“م‚’éپژمپژم‚Œمپ°م€پمپ‚مپ¨مپ¯DFمپŒه¾…مپ¤مپ®مپ؟مپ م€‚
ه¤§ه؛ƒé–“مپ®éڑ…مپ§م€پç§پمپںمپ،مپ¯و®‹مپ£مپںè–¬مپ®و•°م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ‚مپ£مپںم€‚
م€Œمپ مپ„مپکم‚‡مپ†مپ¶مپ؟مپںمپ„م€‚مƒ‰مƒ¼مƒ«م‚‚مپ¾مپ مپ„مپ£مپ±مپ„و®‹مپ£مپ¦م‚‹م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ„مپ¤مپ§م‚‚飛مپ³éپ“ه…·مپŒه‡؛مپ›م‚‹م‚ˆمپ†م€پ用و„ڈمپ—مپ¨مپ‘م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ†م‚“م€‚م€چ
Dه±و€§مپ®èµ¤مپ„مƒڈمƒ³مƒ‰م‚¬مƒ³م‚’مƒ›مƒ«م‚¹م‚؟مƒ¼مپ‹م‚‰هڈ–م‚ٹه‡؛مپ—م€پ点و¤œمپ™م‚‹م€‚
éٹƒم‚’وŒپمپ¤و‰‹مپŒمپ‹مپ™مپ‹مپ«éœ‡مپˆمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپŒم‚ڈمپ‹م‚‹م€‚
مپ—مپ³م‚ŒمپŒو®‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚
ç·ٹه¼µمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ م€‚
ن¼ڑ話مپ«م‚‚ن½™è£•مپŒمپھمپ„م€‚
مپ§م‚‚م€پم‚‚مپ†ه¾Œوˆ»م‚ٹمپ¯مپ§مپچمپھمپ„م€‚
مپم‚“مپھو™‚م€پShioriمپŒçھپ然مپ“م‚“مپھمپ“مپ¨م‚’言مپ„ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œمپمپˆم€پمپ؟م‚“مپھمپ¯مپ“م‚ŒمپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپںم‚‰مپ©مپ†مپ™م‚‹مپ¤م‚‚م‚ٹمپھمپ®ï¼ںم€چ
مپˆم€پمپ¨مپ„مپ†è،¨وƒ…مپ§çڑ†مپŒShioriم‚’見م‚‹م€‚
م€Œمپ‚مپ®مپم€پمپ“مپ®ن»•ن؛‹مپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپ¦م€پمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپŒه¹³ه’Œمپ«مپھمپ£مپںم‚‰م€پ
م€€ç§پمپںمپ،مپ£مپ¦م€په¤±و¥مپ™م‚‹مپ®مپ‹مپھï½مپ£مپ¦و€مپ£مپ¦مپ•م€‚م€چ
م€Œمپم‚“مپھمپ“مپ¨م€پ考مپˆمپ¦مپ؟م‚‚مپ—مپھمپ‹مپ£مپںمپھم€‚م€چ
DakiniمپŒç›¾مپ«مپ¤مپ„مپںه‚·م‚’مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ—مپھمپŒم‚‰è¨€مپ†م€‚ç§پم‚‚ç¶ڑمپ‘مپںم€‚
م€Œمپ†م‚“م€پمپ»م‚“مپ¨مپ«م€‚م€چ
م€Œمپ¯مپ¯م€پمپ»م‚“مپ¨مپ مپم€‚مپ“م‚Œçµ‚م‚ڈمپ£مپںم‚‰ن؟؛م€پمپ©مپ†مپ—م‚ˆمپ†مپ‹مپھمپ‚م€‚م€چ
UkiمپŒç¬‘مپ£مپ¦è¨€مپ†م€‚مپ؟مپھمپ®ç·ٹه¼µمپŒمپ»مپ©م‚ˆمپڈ解مپ‘مپ¦مپ„مپڈم€‚
DakiniمپŒè¨€مپ†م€‚
م€Œه®ںمپ¯مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ن½•م€…ï¼ںمپ¨مپ؟م‚“مپھمپŒDakiniمپ®ه‘¨م‚ٹمپ«é›†مپ¾م‚‹م€‚
çڑ†مپ®é،”م‚’ن¸€é€ڑم‚ٹ見مپ¦مپ‹م‚‰م€پDakiniمپ¯م‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨è‡ھهˆ†مپ®مƒ—مƒ©مƒ³م‚’話مپ—ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œç„،ن؛‹مپ“مپ®ن»•ن؛‹مپŒçµ‚م‚ڈم‚Œمپ°م€پمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ«مپ؟م‚“مپھمپŒé™چم‚ٹç«‹مپ،م€پ
م€€ه¹³ه’Œمپھو™‚ن»£مپŒم‚„مپ£مپ¦مپڈم‚‹م€‚مپ؟م‚“مپھمپ¯مپ“مپ®وکںمپ§و–°مپ—مپ„ç”ںو´»م‚’ه§‹م‚پم‚‹م€‚
م€€مپمپ†مپ—مپںم‚‰ه¨¯و¥½و–½è¨مپ«م‚‚مپچمپ£مپ¨éœ€è¦پمپŒمپ§مپ¦مپڈم‚‹مپ م‚چمپ†م€‚
م€€مپ§م€پن؟؛مپںمپ،مپ«مپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨مپھم‚“مپ مپŒمƒ»مƒ»مƒ»
م€€وک”م€پهœ°çگƒمپ«مƒ‡م‚£م‚؛مƒ‹مƒ¼مƒ©مƒ³مƒ‰مپ£مپ¦مپ„مپ†ç·ڈهگˆه¨¯و¥½و–½è¨مپŒمپ‚مپ£مپںمپ®م€پ
م€€çں¥مپ£مپ¦م‚‹مپ‹ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚م€پو´هڈ²مپ®وژˆو¥مپ§ç؟’مپ£مپںم‚ˆم€‚م€چمپ¨Shioriم€‚
م€Œمپ†م‚“م€پمپںمپ—مپ‹م€پمپ„م‚چم‚“مپھم‚¢مƒˆمƒ©م‚¯م‚·مƒ§مƒ³م‚„و–½è¨مپŒمپ‚مپ£مپ¦م€پ
م€€مپٹه®¢مپ•م‚“مپ¯م‚ڈمپڈم‚ڈمپڈمپ©مپچمپ©مپچمپ®ن½“験مپŒمپ§مپچم‚‹مپ£مپ¦مپ„مپ†مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ç§پم‚‚ه¾Œم‚’継مپگم€‚
م€Œمپمپ†م€پمپ‚م‚Œمپ«è؟‘مپ„مپ“مپ¨م‚’مپ“مپ®مƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ§م‚„مپ£مپ¦مپ؟م‚ˆمپ†مپ‹مپ¨و€مپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚“مپ م€‚م€چ
م€Œمپ¯مپ¯مپ‚مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œه®¢مپ¯مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼مپ«مپھمپ£مپ¦مپ“مپ®و–½è¨مپ®ن¸م‚’ه†’é™؛مپ™م‚‹م€‚
م€€و¬،م€…مپ¨ه®¢م‚’襲مپ†م‚¨مƒچمƒںمƒ¼مپںمپ،م€‚
م€€و¦ه™¨م‚’و‰‹مپ«مپ¨مپ£مپ¦م‚¨مƒچمƒںمƒ¼م‚’مپھمپژو‰•مپ„مپھمپŒم‚‰م€پ
م€€è»¢é€پ装置مپ«ن¹—مپ£مپ¦éƒ¨ه±‹مپ‹م‚‰éƒ¨ه±‹مپ¸مپ¨مپ¤مپچ進مپ؟م€پ
م€€وœ€çµ‚مƒœم‚¹م‚’ه€’مپ›مپ°مپمپ®م‚¹مƒ†مƒ¼م‚¸مپ¯مپٹمپ—مپ¾مپ„مپ£مپ¦مپ„مپ†مپ®مپ¯مپ©مپ†مپ ï¼ںم€چ
م€Œمپھم‚‹ï½م€پ
م€€م‚ڈمپںمپ—مپںمپ،مپŒن»ٹم‚„مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ®مپٹن»•ن؛‹م‚’
م€€م‚·مƒںمƒ¥مƒ¬مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ن½“験مپ•مپ›م‚ˆمپ†مپ£مپ¦مپ„مپ†م‚ڈمپ‘مپم€‚م€چ
ShioriمپŒمپ½م‚“مپ¨و‰‹م‚’و‰“مپ¤م€‚
م€Œمپمپ†م€پمپ—مپ‹م‚‚م‚¨مƒچمƒںمƒ¼مپ¯مپ™مپ¹مپ¦وœ¬ç‰©مپ‹م‚‰مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’وژ،هڈ–م€پ
م€€ç«‹ن½“مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯م‚؟مƒ¼م‚’ن½؟مپ£مپ¦وٹ•ه½±مپ™م‚‹م€‚مƒھم‚¢مƒ«مپ مپœï½م€‚م€چ
م€Œمپ§م‚‚مپم‚Œمپ£مپ¦م€پو–½è¨ن½œم‚‹مپ®مپ«م€پéڑڈهˆ†مپٹ金مپ‹مپ‹م‚‹م‚“مپکم‚ƒمپھمپ„مپ®ï¼ںم€چ
م‚‚مپ£مپ¨م‚‚مپھè³ھه•ڈمپ م€‚
م€Œé‡‘مپھم‚‰مپ‘مپ£مپ“مپ†è“„مپˆمپŒمپ‚م‚‹م‚“مپ م€‚ن»ٹمپ¾مپ§مپ«éڑڈهˆ†ن»•ن؛‹م‚‚مپ“مپھمپ—مپ¦مپچمپںمپ—مپھم€‚م€چ
م€Œمپµï½م‚“م€‚مپ„مپ„مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„م€پمپم‚Œم€‚م€چ
مپ“م‚Œمپ¯ه؟ƒمپ‹م‚‰و„ںه؟ƒمپ—مپںç§پمپ®مپ›م‚ٹمپµم€‚مپ،م‚ƒم‚“مپ¨è²¯é‡‘مپ—مپ¦مپںم‚“مپ م€‚
م€Œمپٹم‚Œم€پمپمپ®è¨ˆç”»م€پن¹—مپ£مپ¦م‚‚مپ„مپ„مپ‹مپھï¼ںم€چ
UkiمپŒè†م‚’ن¹—م‚ٹه‡؛مپ—مپ¦è¨€مپ†م€‚
م€Œمپ„مپ„مپ•م€پمپœمپ²ن¹—مپ£مپ¦مپڈم‚Œم‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپکم‚ƒمپ‚م€پن؟؛مپ®è²¯é‡‘م‚‚ن½؟مپ£مپ¦مپڈم‚Œم‚ˆم€‚
م€€مپم‚“مپ§و€مپ„هˆ‡م‚ٹè±ھه‹¢مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’و§‹ç¯‰مپ™م‚‹م‚“مپ م€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ¯مپ¯م€پمپکم‚ƒمپ‚ç§پمپ¯وژ¥ه®¢و¥مپ§م‚‚مپ•مپ›مپ¦م‚‚م‚‰مپٹمپ†مپ‹مپھï½م€‚م€چمپ¨Shioriم€‚
م€ŒMikiمپ¯مپ©مپ†مپ ï¼ںم€چ
DakiniمپŒمپ،م‚‰م‚ٹمپ¨ç§پمپ«è¦–ç·ڑم‚’م‚ˆمپ“مپ™م€‚
م€Œç§پï¼ںمƒ»مƒ»مƒ»ç§پمپ¯ن»–مپ«م‚„م‚ٹمپںمپ„مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپمپ†مپھمپ®ï¼ںمپ¨مپ„مپ†é،”م‚’مپ—مپ¦م€پShioriمپŒç§پمپ®é،”م‚’覗مپچè¾¼م‚€م€‚Ukiم‚‚
م€ŒMikiمپ«م‚„م‚ٹمپںمپ„مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ£مپ¦م€پهˆم‚پمپ¦èپمپ„مپںمپھم€‚م€چ
مپ¨و„ڈه¤–مپمپ†مپھé،”م€‚
م€Œن؟؛م‚‚مپ م€‚م‚ˆمپ‹مپ£مپںم‚‰èپمپ‹مپ›مپ¦مپڈم‚Œم‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ†م‚“مپ†م‚“م€پç§پم‚‚èپمپچمپںمپ„م€‚م€چ
ç¶ڑمپ‘مپ–مپ¾مپ«è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ†م€‚
مپˆمپ¨مƒ»مƒ»مƒ»مپ¨م€پمپ—مپ°م‚‰مپڈ言مپ„م‚ˆمپ©م‚“مپ§مپ‹م‚‰ç§پمپ¯è©±مپ—ه‡؛مپ—مپںم€‚
م€Œمپ‚مپ®مپم€پن»ٹمپ¾مپ§مپ‚مپ£مپںمپ“مپ¨م‚’è¨ک録مپ«و®‹مپ—مپ¦مپٹمپچمپںمپ„مپھمپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œè¨ک録ï¼ںç«‹ن½“مƒ“مƒ‡م‚ھمپ§ï¼ںم€چ
مپم‚Œمپھم‚‰وŒپمپ£مپ¦م‚‹م‚ˆم€پمپ¨ShioriمپŒو‰‹مپ®مپ²م‚‰مپ«هڈژمپ¾م‚‹ه°ڈمپ•مپھ装置م‚’هڈ–م‚ٹه‡؛مپ—م€پ
مپ¤مپ„مپ§مپ«مپ±مپ،م‚ٹمپ¨ç§پمپ®ç«‹ن½“é™و¢ç”»م‚’ه†™مپ™م€‚
م€Œمپ†مپ†م‚“م€پهڈ¤مپ„و‰‹و³•مپھم‚“مپ مپ‘مپ©م€پو–‡ه—مپ مپ‘مپ§مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œو—¥è¨کمپ؟مپںمپ„مپھم‚‚م‚“ï¼ںم€چ
م€Œمپ†م‚“م€پç§پم€پمپ“مپ®مƒپمƒ¼مƒ مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„م‚چم‚“مپھن؛‹م‚’ه¦م‚“مپ مپ—م€پ
م€€و¥½مپ—مپ„وƒ³مپ„ه‡؛م‚‚مپ„مپ£مپ±مپ„مپ§مپچمپںم€‚مپ مپ‹م‚‰ه؟کم‚Œمپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«م€پ
م€€è‡ھهˆ†مپ®و°—وŒپمپ،م‚’و–‡ه—مپ«مپ—مپ¦و®‹مپ—مپ¦مپٹمپچمپںمپ„مپ®م€‚م€چ
م€Œمپµï½م‚“م€پمپمپ†مپ‹م€پMikiمپھم‚‰مپچمپ£مپ¨مپ†مپ¾مپڈو›¸مپ‘م‚‹م‚ˆم€‚م€چUkiمپŒهٹ±مپ¾مپ—مپ¦مپڈم‚Œم‚‹م€‚
م€Œمپ§مپچمپںم‚‰è¦‹مپ›مپ¦مپم€‚Mikiï¼پم€چ
م€Œمپ†م‚“م€‚Shioriمپ«مپ¯ن¸€ç•ھمپ«è¦‹مپ›م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»مپ‹مپھï¼ںم€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†مپ‹م€‚م€چ
مپ¨DakiniمپŒمپ¤مپ¶م‚„مپڈم€‚
م€Œمپ©مپ†مپ—مپںمپ®ï¼ںم€چ
ShioriمپŒم€پمپ†مپ¤م‚€مپ„مپںDakiniمپ®é،”م‚’ن¸‹مپ‹م‚‰è¦‹ن¸ٹمپ’م‚‹م€‚
م€Œمپ„م‚„م€پمپھم‚“مپ§م‚‚مپھمپ„م€پمپم‚Œم‚ˆم‚ٹم€پمپم‚چمپم‚چè،Œمپ“مپ†م€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ£مپ¦DakiniمپŒç«‹مپ،ن¸ٹمپŒم‚چمپ†مپ¨مپ—مپںم€‚
ShioriمپŒمپم‚Œم‚’و¢م‚پم‚‹م€‚
م€Œمپ،م‚‡مپ£مپ¨ه¾…مپ£مپ¦م€‚م€چ
مپھم‚“مپ مپھم‚“مپ مپ¨UkiمپŒوŒ¯م‚ٹè؟”م‚‹م€‚
م€Œè،Œمپڈه‰چمپ«م€پمپ،م‚‡مپ£مپ¨ç§پمپ®è©±èپمپ„مپ¦مپ»مپ—مپ„مپ®م€‚مپ„مپ„مپ‹مپھï¼ںم€چ
م€Œم‚“ï¼ںم€چ
مپ¨مپ„مپ¶مپ‹مپ—مپŒم‚ٹمپھمپŒم‚‰م‚‚DakiniمپŒè…°م‚’مپٹم‚چمپ™م€‚
م€Œمپˆمپ¨مƒ»مƒ»مƒ»مپ‚مپ®مپم€پç§پمپŒمپ¾مپ ه°ڈه¦و ،مپ®مپ“م‚چمپ®è©±مپھم‚“مپ مپ‘مپ©مپم€‚م€چ
م€€ه°ڈه¦و ،مپ¨مپ„مپ£مپ¦م‚‚م€په½“然مƒڈمƒ³م‚؟مƒ¼é¤ٹوˆگه°‚é–€ه¦و ،مپ مپ£مپںم‚“مپ مپ‘مپ©م€پ
مƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ®ç”·مپ®هگمپ¨ن»²è‰¯مپڈمپھمپ£مپںمپ®مپم€‚
مپ،مپ£مپ،م‚ƒمپ„ç”·مپ®هگمپ مپ£مپںمپ‘مپ©م€پç§پم‚‚مƒپمƒ“مپ مپ£مپںمپ‹م‚‰مپ•م€‚
مپ§م€په½“و™‚مپ¯م€پمپ؟م‚“مپھم‚‚م‚ڈمپ‹م‚‹مپ¨و€مپ†مپ‘مپ©م€پ
مپ¾مپ ن»ٹمپ»مپ©مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ن¸€èˆ¬مپ®çگ†è§£مپŒمپھمپ‹مپ£مپںو™‚ن»£مپ مپ‹م‚‰م€پ
وœ€هˆمپ¯ç§پم‚‚م€پمپ»م‚“مپ¨مپ«مپ„مپ„مپ®مپ‹مپھï¼ں
مپ“مپ®هگمپ¨مپ¤مپچمپ‚مپ£مپ¦مپ„مپ„مپ®مپ‹مپھمپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»
مپ§م‚‚م‚ˆمپڈم‚¯مƒ©م‚¹مپ®ن»•ن؛‹مپ¨مپ‹و‰‹ن¼مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپںمپ®م€‚
مپم‚Œمپ§è‡ھ然مپ«م€پو”¾èھ²ه¾Œمپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«éپٹمپ¶م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپ®مپم€‚
مپم‚Œم‚‚ه¥³مپ®هگمپŒمپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپھéپٹمپ³مپ«مپ¤مپچمپ‚مپ£مپ¦م‚‚م‚‰مپ£مپ¦مپںمپ®م€‚
縄跳مپ³مپ¨مپ‹مپ•م€‚
مپ‚م‚‹و™‚م€پن؛Œن؛؛مپ§مپم€پç”؛م‚’ن¸€ç·’مپ«و©مپ„مپ¦مپںم‚‰م€پ
هگŒç´ڑç”ںمپ®ç”·مپ®هگمپںمپ،مپ«ه‡؛ن¼ڑمپ£مپ،م‚ƒمپ£مپ¦مپم€‚
مپ§م€پمپمپ„مپ¤م‚‰مپŒه½¼مپ®مپ“مپ¨م‚’مپ‹م‚‰مپ‹مپ†م‚“مپ م€‚
م‚„ï½مپ„م€پمپٹه‰چم€پمƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ®هگمپ¨مپ¤مپچمپ‚مپ£مپ¦م‚“مپ®مپ‹مپ£مپ¦م€‚
ç§پم€پمپم‚Œèپمپ„مپںمپ¨مپچم€پمپ™مپ”مپڈم‚·مƒ§مƒƒم‚¯مپ مپ£مپںم€‚
çڈ¾ه®ںمپ¯م‚„مپ£مپ±م‚ٹمپمپ†مپھم‚“مپ مپھمپ£مپ¦م€‚
مپچمپ£مپ¨ه½¼مپ¯ç§پمپ‹م‚‰é›¢م‚Œمپ¦مپ„مپڈم€‚
و¥½مپ—مپ‹مپ£مپںمپ‘مپ©م€پمپم‚Œم‚‚ن»ٹو—¥مپ§çµ‚م‚ڈم‚ٹمپھم‚“مپ مپ£مپ¦م€‚
مپ§م‚‚م€پمپمپ†مپکم‚ƒمپھمپ‹مپ£مپںم€‚مپمپ†مپکم‚ƒمپھمپ‹مپ£مپںمپ®م€‚
م€€Shioriمپ¯مپ“مپ“مپ¾مپ§è¨€مپ†مپ¨م€پمپ“مپ¨مپ°م‚’è©°مپ¾م‚‰مپ›مپںم€‚
مپ—مپ°م‚‰مپڈو²ˆé»™مپŒوµپم‚Œم‚‹م€‚
ç§پمپ¯Shioriمپ®و¶™م‚’مپمپ£مپ¨مپµمپڈم€‚
مپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚
ه°ڈمپ•مپڈ言مپ†مپ¨Shioriمپ¯è©±مپ®ç¶ڑمپچم‚’ه§‹م‚پمپںم€‚
م€€ه½¼مپ¯ç”·مپ®هگمپںمپ،مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦مپ“مپ†è¨€مپ£مپںمپ®م€‚
م€ژه¥½مپچمپ مپ‹م‚‰مپ¤مپچمپ‚مپ£مپ¦م‚“مپ م€‚و–‡هڈ¥مپ‚م‚‹مپ‹ï¼ںم€ڈمپ£مپ¦م€‚
مپمپ—مپ¦مپم€پç§پمپ®و‰‹م‚’وڈ،م‚‹مپ¨م€پ
ç”·مپ®هگمپںمپ،مپ®ه‰چم‚’مپ™مپںمپ™مپںمپ£مپ¦م€پé€ڑم‚ٹéپژمپژمپ¦مپ„مپ£مپںمپ®م€‚
مپ‚مپ„مپ¤م‚‰مپ‚مپ£مپ‘مپ«مپ¨م‚‰م‚Œمپ¦ç§پمپںمپ،م‚’見مپ¦مپںم€‚هڈ£مپ½مپ‹م‚“مپ¨é–‹مپ‘مپ¦م€‚
ç§پè‡ھè؛«م‚‚مپمپ†مپ مپ£مپںمپ¨و€مپ†م€‚
مپ§م‚‚م€پمپ‚مپ®مپ¨مپچمپ®و‰‹مپ®مپ²م‚‰م€پن»ٹمپ§م‚‚è¦ڑمپˆمپ¦م‚‹م€‚
مپ™مپ”مپڈهٹ›ه¼·مپ‹مپ£مپںم€‚
مپمپ†è¨€مپ†مپ¨Shioriمپ¯è‡ھهˆ†مپ®و‰‹مپ®مپ²م‚‰م‚’مپ»مپ£مپ؛مپںمپ«مپڈمپ£مپ¤مپ‘مپںم€‚
م€Œçµگه±€مپمپ®ç”·مپ®هگمپ¯م€پ1ه¹´مپڈم‚‰مپ„مپ—مپںم‚‰مپم€‚転و ،مپ—مپ¦مپ„مپ£مپ،م‚ƒمپ£مپںم€‚م€چ
م€Œمپµï½م‚“مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپ مپ‹م‚‰م€پمپ“م‚Œمپ§مپ“مپ®è©±مپ¯مپٹمپ—مپ¾مپ„م€‚èپمپ„مپ¦مپڈم‚Œمپ¦مپ©مپ†م‚‚مپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚م€چ
م€Œمپ‚مپ‚مƒ»مƒ»مƒ»مپ„مپ„話مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹م€‚م€چ
UkiمپŒمپ—مپ؟مپکمپ؟مپ¨è¨€مپ†م€‚
م€Œمپ†م‚“م€پمپ™مپ”مپڈمپ„مپ„話مپ مپ£مپںم‚ˆم€‚م€چ
ç§پم‚‚مپ†مپھمپڑمپ„مپںم€‚
م€Œç§پمپŒè¨€مپ„مپںمپ‹مپ£مپںمپ“مپ¨م€پم‚ڈمپ‹مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپںï¼ںم€چ
ShioriمپŒDakiniم‚’見مپ¦è¨€مپ†م€‚
م€Œمپ‚مپ‚م€پم‚ڈمپ‹مپ£مپںم‚ˆم€‚م€چ
م€Œم‚ˆمپ‹مپ£مپںم€پمپکم‚ƒم€‚م€چ
مپمپ†è¨€مپ†مپ¨Shioriمپ¯ç«‹مپ،ن¸ٹمپŒم‚ٹم€پ
Ukiمپ®و‰‹م‚’هڈ–م‚‹مپ¨م€پ逆هپ´مپ«مپ‚م‚‹ه²©ه ´مپ¾مپ§ه¼·ه¼•مپ«ه¼•مپ£مپ±مپ£مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
م€Œمپھمپھمƒ»مپھم‚“مپ م‚ˆمپ„مپچمپھم‚ٹï¼ںم€چUkiمپŒو…Œمپ¦م‚‹م€‚
م€Œمپ°مپ‹مپم€پو°—م‚’مپچمپ‹مپ›مپ¦مپ‚مپ’مپھمپ•مپ„م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپˆم€پن½•مپ®ï¼ںم€چ
م€Œمپ„مپ„مپ‹م‚‰مپ“مپ“مپ«ه؛§م‚‹ï¼پم€چ
م€Œمپ¯م€پمپ¯مپ„مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ç§پمپ¯م€پمپ„مپچمپھم‚ٹDakiniمپ¨ن؛Œن؛؛مپچم‚ٹمپ«مپھمپ£مپںمپ“مپ¨مپ«و°—مپŒمپ¤مپ„مپںم€‚
مپ‚م‚ڈمپ¦مپ¦ه½¼مپ‹م‚‰ç›®م‚’مپم‚‰مپ™م€‚
م€Œمپˆمپ¨مƒ»مƒ»مƒ»مپ‚مپ®مƒ»مƒ»مƒ»Shioriمپ©مپ†مپ—مپ،م‚ƒمپ£مپںمپ®مپ‹مپھï¼ںم€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ•مپ£مپچمپ®Shioriمپ®è©±م€پمپ‚م‚Œمپ¯ن؟؛مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦è¨€مپ£مپ¦مپںم‚“مپ م‚ˆمپھم€‚م€چ
م€Œمپˆï¼ںم€چ
م€ŒمپŒم‚“مپ°م‚Œمپ£مپ¦م€‚ه¤§ن؛‹مپھو™‚مپ«ه¤§ن؛‹مپھمپ“مپ¨مپ°م‚’م€پمپ،م‚ƒم‚“مپ¨è¨€مپˆم‚‹ç”·مپ«مپھم‚Œمپ£مپ¦م€‚م€چ
ه½¼مپ®وŒ‡مپŒç§پمپ®مپٹمپ§مپ“مپ«ن¼¸مپ³م‚‹م€‚مپمپ—مپ¦مپمپ£مپ¨ç§پمپ®é،”مپ®هگ‘مپچم‚’ه¤‰مپˆم‚‹م€‚
م€Œمپ‚مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ه½¼مپ®è¦–ç·ڑمپŒç§پم‚’و£é¢مپ‹م‚‰وچ‰مپˆمپ¦مپ„مپںم€‚
م€ŒMikiم€پمپ“م‚ŒمپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپںم‚‰مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«وڑ®م‚‰مپ•مپھمپ„مپ‹ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مƒ»مƒ»مƒ»مپ†م‚“م€پمپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚مپ§م‚‚م€‚م€چ
م€Œè؟·وƒ‘مپ‹م‚‚çں¥م‚Œمپھمپ„م€پمپ§م‚‚مپٹم‚Œمپ¯م€پMikiمپ®مپ“مپ¨مپŒه¥½مپچمپ م€‚م€چ
مپ¨مپ£مپ•مپ«ن½•مپ¨è¨€مپˆمپ°مپ„مپ„مپ®مپ‹م‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپ‹مپ£مپںم€‚
مپم‚Œمپ§م‚‚م€پو°—مپŒمپ¤مپڈمپ¨ç§پمپ®ن¸،و‰‹مپ¯مپمپ£مپ¨ه½¼مپ®و‰‹م‚’هŒ…مپ؟è¾¼م‚“مپ§مپ„مپںم€‚
مپ”مپ¤مپ”مپ¤مپ¨مپ—مپںه½¼مپ®وŒ‡م‚’م€پن¸€وœ¬ن¸€وœ¬مپ»مپگمپ—مپ¦م‚†مپڈم€‚
مپم‚Œمپ‹م‚‰م€پم‚†مپ£مپڈم‚ٹمپ¨è¨€è‘‰مپŒه‡؛مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œمپ†م‚“مƒ»مƒ»مƒ»ç§پم‚‚Dakiniمپ®مپ“مپ¨م€په¥½مپچمپ م‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپمپ†مپ‹م€‚م€چ
م€Œمپ§م‚‚م€پمپ،م‚‡مپ£مپ¨ه¾…مپ£مپ¦م€پ
م€€ç§پم‚‚مپم€پ
م€€ه¤§ن؛‹مپھو™‚مپ«ه¤§ن؛‹مپھمپ“مپ¨م‚’مپ،م‚ƒم‚“مپ¨è¨€م‚ڈمپھمپچم‚ƒمپ„مپ‘مپھمپ„مپ®م€‚م€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپھم‚“مپ®مپ“مپ¨مپ ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مپ®مپم€پç§پم€پمپ“مپ®مƒپمƒ¼مƒ مپ«ه…¥مپ£مپ¦م€پمپ„م‚چم‚“مپھن»²é–“مپ¨çں¥م‚ٹمپ‚مپˆمپ¦م€پ
م€€مپ»م‚“مپ¨مپ«مپ†م‚Œمپ—مپ‹مپ£مپںم€‚ه¹¸مپ›مپ مپ£مپںم€‚
م€€مپ‚مپھمپںمپ¨م‚‚مپ„مپ£مپ—م‚‡مپ«ن»•ن؛‹مپ§مپچمپںمپ—مƒ»مƒ»مƒ»
م€€Shioriمپ¨مپ¯ن»¥ه‰چمپ«م‚‚ه¢—مپ—مپ¦م€پمپ†م‚“مپ¨ن»²è‰¯مپڈمپھم‚Œمپںم€‚
م€€و‰‹è،“مپ®مپ“مپ¨م‚‚ن»ٹمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ¯مپ»م‚“مپ¨مپ«مپ„مپ„وƒ³مپ„ه‡؛مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€ŒMikiمƒ»مƒ»مƒ»م€چ
ç§پمپ¯مپھم‚‹مپ¹مپڈمپ•م‚‰م‚ٹمپ¨è¨€مپ£مپںم€‚
م€Œم‚‚مپ†é•·مپڈمپ¯ç”ںمپچم‚‰م‚Œمپھمپ„مپ®م€‚م€چ
م€Œï¼پم€چ
م€Œمپ”م‚پم‚“مپم€‚م€چ
م€Œمپ”م‚پم‚“مپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»مپھم‚“مپ§ï¼ںمپھم‚“مپ§مپ‚م‚„مپ¾م‚‹م‚“مپ ï¼ں
م€€مپھم‚“مپ§ç”ںمپچم‚‰م‚Œمپھمپ„مپھم‚“مپ¦è¨€مپ†م‚“مپ م‚ˆï¼ںم€چ
م€Œم‚“م€پمپںمپ مپ®ه¯؟ه‘½مƒ»مƒ»مƒ»مپ‹مپھï¼ںم€چ
مپ“م‚Œم‚‚مپ•م‚‰م‚ٹمپ¨è¨€مپ£مپںمپ¤م‚‚م‚ٹمپ مپ£مپںمپŒم€په°‘مپ—ه£°مپŒéœ‡مپˆمپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںمپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپھمپ„م€‚
م€Œه¯؟ه‘½مپ£مپ¦مƒ»مƒ»مƒ»مپمپ†è¨€مپˆمپ°ن»¥ه‰چمپ©مپ“مپ‹مپ§èپمپ„مپںمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹م€‚
م€€مƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ®ه¯؟ه‘½مپ¯ه€‹ن½“ه·®مپŒو؟€مپ—مپ„مپ¨م€‚مپ§م‚‚م€پMikiمپŒï¼ںمپ¾مپ•مپ‹م€‚م€چ
مپمپ†م€پمƒ‹مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³مپ¯ه‰µم‚‰م‚Œمپںç”ںه‘½ن½“مپ مپ‘مپ‚مپ£مپ¦م€پ
مƒ’مƒ¥مƒ¼مƒمƒ³م‚ˆم‚ٹم‚‚وˆگé•·مپŒé€ںمپڈم€پمپ¾مپںم€پ特ه®ڑمپ®èƒ½هٹ›مپ«ه„ھم‚Œمپ¦مپ„مپںم‚ٹمپ™م‚‹م€‚
مپمپ®ن»£ه„ںمپھمپ®مپ‹م€پن¸مپ«مپ¯مپچم‚ڈم‚پمپ¦çںه‘½مپھ者م‚‚مپ„م‚‹م€‚
مپمپ®ن¸مپ®ن¸€ن؛؛مپŒمپںمپ¾مپںمپ¾ç§پمپ مپ£مپںمپ مپ‘مپ م€‚
مپمپ—مپ¦ç§پمپ¯ن»ٹم€پç¥çµŒç³»م‚’ن¸ه؟ƒمپ«ه¯؟ه‘½مپŒو¥م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€Œه‰چم€په…¥é™¢مپ—مپںو™‚مپ«مپم€پمپٹهŒ»è€…مپ•م‚“مپŒè¨€مپ£مپںمپ®م€‚م‚‚مپ£مپ¦مپ‚مپ¨ï¼‘ه¹´مپ مپ£مپ¦م€‚م€چ
م€Œمپم‚“مپھمƒ»مƒ»مƒ»مپکم‚ƒمپ‚ن»ٹمپ“مپ†مپ—مپ¦مپ„م‚‰م‚Œم‚‹مپ®مپ¯مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپ†ï½م‚“م€پمپ‚مپ®مپم€پو™‚م€…و„ڈèکمپŒمپµمپ£مپ¨éپ مپ®مپڈمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ®م€‚
م€€مپ—مپ°م‚‰مپڈمپ™م‚‹مپ¨وˆ»م‚‹م‚“مپ مپ‘مپ©مپم€‚ه¹¸مپ„وˆ¦é—کن¸مپ«مپھمپ£مپںمپ“مپ¨مپ¯مپ¾مپ مپھمپ„مپ®م€‚
م€€م‚¢مƒ‰مƒ¬مƒٹمƒھمƒ³مپŒه‡؛مپ¦مپ„م‚‹çٹ¶و…‹مپ§مپ¯مپھم‚‰مپھمپ„مپ؟مپںمپ„م€‚
م€€وˆ¦é—کمپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپ¦م€پمپµمپ£مپ¨و°—م‚’مپ¬مپ„مپںو™‚مپھم‚“مپ‹م€پمپ‹مپھï¼ںم€چ
م€Œمپ‚م€پمپ‚مپ®و™‚مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپµمپµم€پو€مپ„ه½“مپںم‚‹مپ“مپ¨مپ‚م‚‹مپ§مپ—م‚‡ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پمپھم‚“مپ‹ه¤‰مپ مپھمپ¨مپ¯و€مپ£مپ¦مپںم‚“مپ مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپ مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»مپم€‚ç§پمپ®مپ“مپ¨مپ¯مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
م€Œمپھم‚“مپ§مƒ»مƒ»مƒ»مپھم‚“مپ§Mikiمپ¯م€پè‡ھهˆ†مپ®ن؛‹مپھمپ®مپ«م€پ
م€€مپم‚“مپھ風مپ«ن»–ن؛؛مپ”مپ¨مپ؟مپںمپ„مپ«è¨€مپ†م‚“مپ ï¼ںم€چ
م€Œمپˆمپ¨مƒ»مƒ»مƒ»مپ†م‚“م€پمپم‚ٹم‚ƒمپ‚م‚„مپ£مپ±م‚ٹم€پ
م€€è‡ھهˆ†مپ®ن؛‹مپ¨مپ¯مپ‚مپ¾م‚ٹو€مپ„مپںمپڈمپھمپ„مپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»مپ‹مپھï¼ں
م€€مپ§م‚‚م€پمپ“م‚Œمپ¯ç¢؛مپ‹مپ«ç§پمپ®ن½“مپ«مپٹمپ“مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپھمپ®م€‚
م€€و¯ژو—¥ه°‘مپ—مپڑمپ¤م€پمپ مپ‘مپ©ç¢؛ه®ںمپ«è¨کو†¶م‚„و„ڈèکمپŒمپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپ„مپڈم€‚
م€€مپ¤مپ¾م‚ٹم€پç§پمپ¯ç§پمپکم‚ƒمپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ®مپ‹مپھم€‚
م€€مپ مپ‹م‚‰مپ•م€پو®‹مپ•م‚Œمپںو™‚é–“مپ§م€پوƒ³مپ„ه‡؛م‚’و›¸مپچç•™م‚پمپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨مپ«مپ—مپںمپ®م€‚
م€€مپ†ï½م‚“مƒ»مƒ»مƒ»مپ”م‚پم‚“مپم€‚Dakiniمپ®و°—وŒپمپ،مپ«و·»مپˆمپھمپڈمپ¦مƒ»مƒ»مƒ»م€‚م€چ
ç§پمپ¯مپکمپ£مپ¨ه½¼مپ®ç›®م‚’見مپ¤م‚پم‚‹م€‚ه½¼م‚‚ç§پم‚’見مپ¤م‚پم‚‹م€‚
(م‚ڈمپ‹مپ£مپ¦مپ„مپںم‚ڈم€پمپ‚مپھمپںمپ®و°—وŒپمپ،م€پ
م€€م€€م€€م€€مپڑمپ£مپ¨ه‰چمپ‹م‚‰مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
م€€مپ‚م‚ٹمپŒمپ¨مپ†م€پ
م€€مپ‚مپھمپںمپ¯مپمپ®و°—وŒپمپ،م‚’مپ“مپ¨مپ°مپ«مپ—مپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€مپم‚Œمپ مپ‘مپ§ç§پمپ¯هچپهˆ†مپ«ه¹¸مپ›مƒ»مƒ»مƒ»ï¼‰
ç›®مپ§مپمپ†èھم‚ٹمپ‹مپ‘م‚‹م€‚
مƒ»مƒ»مƒ»مپ„م‚„م€پمپ م‚پمپ م€‚
م€€م€€م€€ه½¼مپ®هڈ£مپŒمپ‹مپ™مپ‹مپ«ه‹•مپڈم€‚
م€€مپˆم€‚
و®‹مپ•م‚Œمپںو™‚é–“مپŒم‚ڈمپڑمپ‹مپ—مپ‹مپھمپ„مپ®مپھم‚‰م€پمپھمپٹمپ•م‚‰مپ®مپ“مپ¨مپ م€‚
مƒ»مƒ»مƒ»
Mikiمپ®و®‹مپ£مپںو™‚é–“م‚’م€پمپٹم‚Œمپ«مپڈم‚Œم€‚
مƒ»مƒ»مƒ»
ن»ٹمپکم‚ƒمپھمپڈمپ¦مپ„مپ„م€‚مپ“مپ®ن»•ن؛‹مپ«مپ‘م‚ٹمپŒمپ¤مپ„مپ¦مپ‹م‚‰مپ§مپ„مپ„مپ‹م‚‰م€پè؟”ن؛‹م‚’مپڈم‚Œم€‚
مƒ»مƒ»مƒ»مپ†م‚“مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
é™مپ‹مپ§وڑ–مپ‹مپھو™‚é–“مپŒوµپم‚Œمپ¦مپ„مپڈم€‚
ShioriمپŒه¸°مپ£مپ¦مپچمپںم€‚
م€Œمپٹ話م€پ終م‚ڈمپ£مپںمپ‹مپھمپ‚ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚مپ‚م€پو°—م‚’مپ¤مپ‹م‚ڈمپ›مپ¦م€پمپ™مپ¾مپھمپ‹مپ£مپںمپھم€‚م€چ
DakiniمپŒç«‹مپ،ن¸ٹمپŒم‚‹م€‚
م€Œمپˆمپ¸مپ¸م€‚م€چ
ç§پمپ¯ç…§م‚Œç¬‘مپ„مپ™م‚‹Shioriمپ®ه¾Œم‚چمپ«ç«‹مپ£مپںم€‚
م€ŒShioriم€‚م€چ
م€Œم‚“ï¼ںم€چ
م€Œمپ‚م‚ٹمپŒمپ¨م€‚م€چ
مپژم‚…مپ£مپ¨وٹ±مپچمپ—م‚پم‚‹م€‚
م€Œم‚ڈم‚ڈم€پمپم‚“مپھمپ“مپ¨مپ—مپںم‚‰ç§پمپںمپ،مپ®ن»²م€پن؛Œن؛؛مپ«ه¤‰مپھ風مپ«ç–‘م‚ڈم‚Œمپ،م‚ƒمپ†م‚ˆï½م€‚م€چ
م€Œمپم‚Œمپ§م‚‚مپ„مپ„م€پمپ—مپ°م‚‰مپڈمپ“مپ†مپ—مپ¦مپ„مپںمپ„م‚“مپ م€‚م€چ
م€Œمƒ»مƒ»مƒ»مپ†م‚“م€‚م€چ
م€Œمپ•مپ‚م€پمپم‚Œمپکم‚ƒمپ‚م€پمپم‚چمپم‚چè،Œمپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚م€چ
UkiمپŒو¦ه™¨م‚’و‰‹مپ«هڈ–م‚ٹ言مپ†م€‚
م€Œمپ‚مپ‚م€پو°—وŒپمپ،م‚’مپچمپ،م‚“مپ¨هˆ‡م‚ٹوڈ›مپˆمپھمپڈمپ،م‚ƒمپھم€‚
م€€مپ؟م‚“مپھم€پم‚¢مƒ‰مƒ¬مƒٹمƒھمƒ³ه…¨é–‹مپ§مپ„مپڈمپم€‚
م€€ن¸€ç¬مپںم‚ٹمپ¨م‚‚و°—م‚’وٹœمپڈمپھم‚ˆم€‚م€چ
م€Œمپ¯مپ„مپ£م€‚م€چ
م€ŒOKï¼پم€چ
Dakiniمپ®هٹ›ه¼·مپ„ه£°مپ«م€پç§پمپںمپ،مپ¯و°—م‚’ه¼•مپچç· م‚پم‚‹م€‚
مپ¾مپڑمپ¯مپ“مپ®ن»¶مپ«مپچمپ،م‚“مپ¨مپ‘م‚ٹم‚’مپ¤مپ‘م€پç„،ن؛‹مپ«ç”ںمپچمپ¦ه¸°م‚‹مپ“مپ¨م€‚
ه…ˆمپ®مپ“مپ¨م‚’考مپˆم‚‹مپ®مپ¯مپم‚Œمپ‹م‚‰مپ م€‚
م€Œم‚ˆمپ—م€پè،Œمپ“مپ†ï¼پم€چ
و‰‰مپŒé–‹مپڈم€‚
ن¸مپ§مپ¯م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸è‰²مپ®ه…‰م‚’مپ¯مپھمپ¤è»¢é€پ装置مپŒم€پ
ه››è§’مپڈé»’مپ„هڈ£م‚’é–‹مپ‘مپ¦ç§پمپںمپ،م‚’ه¾…مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚
مپمپ—مپ¦ن»ٹم€پç§پمپ¯مپ“مپ®مƒ™مƒƒمƒ‰مپ®ن¸ٹمپ«مپ„م‚‹م€‚
و¯ژو—¥ه°‘مپ—مپڑمپ¤م‚مƒ¼مƒœمƒ¼مƒ‰مپ«م‚€مپ‹مپ£مپ¦م€پوƒ³مپ„ه‡؛م‚’و‰“مپ،è¾¼م‚€م€‚
ه…ˆé€±مپ‹م‚‰ن¸‹هچٹè؛«مپŒو€مپ†م‚ˆمپ†مپ«ه‹•مپ‹مپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپچمپںم€‚
ن¸ٹهچٹè؛«م‚‚مپ„مپ¤é§„ç›®مپ«مپھم‚‹مپ‹م‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپ„م€‚
مپمپ†مپھمپ£مپںم‚‰م€پShioriمپ«é ¼م‚“مپ§ï¼Œç§پمپ®و‰‹مپ«مپھمپ£مپ¦م‚‚م‚‰مپٹمپ†م€‚
Dakiniمپ¨Ukiمپ¯م€په¹³ه’Œمپ«مپھمپ£مپںمƒ©م‚°م‚ھمƒ«مپ«م‚¢مƒںمƒ¥مƒ¼م‚؛مƒ،مƒ³مƒˆمƒ‘مƒ¼م‚¯م‚’è¨ç«‹م€‚
مپںمپ مپ—م€پ話م‚’èپمپ„مپںمƒپمƒ¼مƒ مپ®مپ؟م‚“مپھمپŒم€پوˆ‘م‚‚وˆ‘م‚‚مپ¨ه‡؛資مپ—مپ¦مپڈم‚Œمپںمپ®مپ§م€پ
ه½“هˆè€ƒمپˆمپ¦مپ„مپںم‚‚مپ®م‚ˆم‚ٹم‚‚م€پمپ¯م‚‹مپ‹مپ«ه¤§مپچمپھو–½è¨مپŒه‡؛و¥ن¸ٹمپŒمپ£مپںم€‚
ن»ٹمپ®مپ¨مپ“م‚چé †èھ؟مپ«ه®¢è¶³مپ¯ن¼¸مپ³مپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ م€‚
مپ“مپ®é–“مپ¯UkiمپŒم€پ
م€Œوœ€è؟‘م€په®¢مپŒه‹و‰‹مپ«è‡ھهˆ†مپ§ن½œمپ£مپںو¦ه™¨م‚’وŒپمپ،è¾¼م‚“مپ§مپچمپ¦م€په›°م‚‹مƒ»مƒ»مƒ»م€چ
مپ؟مپںمپ„مپھمپ“مپ¨م‚’言مپ£مپ¦مپںمپ£مپ‘مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
Shioriم‚‚هڈ—ن»کو،ˆه†…ه¬¢مپ¨مپ—مپ¦م€پمپٹه®¢مپ•م‚“相و‰‹مپ«و¥½مپ—مپڈن»•ن؛‹م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹م‚‰مپ—مپ„م€‚
ه؟™مپ—مپ„هگˆé–“م‚’مپ¬مپ£مپ¦م€پمپ؟م‚“مپھم‚ˆمپڈç§پمپ«ن¼ڑمپ„مپ«مپچمپ¦مپڈم‚Œم‚‹م€‚
مپ„م‚„م€په®ںم‚’مپ„مپ†مپ¨Dakiniمپ¯مپ»مپ¨م‚“مپ©ن»•ن؛‹م‚’Ukiمپ«ن»»مپ›مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ؟مپںمپ„م€‚
مپ مپ£مپ¦م€پن»ٹم‚‚ç§پمپ®و¨ھمپ«ه؛§مپ£مپ¦م€پç§پمپŒم‚مƒ¼مƒœمƒ¼مƒ‰م‚’مƒڑمƒپمƒڑمƒپمپ¨وٹ¼مپ—è¾¼م‚€ه§؟م‚’م€پ
é»™مپ£مپ¦مپ«مپ“مپ«مپ“見مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ مپ‹م‚‰م€‚
ç§پمپ¯ç–²م‚Œمپںمپ¨è¨€مپ£مپ¦م‚مƒ¼مƒœمƒ¼مƒ‰م‚’مƒ™مƒƒمƒ‰م‚µم‚¤مƒ‰مپ«ç½®مپڈم€‚
مپمپ—مپ¦ن¸،و‰‹م‚’ه½¼مپ«هگ‘مپ‘مپ¦ه·®مپ—ه‡؛مپ™م€‚
مپ™م‚‹مپ¨م€په½¼مپ®و‰‹مپŒç§پمپ®é م‚’ه¼•مپچه¯„مپ›م€په½¼مپ®وŒ‡مپŒç§پمپ®é«ھم‚’مپ¨مپ‹مپ™م€‚
مپ“م‚“مپھمپ«م€پمپ“م‚“مپھمپ«ه¹¸مپ›مپھن؛؛ç”ںمپ¯مپھمپ„مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»مƒ»م€‚
و³¨
مپ“مپ“مپ‹م‚‰مپ¯ShioriمپŒو›¸مپچمپ¾مپ™م€‚
ه…ˆé€±مپ‹م‚‰Mikiمپ®ن»£م‚ڈم‚ٹمپ«ç§پمپŒم‚مƒ¼مƒœمƒ¼مƒ‰م‚’و‰“مپ¤م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
مƒ©م‚°م‚ھمƒ«و¸©و³‰مپ®è©±مپŒMkiمپ®هڈ£مپ‹م‚‰ه‡؛مپںو™‚مپ¯م€پ
مپ‚مپ‚م€پمپم‚“مپھمپ“مپ¨م‚‚مپ‚مپ£مپںمپ£مپ‘مپھمپ‚مپ£مپ¦م€پ
و‡گمپ‹مپ—مپڈمپ¦م€پو€م‚ڈمپڑو³£مپ„مپ،م‚ƒمپ£مپںم€‚
وکژو—¥مپ¯م€پمƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®م€Œçœںçڈ مپ®و¶™م€چمپ®è©±م‚’و‰“مپ،è¾¼م‚€ن؛ˆه®ڑم€‚
مپٹمپ¨مپ¤مپ„مپڈم‚‰مپ„مپ‹م‚‰م€پMikiمپ¯مپ¨مپ†مپ¨مپ†ç§پمپ®مپ“مپ¨مپŒم‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپڈمپھمپ£مپںمپ؟مپںمپ„م€‚
مپ§م‚‚Dakiniمپ•م‚“مپŒو¨ھمپ«و¥م‚‹مپ¨م€پمپ™مپ”مپڈمپ†م‚Œمپ—مپمپ†مپ«مپ™م‚‹م€‚
مپمپ®و™‚مپ®ç¬‘é،”مپŒم€پمپ™مپ”مپڈمپ‹م‚ڈمپ„مپ„م€‚
ن»ٹو—¥م€پمپٹ見èˆمپ„مپ«م‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚
مپمپ—مپںم‚‰ç›®م‚’مپچم‚‰مپچم‚‰مپ•مپ›مپ¦م€پم‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹م€پم‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ¨è¨€مپ†م€‚
çµمپ£مپ¦م‚¸مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ«مپ—مپںم‚‚مپ®م‚’م‚¹مƒ—مƒ¼مƒ³مپ§هڈ£ه…ƒمپ«م‚‚مپ£مپ¦مپ„مپڈمپ¨م€پ
ç›®م‚’ç´°م‚پمپ¦مپ“مپڈمپ“مپڈه°ڈمپ•مپھéں³م‚’ç«‹مپ¦مپ¦é£²م‚“مپ مپ®م€‚مپمپ—مپ¦
م€ŒShioriمپ¯و،ƒمپ®مپ»مپ†مپŒه¥½مپچمپھم‚“مپ م‚ˆمپم€‚م€چ
مپ£مپ¦م€پمپمپ†مپ¯مپ£مپچم‚ٹ言مپ£مپںمپ®م€‚
وکژو—¥مپ¯و،ƒم‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ“مپ†مپ‹مپھمپ‚م€‚
وœ€ه¾Œمپ¯ç§پم€پDakiniمپŒو›¸مپڈم€‚
Mikiمپ®و›¸مپچو®‹مپ—مپںم‚‚مپ®م‚’مپ“مپ†مپ—مپ¦وœ¬مپ«مپ—مپ¦مپ؟مپںم€‚
è‡ھè²»ه‡؛版مپ م€‚ه£²م‚‹مپ¤م‚‚م‚ٹمپ¯مپھمپ„مپ—م€پم‚‚مپ†مپ‹م‚‹م‚‚مپ®مپ§م‚‚مپھمپ„مپ م‚چمپ†م€‚
مپںمپ م€پç”ںه‰چم€پMikiمپ«è¦ھمپ—مپڈمپ—مپ¦مپڈم‚Œمپںن؛؛مپںمپ،مپ«èھم‚“مپ§م‚‚م‚‰مپˆمپںم‚‰م€پ
ه°‘مپ—مپ¯Mikiم‚‚ه–œم‚“مپ§مپڈم‚Œم‚‹مپ‹مپھمپ¨و€مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
Shioriمپ¯مپ‚م‚Œمپ‹م‚‰مپ—مپ°م‚‰مپڈèگ½مپ،è¾¼م‚“مپ§مپ„مپںمپŒم€پ
UkiمپŒو¯ژو—¥م‚„مپ£مپ¦مپچمپ¦مپ¯هٹ±مپ¾مپ—مپ¦مپ„مپںمپ‹م‚‰م€پ
مپچمپ£مپ¨مپمپ®مپ†مپ،ه…ƒو°—مپ«مپھم‚‹مپ م‚چمپ†م€‚
ن½•مپ¨è¨€مپ£مپ¦م‚‚ه½¼ه¥³مپ«مپ¯ç¬‘é،”مپŒن¼¼هگˆمپ†مپ‹م‚‰م€‚
ن»²é–“مپ®ن¸مپ«مپ¯م€پMikiمپ¨هگŒمپکمپڈçںه‘½مپ§çµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپں者م‚‚مپ„م‚‹م€‚
مپ مپŒم€پçںه‘½مپ مپ‹م‚‰مپمپ®ن؛؛ç”ںمپŒن¸چه¹¸مپ‹مپ¨مپ„مپ†مپ¨م€پمپمپ†مپ§مپ¯مپھمپ„مپ م‚چمپ†م€‚
Mikiمپ¯ه¹¸مپ›مپ مپ£مپںمپ¨و€مپ†م€‚
مپںمپ م€پو®‹مپ•م‚Œمپں者مپŒم€په°‘مپ—مپ¤م‚‰مپ„وƒ³مپ„م‚’مپ™م‚‹م€‚
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ¨Chieمپ•م‚“مپ®é–“مپ«مپ¯هگمپ©م‚‚مپŒç”£مپ¾م‚Œمپںم€‚
Chieمپ•م‚“مپ«ن¼¼مپ¦م€پمپ´م‚‡مپ“م‚“مپ¨é£›مپ³ه‡؛مپں耳مپŒمپ‹م‚ڈمپ„مپ„ه¥³مپ®هگمپ م€‚
مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®ç›®ه…ƒم‚‚مپ“مپ“مپ®مپ¨مپ“م‚چم‚†م‚‹مپ؟مپ£مپ±مپھمپ—مپ م€‚
و£ç›´م€پMikiمپ¨مپ®é–“مپ«هگمپ©م‚‚مپŒمپ§مپچمپ¦مپ„مپںم‚‰مپھمپ¨م€پمپµمپ¨و€مپ†مپ“مپ¨م‚‚ç¢؛مپ‹مپ«مپ‚م‚‹م€‚
مپ§م‚‚م€پMikiمپ¯هگمپ©م‚‚مپ®ن»£م‚ڈم‚ٹمپ«مپ“م‚Œم‚’و®‹مپ—مپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
مپ“م‚Œم‚’èھم‚پمپ°مپ„مپ¤مپ§م‚‚Mikiمپ«ن¼ڑمپˆم‚‹م€‚
وœ؛مپ®ن¸ٹمپ«مپ¯مپ„مپ¤مپ‹ShioriمپŒو’®مپ£مپںMikiمپ®ç«‹ن½“ه†™çœںم€پ
و¨ھمپ«مپ¯ه½¼ه¥³مپ®ه¥½مپچمپھم‚ھمƒ¬مƒ³م‚¸م€پ
مپمپ®ه¥¥مپ«مپ¯ه°ڈمپ•مپھمƒ–مƒƒم‚¯م‚¹م‚؟مƒ³مƒ‰مپŒمپ‚م‚‹م€‚
مپ“مپ®وœ¬م‚’ç½®مپ„مپ¦مپٹمپڈمپںم‚پمپ®م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚
م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€م€€çµ‚م‚ڈم‚ٹ
|